
相続発生から1年間は、相続人の方にとって、故人が亡くなられて負担が多い時期です。
相続手続きに向き合うには、冷静な判断と正確な情報が大切です。
相続とは、大切な人が亡くなった際に財産や権利を受け継ぐ手続きです。
しかし、その内容は複雑であり、法的な要件も多くあります。
また、手続きを行う先は多岐にわたり、必要となる資料や期限もそれぞれ異なります。
そのため、手続きについての正確な情報と適切なタイミングでの準備対応が不可欠となります。
そこで、まずは相続発生から1年間の相続のスケジュールを把握し、それぞれの期間ごとにやるべき手続きとポイントを確認し、次に行うべき手続きを1つ1つ確認しましょう。
今回は、相続が発生してから1年間、何をどうするかについて、お話し致します。
(将来法令等の改正により内容が変わる場合があります。)
相続発生から1年間の全体スケジュール
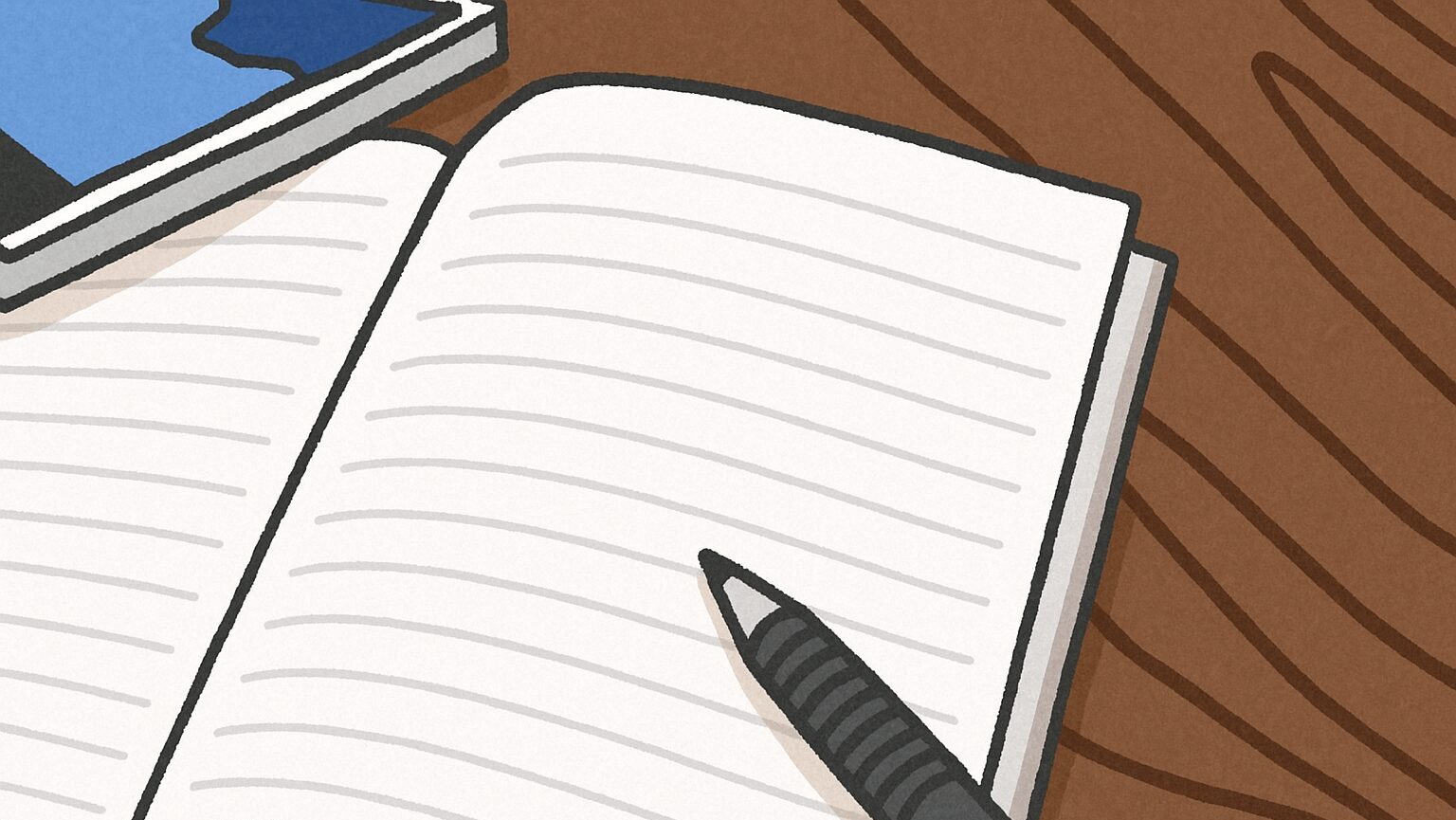
1週間以内にするべきこと
通夜、葬儀・告別式
・葬儀会社
・亡くなってからすみやかに
火葬
・葬儀会社
・亡くなってからすみやかに
初七日法要
・葬儀会社
・原則、亡くなった日から7日目まで
【役所】
死亡届の提出
・役所
・亡くなったことを知った日から7日以内
死体火葬許可証交付申請書の提出
・役所
・亡くなったことを知った日から7日以内
2週間以内にするべきこと
世帯主変更届の提出
・役所
・亡くなった日から14日以内
健康保険の諸手続き
・役所
・亡くなった日から5日以内
国民健康保険の諸手続き
・役所
・亡くなった日の翌日から14日以内
介護保険の諸手続き
・役所
・亡くなった日から14日以内
【年金】
国民年金受給の停止手続き
・年金事務所
・亡くなった日から10日以内
厚生年金受給の停止手続き
・年金事務所
・亡くなった日の翌日から14日以内
遺族年金の請求
・年金事務所
・すみやかに
未支給年金の請求
・年金事務所
・すみやかに
1か月以内にするべきこと
相続人の確定(戸籍の収集)
・役所
・可能な限り早期
保管自筆証明書遺言の検索
・法務局
・遅滞なく
公正証書遺言の検索
・公証役場
・遅滞なく
自筆証書遺言の検索
・家庭裁判所
・遅滞なく
【税務】
個人事業の開業・廃業等届出書の提出
・税務署
・亡くなった日から1か月以内
個人事業者の死亡届書の提出
・税務署
・すみやかに
消費税課税事業者選択届出書の提出
・税務署
・原則、相続開始年の年末まで
消費税簡易課税制度選択届出書の提出
・税務署
・原則、相続開始年の年末まで
【その他】
電気、ガス、水道の名義変更・解約
・電力会社等
・引き継ぐ相続人が決まり次第(もしくは解約などが決まり次第)
固定電話の名義変更・解約
・電話会社
・引き継ぐ相続人が決まり次第(もしくは解約などが決まり次第)
携帯電話の解約
・電話会社
・引き継ぐ相続人が決まり次第(もしくは解約などが決まり次第)
インターネットの名義変更・解約
・プロバイダー
・引き継ぐ相続人が決まり次第(もしくは解約などが決まり次第)
NHKの名義変更・解約
・NHK
・引き継ぐ相続人が決まり次第(もしくは解約などが決まり次第)
運転免許証の返納
・警察署
・すみやかに
クレジットカードの解約
・カード会社
・すみやかに
老人ホーム等の解約、退去清算
・老人ホーム
・すみやかに
2か月以内にするべきこと
四十九日の法要
・寺院
・期限なし
納骨
・寺院
・期限なし
【役所】
葬祭費の支給申請
・役所
・葬式日から2年以内
埋葬料の支給申請
・健康保険組合等
・死亡日の翌日から2年以内
埋葬費の支給申請
・健康保険組合等
・埋葬日の翌日から2年以内
【その他】
死亡保険料の請求
・保険会社
・亡くなった日から3年以内
【税務】
相続税申告の税理士の選定
・税理士
・亡くなった日から2か月くらいまで
3か月~6ヶ月以内にするべきこと
相続放棄
・家庭裁判所
・相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
限定承認
・家庭裁判所
・相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
【税務】
準確定申告書の提出
・税務署
・相続の開始があったことを知ったときから4か月以内
所得税の青色申告承認申請
・税務署
・原則4か月以内
【法務】
財産目録の作成
・亡くなった後6か月程度
特別代理人の選定
・家庭裁判所
・亡くなった後6か月程度
7か月~1年以内にするべきこと
遺産分割協議書の作成
・10か月以内
【税務】
相続税申告書の提出
・税務署
・10か月以内
【法務】
不動産の相続登記
・法務局
・期限なし
【その他】
金融資産の相続手続き
・金融機関
・期限なし
【葬儀】
一周忌法要
・寺院
・期限なし
1年経過後にするべきこと
遺産分割協定
・家庭裁判所
・期限なし
【その他】
相続不動産の売却
・不動産会社
・期限なし
1週間以内にするべきこと

□【葬儀】火葬
□【葬儀】初七日法要
□【役所】死亡届の提出
□【役所】死体火葬許可証交付申請書の提出
通夜、葬儀・告別式【葬儀】
近親者が集まり、亡くなった方の冥福を祈り、別れを惜しむ場となります。
葬儀とは、亡くなった方を伴う宗教的な儀式です。
告別式とは、葬儀の後、出棺前に行われる亡くなった方への別れを告げる儀式です。
葬儀は宗教や宗派によって異なりますが、告別式は宗教的な要素はなく、現代では区別せずに同時に行われることが増えています。
多くの場合、告別式が終わると出棺となり、火葬場に移動して火葬が行われます。
通夜、葬儀・告別式、火葬や初七日法要の具体的なスケジュールなどについては、地域や宗教、個々の状況によって異なる場合があります。
関係者や主催者と相談することが望ましいでしょう。
火葬【葬儀】
法律ではいつまでに火葬しなければならないということは決まっていませんが、死亡後24時間以内での火災は禁止されています。
実施場所:火災場
必要書類:死亡届、死亡診断書、火災許可申請書、火葬料(民営の場合5万円~10万円程度)、位牌、遺影
初七日法要【葬儀】
正式には亡くなった日から7日目に行いますが、参列者の予定が合わない場合も多く、繰り上げるかたちで葬儀と同じ日に執り行うことが増えてきています。
従来は七日法要から四十九日法要まで7回の法要を行っていましたが、現在では生活様式の変化などにより、初七日法要と四十九日法要のみ行うことが増えています。
死亡届の提出【役所】
提出することによって、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
役所に備え付けてあるものに記入して提出します。
市役所等へ提出すると返却してもらえないが、保険請求などにも必要となります。
提出前に、必要枚数以上のコピーを取っておきましょう。
提出先:亡くなった人の本籍地、届出人となる人の住所地、もしくは死亡地の役所
必要書類:死亡診断書(死体検案書)
死体火葬許可証交付申請書の提出【役所】
役所に備え付けられており、死亡届と同時に提出します。
交付された火葬許可証は、火葬のときだけでなく納骨のときにも必要です。
しっかりと保管しておきましょう。
提出先:亡くなった人の死亡地、または本籍地や届出をする方の所在地に該当する役所
必要書類:死亡届、印鑑、火葬料(公営火葬の場合、無料~6万円程度)
2週間以内にするべきこと

□【役所】健康保険の諸手続き
□【役所】国民健康保険の諸手続き
□【役所】介護保険の諸手続き
□【年金】国民年金受給の停止手続
□【年金】厚生年金受給の停止手続き
□【年金】遺族年金の請求
□【年金】未支給年金の請求
世帯主変更届の提出【役所】
世帯に残った者の1人が新しい世帯主になることが明白な場合には、提出不要です。
提出先:亡くなった世帯主の居住地の市区町村役場
必要書類:本人確認書類、印鑑、国民健康保険証 (委任者の場合には委任状)
健康保険の諸手続き【役所】
提出先:協会けんぽや会社が加入していた健康保険組合
必要書類:健康保険資格喪失証明書、マイナンバー、印鑑
国民健康保険の諸手続き【役所】
提出先:亡くなった人の住所地の市区町村役場の窓口
必要書類:国民健康保険資格喪失届、謄本(死亡届)、本人確認書類、印鑑
介護保険の諸手続き【役所】
提出先:亡くなった人の住民票がある市区町村役場の窓口
必要書類:介護保険資格喪失届、介護保険被保険者証
年金受給の停止手続き【年金】
手続きを怠って年金の受給を続けると、不正受給とみなされる可能性があります。
提出先:年金事務所または最寄りの年金相談センター
必要書類:年金証書、死亡の事実を証明できる書類(住民票除票、戸籍抄本など)
遺族年金の請求【年金】
提出先:年金事務所または最寄の年金相談センター
必要書類:基礎年金番号通知書(年金手帳)、戸籍謄本、世帯全員の住民票、死亡者の住民票の除票、請求者および子の収入確認書類、死亡届、受取口座情報
未支給年金の請求【年金】
未支給年金を請求するためには、「未支給年金・未支払給付金請求書」の提出が必要です。
未支給年金は相続財産に該当せず、支給金を受け取った相続人等の一時所得に該当します。
確定申告が必要になる場合があるため注意が必要です。
提出先:年金事務所または最寄りの年金相談センター
必要書類:年金証書、戸籍謄本(法定相続情報一覧図)、受取口座情報 等
1か月以内にするべきこと

□【法務】保管自筆証明書遺言の検索
□【法務】公正証書遺言の検索
□【法務】自筆証書遺言の検索
□【税務】個人事業の開業・廃業等届出書の提出
□【税務】個人事業者の死亡届書の提出
□【税務】消費税課税事業者選択届出書の提出
□【税務】消費税簡易課税制度選択届出書の提出
□【その他】電気、ガス、水道の名義変更・解約
□【その他】固定電話の名義変更・解約
□【その他】携帯電話の解約
□【その他】インターネットの名義変更・解約
□【その他】NHKの名義変更・解約
□【その他】運転免許証の返納
□【その他】クレジットカードの解約
□【その他】老人ホーム等の解約、退去清算
相続人の確定(戸籍の収集)【法務】
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を入手します。
戸籍謄本等の入手期限はありませんが、各種手続きに必要となるため、最初に取得すべき書類です。
転籍や婚姻等により戸籍が複数ある場合には、そこから遡って出生までの除籍謄本や改製原戸籍を取得しなければなりません。
取得先:本籍地のある市区町村の戸籍係
必要書類:各自治体の戸籍交付申請書、印鑑(認印でも可)、本人確認書類
【法定相続情報証明制度】
法定相続情報証明制度とは、相続関係を一覧にまとめた図(法定相続情報一覧図)を登記所に提出することによって、登記官が認証文を付した写しを無料で交付する制度です。
これにより、相続に伴う登記移転手続きや預金払い戻しにおいて、繰り返し戸籍除籍謄本を提出する手間が省け、相続手続きが円滑に進む利点があります。
保管自筆証明書遺言の検索【法務】
遺言書保管事実証明書の交付の請求により、この自筆証書遺言が法務局で保管されているどうか、確認を取ることができます。
また、検索の結果、事実証書遺言が存在した場合には、遺言書情報証明書の交付の請求により、その遺言の内容を確認することができます。
相続人等の誰かが遺言書情報証明書の交付を受けると、請求者以外のすべての相続人等に対して、関係する遺言書を保管している旨の通知が行われます。
請求先:最寄りの保管場所(法務局)
必要書類:戸籍(除籍)謄本、相続人の住民票の写し、本人確認書類
公正証書遺言の検索【法務】
公正証書遺言の存在の有無は、直接公証役場へ出向き、遺言書検索システムを利用することによって、全国どこの公証役場でも検索ができます。
一方で検索の結果、公正証書遺言があった場合には、その交付を請求できるのは。原本が保管されている公証役場だけです。
遠方の場合には、郵送対応も可能となっていますが、最寄りの公証役場で。公正証書謄本交付申請書の署名認証を受けなければなりません。
公証役場では予約が取れるので、事前に連絡して予約をするとともに、必要資料の確認をしておきましょう。
請求先:最寄りの公証役場
必要書類:戸籍(除籍)謄本等、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、本人確認書類
自筆証書遺言の検索【法務】
自宅等で亡くなった人の遺した遺言が発見された場合には、検認を行わなければなりません。
検認はあくまで「状態や内容を確認し、そのときの状態を保存する手続き」であり、遺言が有効か無効かを判断する手続きとはなりません。
請求先:家庭裁判所
必要書類:検認申立書、遺言者の出生から死亡まで連続戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本
個人事業の開業・廃業等届出書の提出【税務】
相続人は、被相続人の事業を引継ぐ場合には、相続人自身の事業開始の手続きとして、「個人事業の開業・廃業等届出書」を、亡くなった日から1か月以内に提出しなければなりません。
提出先:(被相続人の廃業)被相続人の納税地の税務署、(相続人の開業)相続人の納税地の税務署
必要書類:本人確認書類
個人事業者の死亡届書の提出【税務】
また、被相続人がインボイス登録をしていた場合には、亡くなった日の翌日から4か月以内に「適格請求書発行事業者の死亡届出書」の提出をしなければなりません。
提出先:相続人の納税地の税務署
必要書類:本人確認書類
消費税課税事業者選択届出書の提出【税務】
亡くなったのが提出期限前概ね1か月以内など、年末までに提出することが事実上困難な場合には、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に「特例承認申請書」を提出することによって、相続があった年から適用を受けることができるようになります。
提出先:相続人の納税地の税務署
必要書類:消費税課税事業者選択届出書
消費税簡易課税制度選択届出書の提出【税務】
亡くなったのが提出期限前概ね1か月以内など、年末までに提出することが事実上困難な場合には、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に「特例承認申請書」を提出することによって、相続があった年から適用を受けることができるようになります。
提出先:相続人の納税地の税務署
必要書類:消費税簡易課税制度選択届出書
電気、ガス、水道の名義変更・解約【その他】
特に期限等はなく、電話やネットでの手続きで完結することができます。
各種公共料金が口座振替やカード払いとなっている場合において、被相続人の口座が凍結されたときは、送られてきた請求書(払込書)によって支払いを行うことになります。
提出先:電力会社、ガス会社、水道局
必要書類:(解約)基本的に必要なし、(名義変更)依頼書、口座振替依頼書
固定電話の名義変更・解約【その他】
特に期限等はなく、ネットでの解約申込や名義変更手続きもできます。
携帯電話の場合、原則として最寄りの携帯ショップに連絡を行い、直接店舗での解約手続きを行います。
提出先:NTT
必要書類:死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、死亡診断書等)、本人確認書類、名義変更の場合には相続関係が確認できる書類(相続人の戸籍や法定相続情報)
携帯電話の解約【その他】
提出先:携帯ショップ
必要書類:死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、死亡診断書等)、本人確認書類、名義変更の場合には相続関係が確認できる書類(相続人の戸籍や法定相続情報)
インターネットの名義変更・解約【その他】
また、解約の場合に、機器の返却が必要であれば指示に従って返却を行います。
提出先:回線業者・プロバイダー
必要書類:死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、死亡診断書等)、本人確認書類
NHKの名義変更・解約【その他】
解約の場合はネットでの手続きはできませんが、名義変更の場合にはネットでの手続きだけで終えられることがあります。
提出先:NHKふれあいセンター
必要書類:放送受信契約解約届、死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、死亡診断書等)
運転免許証の返納【その他】
特に期限等はありませんが、死亡によって免許は失効します。速やかに行いましょう。
提出先:最寄りの警察署
必要書類:故人の運転免許証、死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、死亡診断書等)
クレジットカードの解約【その他】
電話のみで手続きが済む場合もありますが、カード会社によっては書類の提出が必要なケースもあります。
提出先:カード会社
必要書類:退会届等各種届出書、死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、死亡診断書等)、相続関係が確認できる書類(相続人の戸籍や法定相続情報)
老人ホーム等の解約、退去清算【その他】
必要な書類や手続きは老人ホームの方針や契約内容によって異なりますので、担当者に確認してください。
未使用のサービスや施設の利用料金の返金や調整、資金や保証金の返却、退去時の清掃費用や修繕費用の清算等が必要です。
提出先:老人ホーム
必要書類:施設・契約によって異なります。
2か月以内にするべきこと

□【葬儀】納骨
□【役所】葬祭費の支給申請
□【役所】埋葬料の支給申請
□【役所】埋葬費の支給申請
□【その他】死亡保険料の請求
□【税務】相続税申告の税理士の選定
四十九日の法要【葬儀】
亡くなった日から数えて、四十九日目を忌明けと呼び、遺族はこの日を境として喪に服していた期間を終えます。
四十九日法要は菩提寺にて遺族、親族、親しい友人等を招いて行うことが一般的です。
四十九日法要の準備項目
菩提寺に連絡、本位牌の準備、案内状の送付、供物・供花の準備、お斎(会席)の準備、お布施の準備
納骨【葬儀】
納骨は、多くは四十九日法要や一周忌法要に合わせて実施します。
納骨式は、墓前で行い、供物、供花を並べます。
その後、遺骨を墓石に納め、僧侶による読経、参列者による焼香を行います。
納骨には、埋葬許可証が必要ですので、火葬後に証明印が押印された埋葬許可証を準備しておきましょう。
※埋葬許可証
一般的に、火葬許可証に火葬場で火葬済みの証明印を押印したものが埋葬許可証として使用されます。
自治体によっては、「火葬証明書」や「埋葬許可証明書(許可証)と呼ばれることや、火葬許可証とは別の書類として発行される場合もあります。
納骨の準備項目
埋葬許可証の準備、菩提寺に連絡、卒塔婆の準備、供物・供花の準備、読経料の準備
葬祭費の支給申請【役所】
市区町村によって違い、1万円から7万円前後です。
なお、会社員等で社会保険加入者は埋葬料であり、個人事業主等の国民健康保険の被保険者は葬祭費です。
申請してから2、3週間ほどで支給されます。
葬祭費は、相続税、所得税は非課税です。
提出先:住所地の役所
必要書類:申請書、除籍謄本、住民票除票、死亡診断書(死体検案書)、葬儀の領収書。埋葬許可証、申請者の身分証明書類
埋葬料(費)の支給申請【役所】
埋葬料と埋葬費の違いは、亡くなった人の家族が申請する場合は埋葬料、亡くなった人の家族がいない場合で実際に埋葬を行った人が申請する場合は埋葬費、という点です。
なお、会社員等で社会保険加入者は埋葬料であり、個人事業主等の国民健康保険の被保険者は葬祭費です。
申請してから2、3週間ほどで支給されます。
埋葬料(費)は、相続税、所得税は非課税です。
提出先:健康保険組合等
必要書類:申請書、除籍謄本、住民票除票、死亡診断書(死体検案書)、葬儀の領収書。埋葬許可証、申請者の身分証明書類
死亡保険料の請求【その他】
被保険者の死亡日から3年を経過すると、保険金の請求権が時効により消滅すると保険法に定められています。
ただし、3年経過しても保険会社が時効を主張せずに支払いに応じてくれるケースもあるため、保険会社に相談してみましょう。
死亡保険金は受取人の固有財産であるため、遺産分割の対象にはなりません。
契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人がだれかによって、かかる税金(相続税、贈与税、所得税)が変わるので注意しましょう。
相続税には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されています。
提出先:保険会社
必要書類:死亡保険金請求書(保険会社から送られてきます)、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本、受取人の印鑑登録証明書、死亡診断書(死体検案書)、保険証券 等
相続税申告の税理士の選定【税務】
まずは、不動産、有価証券、現金、預貯金、生命保険金などの合計額が基礎控除額を超えるかどうか確認しましょう。
相続税申告の期限は、相続開始を知った日から10か月以内(通例は亡くなった日の10か月後の応当日)となります。
それまでに相続税申告を終わらせるためにも、亡くなったあと2か月くらいまでには税理士を選定しておいたほうがいいでしょう。
税理士にも医者と同じように専門分野があります。
相続税申告を専門に取り扱っている税理士に依頼しましょう。
【チェックポイント】
① 相続専門の税理士もしくは税理士法人
② 相続税申告の実績と経験
③ 担当者が税理士資格を持っていること
④ 税理士報酬の額 遺産総額の0.5%~1%の範囲内であって適正であること
⑤ 二次相続の提案があること
⑥ 税務調査率が低いこと
⑦ アフターサービスの充実
3か月~6ヶ月以内にするべきこと

□【法務】限定承認
□【税務】準確定申告書の提出
□【税務】所得税の青色申告承認申請
□【法務】財産目録の作成
□【法務】特別代理人の選定
相続放棄【法務】
被相続人に多額の借金があり引き継ぎたくない場合や、相続争いに巻き込まれたくないような場合に、相続放棄を選択することがあります。
相続放棄のポイント
■相続人1人でも相続放棄ができます。
■第1順位である子の全員が相続放棄をした場合、第2順位の親(親が既に亡くなっている場合は第3順位の兄弟姉妹)が相続人となってしまうため、次順位の相続人にも借金等を引き継がせたくない場合には次順位の相続人も相続放棄をしなければなりません。
■生命保険等のみなし相続財産は、相続放棄をしても受け取ることができます。
■相続放棄をすることにより相続税法上不利益が生じることもあるので、相続税がかかる場合には事前に専門家へ相談しましょう。
提出先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用:収入印紙800円、連絡用の郵便切手代
必要書類:申述書、被相続人の戸籍謄本、住民票除票、申述人の戸籍謄本 等
限定承認【法務】
財産と借金のどちらが多いかわからない場合などに、限定承認を選択することがあります。
限定承認のポイント
■共同相続人全員の同意が必要です。
■限定承認をすると、税制のうえでは被相続人から相続人へ相続財産を売却したとみなされ、相続財産に含み益がある場合には、被相続人の準確定申告が必要となり、相続人に所得税の負担が生じる可能性があります。
提出先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用:収入印紙800円、連絡用の郵便切手代
必要書類:申述書、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本、住民票除票、申述人の戸籍謄本 等
準確定申告書の提出【法務】
※相続人が複数いる場合には、原則として各相続人等が連署により準確定申告書を提出します。
提出先:被相続人の最後の住所を所轄する税務署
確定申告書:確定申告書、確定申告書付表、収支内訳書、青色申告決算書。給与・年金の源泉徴収票、所得控除関連書類、相続人のマイナンバーカード 等
所得税の青色申告承認申請【税務】
相続開始年からお会い路申告するための申告期限
■1/1~8/31までに相続が開始 相続開始か日から4か月以内
■9/1~10/31までに相続が開始 相続開始年の12/31まで
■11/1~12/31までに相続が開始 相続開始年の翌年2/15まで
請求先:相続人の住所地を所轄する税務署
必要書類:青色申告承認申請書
財産目録の作成【法務】
この財産目録に基づいて遺産分割協議をすることとなります。
提出先:提出なし
必要書類:固定資産税の課税明細書、不動産の全部事項証明書、預金の残高証明書、有価証券の残高証明書、債務・葬式費用関係書類、その他相続財産の評価に必要となる書類
特別代理人の選定【法務】
提出先:未成年者等の住所地の家庭裁判所
費用:被相続人の最後の住所を所轄する税務署
必要書類:申立書、未成年者の戸籍謄本、親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、遺産分割協議書案、不動産の登記簿謄本 等
7か月~1年以内にするべきこと

□【税務】相続税申告書の提出
□【法務】不動産の相続登記
□【その他】金融資産の相続手続き
□【葬儀】一周忌法要
遺産分割協議書の作成【法務】
遺産分割協議自体は口頭でも成立しますが、後々トラブルにならないことや相続税申告相続登記などの相続手続きで書面が必要となることから、遺産分割協議書を作成する事が通例です。
遺産分割協議書の作成には法的な期限はありませんが、遺産分割協議書を相続税申告書に添付することを考えると、相続税申告の期限である10か月以内には遺産分割協議書も作成しておくべきでしょう。
遺産分割の方法
■現物分割:遺産をそのままの状態で分割する方法。遺産分割の原則的な方法。
■換価分割:不動産や株式などの換金可能な遺産をそのまま相続するのではなく、売却して現金にした後その現金を分ける方法。
■代償分割:特定の相続人が特定の財産を取得した代わりに、代償財産をほかの相続人に交付する方法。
■共有分割:遺産を複数の相続人で共有して相続する方法。
提出先、形式要件、印鑑登録証明書の期限
■相続税申告 提出先:税務署、形式:署名実印、印鑑登録証明書:相続開始後であれば期限なし
■不動産登記 提出先:法務局、形式:記名実印、印鑑登録証明書:相続開始後であれば期限なし
■金融資産の相続 提出先:金融機関、形式:署名実印、印鑑登録証明書:3か月~6か月
相続税申告書の提出【税務】
相続税申告のポイント
■配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用により相続税がゼロになったとしても、相続税申告書を税務署に提出しなければなりません。
■相続人や親族名義であっても、被相続人が拠出し管理していた金融資産は相続税の対象となります。
■遺産分割が申告期限までに決まらなかったとしても、申告・納税は期限までにしなければなりません。その場合には配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例等は適用できません。
提出先:被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署
必要書類:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺言書、遺産分割協議書、固定資産税の課税明細書、預金の残高証明書、証券の残高証明書、生命保険の支払通知書、債務や葬式費用の領収書 等
※相続税申告の必要資料は、多岐に渡ります。詳細は税理士に確認しましょう。
不動産の相続登記【法務】
不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記することが義務付けられています。
相続登記のポイント
■登録免許税が不動産の固定資産税評価額の0.4%の割合でかかります。
■郵送でも手続きはできますが、窓口に持参すれば相談窓口で申請前に相談することができます。
■登記完了までは、申請から2~3週間程度はかかります。
提出先:不動産を管轄する法務局
必要書類:登記申請書、固定資産評価証明書、相続関係説明図、戸籍謄本、被相続人の住民票除票、取得者の住民票、印鑑登録証明書、遺言書、遺産分割協議書
金融資産の相続手続き【その他】
金融機関に相続手続きの連絡をすることにより口座が凍結されてしまうため、水道光熱費等の自動引き落としや家賃等が入金されている口座は、連絡をするタイミングに注意しましょう。
相続税申告や遺産分割協議で残高証明書が必要になる場合には、相続手続き前に発行依頼をしましょう。
提出先:金融機関
必要書類:相続届出、戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺言書、遺産分割協議書
一周忌法要【葬儀】
命日が平日の場合には、その前の休日に行うことが一般的です。
なお、一周忌法要以降の年忌法要としては。 三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌等がありますが、最近は七回忌まで実施して、その後の法要は省略することも多くなっています。
一周忌法要には、遺族、親族等を招いて、お寺や自宅で法要を行います。
一周忌法要の準備項目
■菩提寺に連絡
■本位牌の準備
■案内状の送付
■供物・供花の準備
■お斎(会席)の準備
■お布施の準備
1年経過後にするべきこと

□【その他】相続不動産の売却
遺産分割協定【法務】
遺産分割調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員から組織される調停委員会が相続人双方の意見を聞いて、中立的な立場で遺産分割の調停を斡旋します。
調停は月に1度のペースで、最低でも5回程度実施されるため、結果がまとまるまで1年程度かかることもあります。
調停でも遺産分割がまとまらなければ、審判、裁判に移行することになり、さらに長期化します。
申立先:相手方の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本(相続人の住民票)、印鑑登録証明書、遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、預貯金等の残高証明書等)
相続不動産の売却【その他】
仲介業者との売買契約は、一般媒介、専任媒介等の複数種類の中から、売主や売却物件に応じて適切なものを選択します。
売却した場合において、利益が出ていた場合には所得税が課税されます。
所得税上の各種特例(空き家特例、取得費加算等)の適用についても検討しましょう。
終わりに
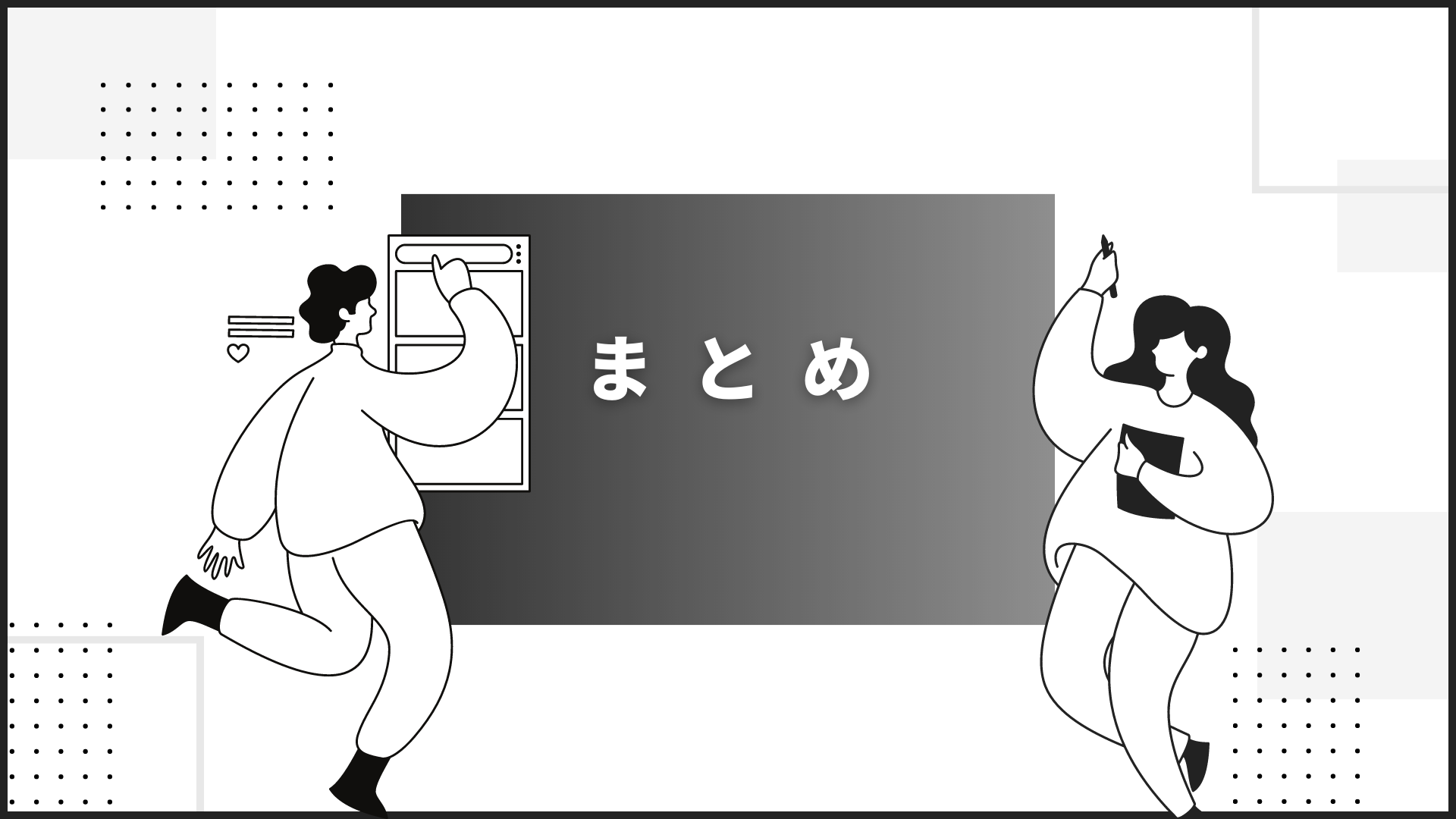
特に大切な方が亡くなられた後は精神的にもつらいときですが、多くの手続きが控えています。
改めて、人は多くのことと関係しながら生きてきているのだということを実感するでしょう。
相続の手続きには、冷静な判断と正確な情報が大切です。
これらの手続きは、すぐに済ませられるものではありません。
1つ1つ適切に対応していくとよいでしょう。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
