
不動産取引を行ううえで、登記は極めて重要な事柄です。
登記に関係する法規である不動産登記法では、この法律の目的を、不動産の表示および不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする、としています。
なお、不動産所有者に対し不動産売却を促すダイレクトメールが届くことを気味悪いと言われることが度々ありますが、不動産登記によってその権利を公示している、つまり公の機関が周知させ一般の人が知ることができるようにしているのです。
その利用の仕方については、議論の対象となるでしょうが、公示を否定することは登記制度に疑問を呈することになります。
では、具体的に登記にはどのような目的があり、どのような効力があるのでしょうか。
今回は、登記の目的とその重要性について、お話し致します。
登記の目的と重要性

登記の手続きについては、不動産登記法、その他の法令で定められています。
登記される権利
登記をすることができる権利は、土地・建物についての所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権、採石権の10種類です。
これに対し、占有権と留置権は占有という外形的な事実に基づく権利であるため、登記という公示を要求する必要はないことから、それらは登記不要(登記できない)とされています。
なお、入会権もその権利内容が監修によって決まるため、登記による公示に適さないゆえ、登記がなくても対抗力があります。
物件そのものではないですが、買戻権の登記、物件取得を目的とする請求権の仮登記を認められています。
登記の対抗力
所有権の移転や抵当権の設定という不動産の物権の変動は、当事者の意思表示だけで効力が生じます(民法第176条)。
しかし、そのことを当時者以外の第三者に主張するためには、登記をしなければならないという意味です。
要するに、対抗することができないという意味は、たとえ権利者であっても登記がされていない限り、当事者以外の者に対しては物権変動のあったことを主張できないということです。
登記がないと対抗できない第三者
判例上、当事者およびその包括承継人(相続人、包括受遺者)以外の者で、登記の欠缺(不存在)を主張する正当な利益を有する者をいいます。
学説上は、その物件変動と両立し得ない利害関係を有するに至った者、いわば正当な競争関係にある者のみをいう、と解されています。
例えば、同一の不動産について二重に譲り受けた者、地上権・抵当権の設定を受けた者、あるいは賃借した者、差し押さえた債権者等は、正当な競争関係にあるため、ここにいう「第三者」に該当するが、その土地・建物を不当に占拠している者や、その不動産に何らの実質的な権利を有しない者等は、「第三者」に当たらないと解されています。
詐欺または脅迫によって登記の申請を妨げた者、他人のために登記の申請をする義務のある者は、他人に登記がないことを主張することができません。
ここで「第三者」に該当するか否かの問題で誤解してはならないことは、不動産の二重譲渡がなされた場合に、例えば第2の譲受人がその不動産を取得した時点において、既に自分より先の第1の譲受人が存在していることを知っていた(すなわち、悪意であった)としても、先に登記をすれば確定的に権利を取得できるということです。
先に登記したものが勝つという登記制度がありながら、二重譲渡の場合に常に「知っていたか、知らなかったか」という内心の事実を問題としていたのでは、自由競争は成り立たないためです。
しかし、例えば、第1の譲受人にまだ登記がなされていないことを幸いに、その者に単に嫌がらせをしてやろうとか、その不動産をどうしても欲しがっている者に高く売りつけようなどと考えて、元の所有者から取得のうえ、先に登記したものを勝たせることは、正義公平の観点からも妥当ではありません。
そのような者を背信的悪意者といいますが、判例は、第1の譲受人は背信的悪意者に対して登記なくして対抗できるものとしています。
権利の推定力
このことを、登記の権利推定力または単に推定力といいます。
登記に公信力なし
しかし、民法はこれを採用せず、例え登記を真実のものだと信頼して取引に入ったとしても、権利を取得できないという建前をとっています。
このことを、登記に公信力がないといいます。
これは、真実の権利者の利益を保護するためです。
したがって、ある人から不動産を買い受けようとする者や、金銭を貸して抵当権を設定しようとする債権者は、取引の相手方に単に登記名義が存在するということだけでなく、その登記の原因となった実体関係の有無およびその有効性も確認しなければならないといえます。
このような確認を容易にするために、権利変動の過程を忠実に登記記録に公示することが、不動産登記制度の重要な役割です。
ちなみに、動産の取引の場合は、他人の占有を信じて取引した者は、一定の要件のもとに保護され、信じたとおりの権利を取得します(民法第192条)。
すなわち、動産の占有には公信力があるということになります。
動産は不動産の場合と異なり、頻繁に取引が行われ、取引の安全を図る必要性が大きいためです。
登記記録(登記簿)

登記記録は、土地および建物について編成され、これは土地と建物がまったく別個独立の不動産とされていることの表れです。
登記記録(登記簿)の構成
1つの登記記録(登記簿)は、表題部および権利部としての甲区および乙区の3つの記録から構成されます。
ただし、区分所有建物にあっては、区分所有建物ごとの表題部、権利部としての甲区および乙区のほかに一棟全体の所在、構造、床面積を記録した一棟の建物の表題を各個の区分所有建物の専有部分の表題部の登記記録の前に編成します。
ある不動産について登記がなされているということは、少なくとも表題部の記録があるといえますが、常に甲区、乙区の記録があるわけではありません。
乙区に登記すべき事項がなければ乙区の記録は設けられず、甲区に登記すべき事項がなければ甲区の記録も設けられないのが通常です。
なぜなら、権利部の登記は義務ではないからです。
各部分に登記される事項は、次のとおりです。
(1) 表題部
土地・建物の表示に関する事項、すなわち、不動産番号、地図番号、筆界特定、所在、地番、地目、地積あるいは種類、構造、床面積など、土地・建物の物理的現況が記録されます。
(2) 権利部
① 権利部・甲区
事項欄と順位番号欄があり、事項欄には「所有権」に関する事項が記載され、順位番号欄には、事項欄のそれぞれの登記の順番を示す番号が記録されます。
② 権利部・乙区
甲区と同じく、事項欄と順位番号欄がありますが、所有権以外の権利、すなわち地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権、採石権に関する事項が記録されます。
区分所有建物の登記
不動産登記法では、登記された敷地利用権で専有部分と分離処分できないものを敷地権といいます。
具体的には、所有権、地上権、土地賃借権のいずれかです。
敷地権は、一棟の建物および専有部分の表題部に登記すべきものとされ、敷地権の表示の登記をしたときは、敷地権の目的となっている土地の登記記録(登記簿)の相当事項欄に敷地権である旨の登記が登記官の職権をもってなされ、建物とその敷地利用権が一体であることが公示されます。
なお、相当区事項欄とは、その敷地利用権が所有権のときは甲区欄、地上権または賃借権のときは乙区欄のことをいいます。
敷地権化されていない場合は、土地の登記記録を取り寄せて、共用共有持分を膨大な記録から調査することを要します。
権利の順位
登記の前後によるというのは、時間的に先になされた登記が後になされた登記に優先するということです。
そして当期の前後は、登記記録の同区(同じ区、すなわち甲区なら甲区、乙区なら乙区)にされた登記の間では、順位番号によります。
別区(甲区と乙区)にされた登記の間では、受付番号によります。
ただし、付記登記は主登記の順位により、仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は当該仮登記の順位によります。
参考:民法第331条(不動産の先取特権の順位)【e-GOV】
登記事項証明書の交付等および附属書類の閲覧

登記事項証明書の交付
(2) 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる
(3) 上記(1)の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができます。
地図の写しの交付
(2) 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができます。
登記簿の附属書類の写しの交付
(2) 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができます。
附属書類の閲覧
地図等または登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様です。
(1) 請求人の氏名または名称
(2) 不動産所在事項または不動産番号
(3) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
(4) 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、登記事項証明書の区分
(5) 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録または信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
(6) 地図等または土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
(7) 送付の方法により登記事項証明書、地図等の全部もしくは一部の写しまたは土地所在図等の全部もしくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨および送付先の住所
② 不動産登記法第121条第3項または第4項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第1号および第2号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とされています。
(1) 請求人の住所
(2) 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
(3) 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名または名称および住所ならびに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
(4) 不動産登記法第121条第3項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分および当該部分を閲覧する正当な理由
(5) 不動産登記法第121条第4項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨
③ 前②の(4)の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければなりません。
この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面またはその写しを登記官に提出しなければなりません。
④ 前②の(5)の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければなりません。
この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面またはその写しを登記官に提出しなければなりません。
⑤ 前②の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければなりません。
ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでありません。
⑥ 前②の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければなりません。
ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りではありません。
⑦ 法人である代理人によって前②の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しません。
公図(地図に準ずる図面)
このため、土地の区画や地番を明確にした地図を備え付けることによって、土地の位置形状を明らかにしなければなりません。
現在、登記所に備え付けられている地図は、国土調査法等に基づいて作成された不動産登記法に規定する正確な地図(不動産登記法第14条第1項)と、明治初期、地租改正に伴い作成された旧土地台帳附属地図とが備え付けられています。
一般に公図といわれているものは後者の地図を指しており、この意味での公図は14条地図に準ずる図面で、14条地図が備え付けられるまでの補完的図面として備え付けられているものです。
現在、国土地理院、地方公共団体等の協力を得て、日本全土にわたって精密な測量作業が行われていますが、まだ約半数程度しか実施されておらず、ほとんどの都市部では補完的図面としての公図が活用されているのが現状です。
登記情報提供サービス
現在電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第4条第1項の業務を行う者(指定法人)として、一般財団法人民事法務協会が指定されており、同協会が運営するホームページから登記情報提供サービスが利用できます。
提供される情報としては、下記の情報等があります。
(1) 不動産の登記記録
(2) 商業登記記録
(3) 法人の登記記録
(4) 動産譲渡登記事項概要ファイル
(5) 債権譲渡登記事項概要ファイル
(6) 地図、建物所在図、地図に準ずる図面、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面および各階平面図が記録されたファイル
所有権の移転登記に必要な書類

その場合の登記申請に必要な一般的となる必要書類等は以下のとおりです。
売主の必要書類
登記済権利証(登記識別情報通知)は、あらかじめ売買契約時などに原本を確認して、コピーやPDFなどデータを取り、決済立会する司法書士へ事前に送付し確認してもらうことが望ましいでしょう。
① 登記済権利書(登記識別情報通知)を所持していることは、物件所有者であることを推認させる一番の資料となります。早めに確認することによって、地面師などによるなりすまし対策にもなります。
② 登記済権利証(登記識別情報通知)がない場合、司法書士による事前の本人確認面談が必要となります。
③ 売主が原本だと信じていたものがカラーコピーだった、権利証に記載されている受付番号と登記記録の受付番号の齟齬があったなど、予期しない事態に前もって対応できます。
(2) 印鑑証明書
① 登記申請日から、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
② 印鑑証明書も権利証と同様に、あらかじめ売買契約時などに原本を確認して、コピーやPDFなどデータを取り、決済立会する司法書士へ事前に送付し確認してもらうことが望ましいでしょう。
③ 印鑑証明書に記載されている住所(氏名)と登記記録に記載されている住所(氏名)に齟齬がある場合は、住所(氏名)変更登記が必要となります。
(3) 本人確認書類
犯罪収益移転防止法上の要件を満たす本人確認書類が必要です。
あらかじめ売買契約時などに原本を確認して、コピーやPDFなどデータを取り、決済立会する司法書士へ事前に送付し確認してもらうことが望ましいでしょう。
免許証の偽造や変造などを事前に判断する材料となります。
(4) 実印
登記委任状に、実印で捺印しなければなりません。
実印を紛失している場合や、実印が欠けていて印鑑証明書の印影と一致しない場合、銀行のお届け印と混同している場合などもありますので、事前に確認すべきでしょう。
(5) 固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税課税明細書 ※申請年度のもの
登録免許税や司法書士報酬を算定するために必要です。
(6) その他
司法書士作成の登記委任状や登記原因証明情報に、署名・押印が必要です。
買主の必要書類
マイナンバーの記載は不要です。
(2) 印鑑証明書
① 抵当権(根抵当権)設定登記がある場合は必要です。
② 登記申請日から、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
(3) 本人確認書類
犯罪収益移転防止法上の要件を満たす本人確認書類が必要です。
あらかじめ売買契約時などに原本を確認して、コピーやPDFなどデータを取り、決済立会する司法書士へ事前に送付し確認してもらうことが望ましいでしょう。
免許証の偽造や変造などを事前に判断する材料となります。
(4) 実印・認印
買主は、登記関係書類については基本的に認印で足ります。
ただし、抵当権設定登記委任状の印影に不備がある場合など、再度押印し直すケースがあるため、決済時に実印を持参すると急な対応が可能となります。
(5) その他
司法書士作成の登記委任状や登記原因証明情報に、署名・押印が必要です。
その他注意すべき添付書類
(2) 成年後見人が家庭裁判所の許可を得て、成年被後見人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可審判書が必要です(民法第859条の3)。
(3) 利益相反取引(会社法第356条)に該当する場合、利益相反取引を承認する株主総会議事録(取締役会非設置会社の場合)、取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)が必要です。
仮登記

仮登記がどのような場合にできるかについては、不動産登記法第105条で規定しています。
仮登記の種類
・・不動産登記法第105条第1号:1号仮登記
登記すべき物件変動はすでに生じているが、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しないときに行うことができるものとされてます。
【例】
① 登記義務者(売主等)の登記識別情報または登記済証が提出できない場合
② 登記原因について第三者の許可、同意、承諾を証する書面の添付ができない場合(農地法に定める都道府県知事の許可書の添付ができない場合など) ※1号仮登記は許可等が与えられていることが前提。
(2) 請求権保全の仮登記
・・不動産登記法第105条第2号:2号仮登記
物件変動はまだ生じていないが、登記すべき不動産に関する権利の設定、移転、変更または消滅の請求権を保全するときであって、この請求権が条件付きであったり、始期を定めた場合に行うことができます。
【例】
① 売買の予約を行った場合
② 代物弁済予約を行った場合
仮登記の申請手続
ただし、例外として、仮登記義務者の承諾があるとき、または仮登記を命じる処分があるときは、登記権利者の単独申請の方法も認められています(不動産登記法第107条第1項)。
仮登記をすると、その仮登記された欄の下に予約が設けられます。
これは、仮登記に基づく本登記をその余白にすることにして、本登記の順位が仮登記の順位によることを一目瞭然することができるためです。
仮登記の効力
後日に、その仮登記に基づく本登記をすることによって、はじめて第三者へ対抗力をもちます。
本登記がなされることにより、仮登記後になされた第三者(利害関係人)の登記は、仮登記に基づく本登記と矛盾する範囲で、利害関係人の承諾書(印鑑証明書付)を添付することによって、登記官の職権により抹消されます(不動産登記法第109条第1項、第2項)。
配偶者居住権
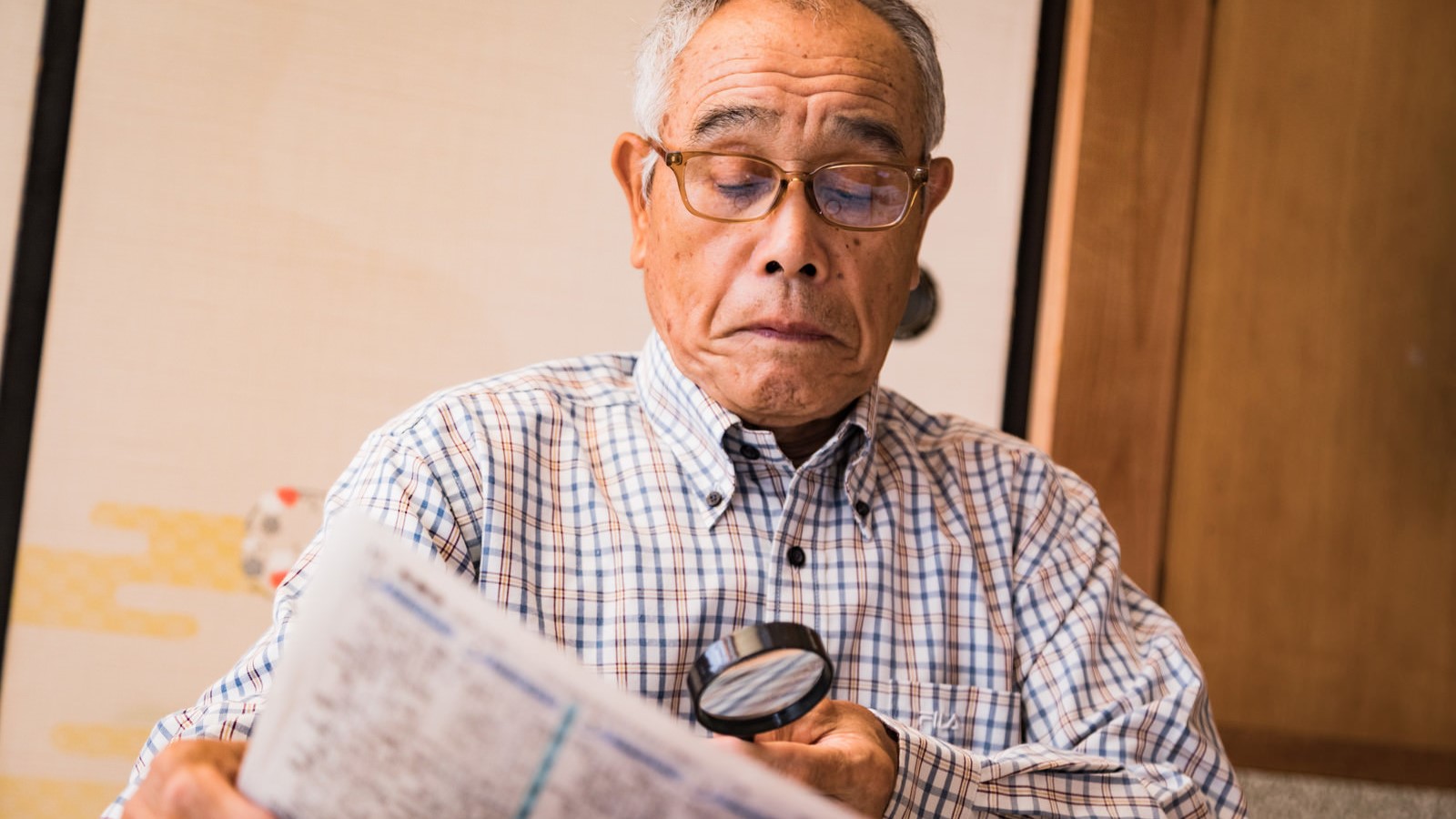
配偶者居住権
(1) 残された配偶者は、被相続人の遺言や相続人間の遺産分割協議等によって「配偶者居住権」を取得し、配偶者の居住権を保護するため、居住建物の所有者は、配偶者とともに「配偶者居住権設定」の登記を行ないます。
(2) 配偶者居住権は一身専属的権利であり、これを第三者に売却、贈与等、譲渡することは認められません。
当該配偶者が死亡した場合は、この権利の相続が発生せず、消滅します。
(3) 居住建物所有者の承諾を得て配偶者居住権に基づく特約で、第三者に居住建物の使用または収益をさせることは認められています。
この特約も登記で行います。
※民法第1028条から第1036条をご参照ください。
配偶者短期居住権
なお、配偶者の短期居住権であり、登記制度はありません。
(1) 配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合は、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし最低6ヶ月間は保障)。
(2) 上記(1)以外の場合には、居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得します。
※民法第1037条から第1041条をご参照ください。
相続登記と住所・氏名変更登記の義務化

・適切な管理がされず放置されている
・所有者の探索に時間と費用が必要
これらの問題を解決するために、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の申請義務化
その改正の背景は、所有者不明土地等の発生予防です。
① 相続(遺言を含む)により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
② 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
③ 2024年(令和6年)4月1日より前に相続が開始している場合でも、3年間の猶予期間がありますが、義務化の対象となることに注意しなければなりません。
④ 正当な理由なく申請をしなかった場合は、10万円以下の科料(行政罰)が課せられることがあります。
(正当な理由の例)
(1) 相続登記を放置したために、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集やほかの相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2) 遺言の有効性や遺産の範囲が長期にわたって争われているケース
(3) 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があり、やむを得ないケース
相続人申告登記制度の設立
施行日は同じく2024年(令和6年)の4月1日です。
① 登記簿上の所有者について、相続が開始したことと自分が相続人であることを法務局に対し申し出ることによって、登記官が職権で申出をした相続人の氏名、住所等を登記します。もっとも、権利を取得を公示するものではないため、相続登記の効果を生じません。
② この制度の利用により、相続人が単独で、費用もかけずに相続登記の義務を履行したことになります。
住所変更登記・氏名変更登記の義務化
そのため、2021年(令和3年)の不動産登記法の改正により、住所や氏名の変更が義務化され、その変更の日から2年以内に変更登記しなければなりません。
また、2026年(令和8年)4月1日より前に変更があった場合でも、2026年(令和8年)4月1日から2年以内に変更登記をしなければなりません。
ただし、この義務付けは、2026年(令和8年)4月1日からとされています。
終わりに
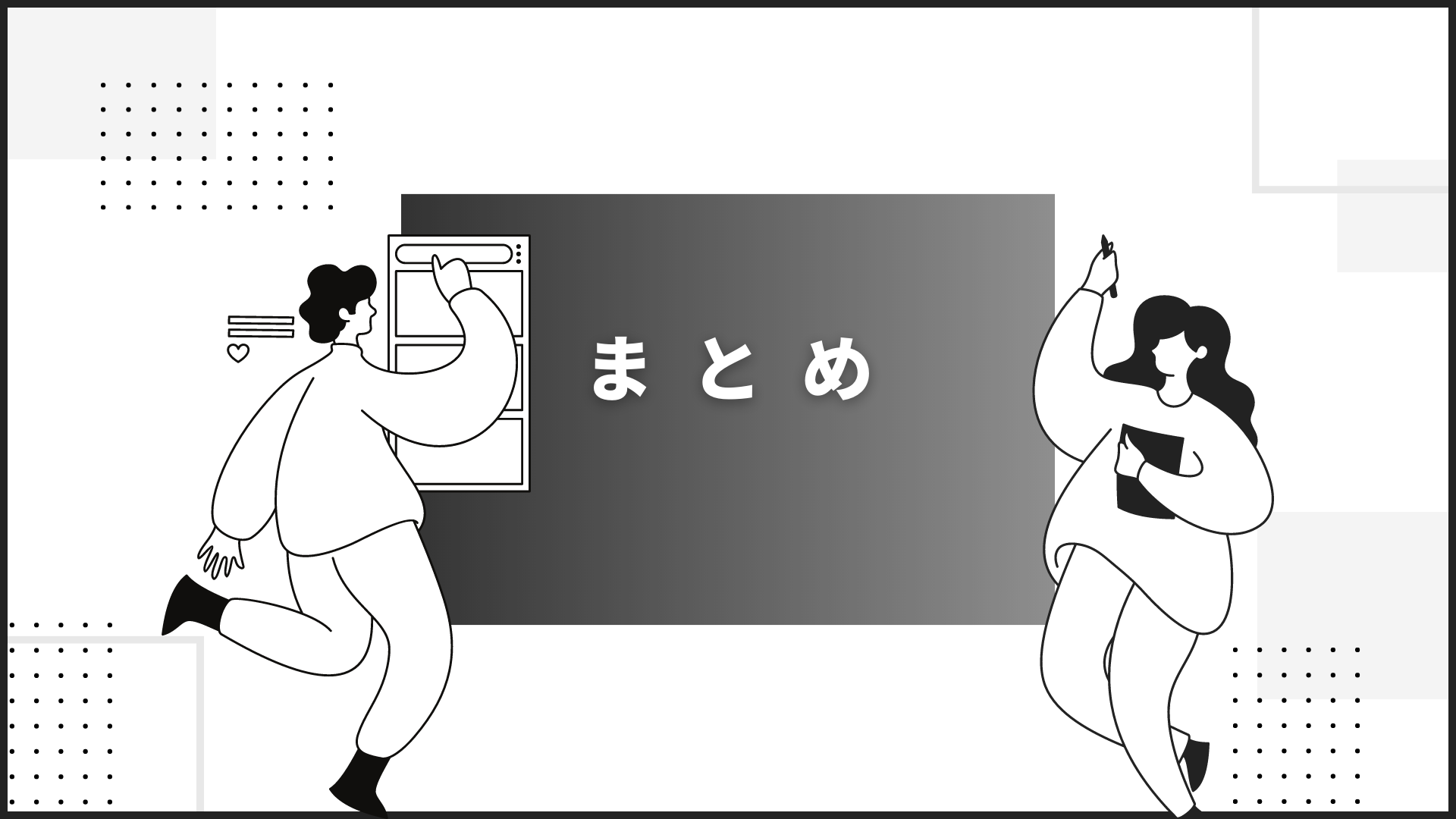
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。
なお、2024年(令和6年)4月1日より前の相続については、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を完了しなくてはなりません。
従来、相続の登記を申請するかどうかは相続人の任意とされてきましたが、所有者不明土地等の発生予防の観点から相続登記が義務化されることになりました。
今後登記については、任意ではなく事実を正しく行うことに重きがおかれることになるでしょう。
これを機に登記について理解することが望ましいでしょう。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
