
前回、売買契約の約定に関する基本的事項についてお話ししました。
今回も売買契約をめぐる紛争になる可能性がある事項について触れていきます。
さらには、実際に損害賠償を請求したり、契約解除を行ったりするときの詳細について、みていきましょう。
今回は、売買契約の約定に関する紛争について、お話し致します。
目的物件の不存在

しかし、改正後の民法は、目的物件が不存在であるときには契約は無効であるとする考え方を採用していません。
目的物件が存在しなくても契約は有効であることを前提として、「債務の履行が契約その他の債務の発生原因、および取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない」としつつ、「契約に基づく債務の履行がその契約の成立のときに不能であったことは、民法第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない」として、損害賠償によって契約当事者の利益を調整するものとされています。
例えば、建物の売買契約を締結したときに、既に建物が火災で焼失していて存在しなかった場合でも、売買契約は効力を有します。
買主が売買契約を締結したことによって損害を被ったのであれば、売主に対する損害賠償請求によってその不利益を補填することになります。
契約の存在については、解除によって処理されます。
債権者(売買契約においては買主)は、債務の全部の履行が不能であるときには催告をすることなくして契約を解除することが可能であり、解除がなされれば、契約が存在しないことになります。
解除をするためには、債務者(売買契約においては売主)の帰責事由は必要とされていないため、建物の火災による焼失についてみれば、火災について売主に過失があるかどうかを問わず、買主は売買契約を解除することができます。
また、最後の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者から契約を解除することは認められず、建物の火災による消失について買主に過失があれば、買主は契約を解除することはできません。
債務不履行

債務の本旨とは、債務として予定されている本来の趣旨のことであり、また履行とは、債務者が債務の内容を実現することをいいます。
債務不履行の意義・種類
なお、債務者は債務を負担して履行しなければならない立場にいる以上、債務者が債務不履行の責任を免れるためには、その不履行が自己の責めに帰すべき事由に基づくものではないことを立証(証明)しなければならない、と解されています。
債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類の態様があります。
不完全履行の問題の多くは担保責任の問題となります。
① 履行遅滞
履行遅滞とは、履行が可能であるにもかかわらず、履行期が過ぎても履行しないことをいいます。
例えば、建物の売主が約定の引き渡し期日に引渡しをしない、ということが該当します。
② 履行不能
履行不能とは、履行することができないことをいいます。
例えば、建物の売買契約の締結後、引渡し前に売主の失火(過失)により、売買の目的物件を焼失させてしまい、引渡しができなくなった、ということが該当します。
債務者の責めにより履行不能となると、債権者は損害賠償の請求と契約の解除ができます。
③ 不完全履行
不完全履行とは、債務の履行として、とにかく一応の履行はなされたが、それが債務の本旨に従ったものではない不完全な場合のことをいいます。
例えば、ある物件の調査を依頼された者がずさんな報告をしたため、依頼者が損害を被った、ということが該当します。
不完全履行の場合、もし追加(債務者が改めて完全な履行すること)が可能であるときは、追完の請求ができます。
さらに、債務者の責めによる不完全履行の場合には、その遅延による損害賠償の請求をすることができます。
追完がそもそも不能であるときは、履行に代わる損害賠償請求ができます。
損害賠償に関する原則
損害賠償は、金銭によって支払われることが原則です。
損害が発生したこと、および損害の額については、請求者の側が立証しなければなりません。
その請求できる範囲は、債務不履行と条件関係のあるすべての損害ではなく、その債務不履行によって生ずべき損害、いわば債務不履行と相当因果関係にある損害に限られます。
相当因果関係にある損害とは、原因・結果の関係、すなわち因果関係のうち、常識的にみて、そのようなことがあれば、そのような結果になるだろうと考えられる範囲の損害です。
なお、特別の事情によって生じた損害は、当事者がその事情を予見し、または予見することができた場合のみ賠償の範囲に含まれる、と解されています。
損害賠償の予定
この予定をした場合には、請求者は相手方の債務不履行の事実を立証すれば、それだけで約定の賠償額を請求でき、損害を受けた額を立証する必要がありません。
それにより、損害の額をめぐる当事者間の紛争を未然に防止することができることになり、また、当事者の債務の履行を促進させる効用があるため、不動産の取引実務で広く行なわれています。
この予定がなされているときは。請求者が実際の損害額について予定額より大きいことを立証しても、予定額を超えて請求することができない反面、実際の損害額が予定額より小さくても、請求者は予定額を請求できます。
損害賠償額の予定は、履行の請求や解除権の行使とは別の問題であり、賠償額の予定をしても、履行の請求または契約の解除は自由にできます。
なお、損害賠償額の予定に類似の概念として違約金があります。
違約金は、契約締結の際、当事者間で債務不履行のときに、債務者が債権者に一定額の金銭を支払うことをあらかじめ約束する場合の、金銭のことをいいます。
この性質は当事者の意思によって決定されるものであり、例えば、損害賠償額の最低額の予定であったり、債務不履行があればとりあえず違約金お支払い、実際の損害は別途証明することにより請求できるという趣旨のものであったり、さまざまなものがありえますが、民法は、これを損害賠償額の予定と推定することとしています。
金銭債務の特則と過失相殺
(1) 金銭債務は履行不能になることはあり得ず、その不履行というのは、常に履行遅滞である。
たとえ金銭を用意できず支払うことができない、といっても、それは結局弁済期に弁済できないという履行遅滞になるだけである。
(2) 金銭債務の遅滞においては、その原因が不可抗力によるものであることを証明しても賠償義務を免れることができず、また請求者は損害があったことの証明をすることも要しない。
(3) 賠償額は原則として法定利率によって定められます。
法定利率については、2020年(令和2年)4月1日施行の民法改正によって変動制が採用されています。
改正民法施工時は年3%であり、その後3年ごとに見直されます。
また、賠償額についての約定利率が法定利率と異なるときは、その約定利率によります。
債務の不履行に関して、債権者の側にも過失があるときは、損害賠償の責任、およびその金額を定めるにあたって斟酌します。
そのような場合でも、債務者のみに全損害を負担させるというのでは、不公平だからとされています。
売主の担保責任

買主には、①修補・追完、②代金減額、③損害賠償、④契約解除の4つの救済方法が認められています。
契約不適合責任
引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができます。
契約の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追加の請求をすることができません。
② 代金減額
引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものである場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適法の程度に応じて代金の減額を請求することができます。
次に掲げる場合には、買主は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができます。
一 履行の追完が不能であるとき
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
三 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、寄主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
目的物の契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、代金の減額の請求をすることができません。
③ 損害賠償
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができます。
売買契約でも、引渡しのなされた目的物について契約の内容に適合しない場合には、損害賠償を請求することができます。
しかし、売買契約および社会通念に照らして債務者(売主)に責めに帰すべき事由がないときは損害賠償はできません。
④ 契約解除
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をしたうえで、また、債務の全部の履行が不能であるときには催告をすることなく、それぞれ契約の解除をすることができるとされています。
売買契約でも、売主が債務の本旨に従った履行しないなどの状況があれば、買主は契約を解除することができます。
ただし、その債務の不履行が売買契約および社会通念に照らして軽微であるときは、解除することができません。
また、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約の解除をすることができないため、契約不適合について買主に責任があるときには、買主から契約を解除することは認められません。
期間制限
ここでは、通知期間に通知をすれば権利が保存されるので、通知期間内に請求することまでは求められません。
通知期間の起算点は、買主が契約不適合を知ったときです。
ただし、売主が引渡しのときにその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、買主が通知期間に通知をしなかったとしても、買主の請求につき期間制限を受けません。
もっとも、買主が通知期間内に通知をすれば契約不適合責任を追及する権利が保存されますが、債権の消滅時効に関する一般原則が通用されなくなるものではありません。
通知期間に通知をしても、権利を行使できることを知ったときから5年、権利を行使できるときから10年という消滅時効の規定は適用されます(参考:最高裁平成13年11月27日判決)。
また、時間制限が適用されるのは、物の種類と品質に関する契約不適合です。
権利の契約不適合と数量(分量)の契約不適合については。時間制限は適用されません。
担保責任を負わない旨の特約
ただし、その場合でも、売主は次のものについては免責されません。
① 売主が知っていながら買主に告げなかった事実
② 売主が自ら第三者のために設定し、または譲渡した権利
特別法による特約

宅建業者が売主の売買における特約
買主に不利となる特約は無効となります。
ところで、従前、宅建業者による自ら売主の場合の担保責任は、瑕疵担保責任の特約に対する制限でしたが、2020年(令和2年)4月1日施行の民法改正によって瑕疵担保責任が廃止され、契約不適合責任の仕組みが取り入れられました。
そのため、宅建業法第40条第1項も、民法の規定に合わせて瑕疵担保責任の制限から契約不適合責任の制限に改められました。
ここで、瑕疵担保責任がその責任が限定された範囲に留まっていたのに対し、契約不適合責任は、一般の契約のルールが適用されることになりますので、宅建業法によって効力が否定される特約の範囲が従前と比較して拡大されました。
例えば、「隠れた瑕疵について売主は責任を負う」という特約(買主の善意無過失を要求するものであって買主に不利)、目的物に契約不適合責任があったときの救済手段について、先後をつける特約(民法で認められた救済手段の選択を認めないものとして買主に不利)、「売主は引渡し後2年間に限り担保責任を負う」という特約(改正により契約不適合責任の追及のためには2年以内に契約不適合がある旨を通知すればよいこととなっており、2年以内に請求までを要求することは買主に不利)、売主の担保責任を問うための通知について、「通知方法を書面通知に限る」とする特約(書面でなければおよそ通知として受け付けないものとする特約は買主に不利)などは、宅建業法第40条第1項によって禁止され、同条第2項によって無効になります。
住宅品質確保法
この規定は強行規定であり、これに反して責任期間を短縮し、あるいは責任を免除する特約には効力が認められません。
ただし、特約によって、この期間を20年間まで延長することはできます。
なお、売主の担保責任に関し、民法では「瑕疵」という言葉は廃止されましたが、住宅品質確保法では「この法律において瑕疵とは、種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう」との定義規定を設けたうえで、引き続き、目的物の欠陥を示す法律上の用語として用いられています。
商人間の不動産売買
売買の目的物が種類、または品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6か月以内にその不適合を発見したときも、同じく損害賠償等の請求をすることはできません(商法第526条第1項~第3項)。
不動産の売買についても、商法が適用になる場合には、特約がない限り、買主には商法による検査通知義務があると理解されています(東京地裁平成4年10月28日判決)。
商法による検査通知の義務の定めは、強行規定でなく、法の定めと異なる特約も有効です。
消費者契約法
契約の解除
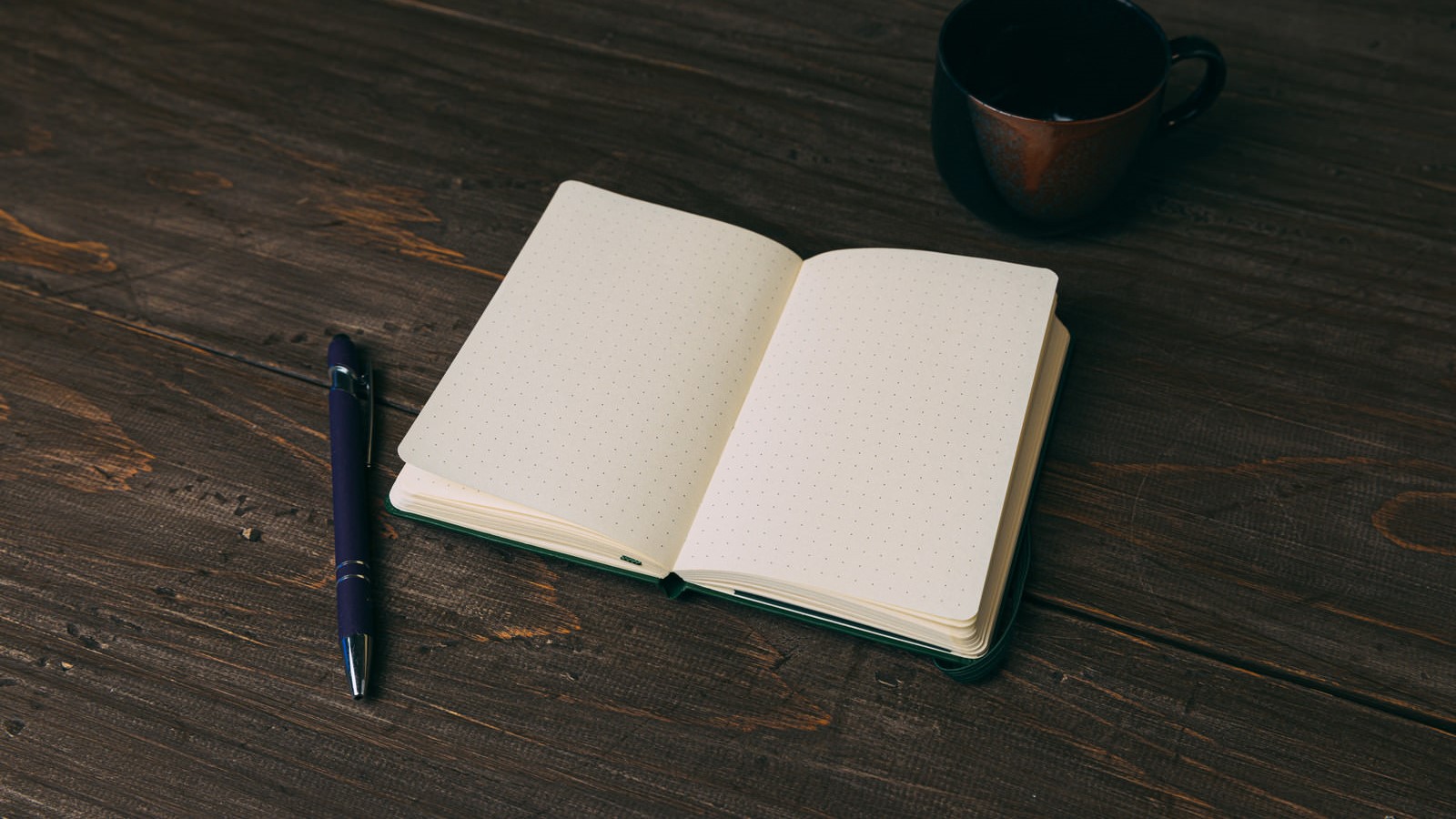
解除と類似の制度
賃貸借や委任などのような継続的な契約関係を一方的に解消する場合、これを特に解除と区別して解約や告知といいます。
この場合、その効果は将来に向かって契約を消滅(終了)させるだけで、解除のように訴求しない点に特色があります。
② 合意解除(解除契約)
解除権の有無を問わず、当事者が現に存在する契約を解消して、契約がなかったことにしようとする合意を新たにすることを合意解除(解除契約)といい、契約自由の原則により自由にできます。
これはあくまでも当事者の契約(合意)に基づくもので、解除のように解除権者が一方的な意思表示で行うものと異なります。
③ 解除条件
一定の事実の発生によって、法律行為の効力が当然に消滅するという条件を、解除条件といいます。
条件の一種であって、契約の解除とは明らかに異なる概念です。
④ 取消し
制限行為能力や錯誤、詐欺・脅迫による意思表示などの場合に、その意思表示を当初にさかのぼって無効にしようという意思表示のことを取消しといいます。
取消しについては、一方的意思表示で契約の相手方が行った意思表示の効果を消滅させる点は「解除」と同じですが、解除においては意思表示に問題があったのではなく、契約上の義務を履行しないなどの理由によって意思表示の効果を失わせるのに対して、取消しの場合は、意思表示それ自体に問題があったために意思表示の効果を消滅させる仕組みであるという点で「解除」と異なっています。
解除権の発生
① 約定解除権
解約手付による解除のように、当事者の合意によって生じるものをいいます。
② 法定解除権
債務者が債務を履行しない場合であって、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、解除することができます。
この場合の解除の権利が、法定解除権です。
その期間を経過したときにおける債務の不履行が、その契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除権は生じません。
期間を定めないで催告した場合や期間が相当でなかった催告についても、その催告から相当期間を経過すれば解除の効果が生じます。
解除の前に催告を必要とするのは、催告によって債務者の翻意を促し、債務を履行する機会を与えられながら債務の履行をしない場合にはじめて解除が可能になるものと考えられるためです。
そのために、催告によって債務者に翻意の機会を与える必要がない場合には、催告をせずに契約を解除することができます。
催告をしないで契約を解除することができるのは、次の場合です。
ア 債務の全部の履行が不能であるとき
イ 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
ウ 債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
エ 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき
オ 上記アーエのほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
解除権行使の行使
いったん解除した以上、これを撤回することはできません。
解除権の行使には、条件を付することができないと解されています。
これを認めると、法律関係を不安定なものにしてしまうためです。
しかし、催告をする際に、例えば「7日以内に履行がなされなければ、改めて解除の意思表示をしなくても契約は解除されたものとする」という意思表示は、法律関係を不安定にするものではないので許されます。
1つの契約に当事者が数人存在するときは、その全員から、また全員に対して解除の意思表示を行わなければなりません(民法第544条第1項)。
解除権行使の効果
その結果、当事者は互いに原状回復義務を負います。
既に引き渡された目的物件は返還され、給付された金銭も返還されますが、解除の結果、金銭を返還するときは、受領のときからの利息を付けなければなりません。
また、金銭以外のものを返還するときは、その受領のとき以後に生じた果実をも返還しなければなりません。
解除の遡及効は、第三者には及びません。
例えば、Aから土地を買ったBがCに転売したのち、AB間の契約が解除されたとしても、AはCに対してその土地の返還請求をすることはできません。
判例では、この場合、第三者のCは善意でも悪意でもよいが、この保護を受けるためには、登記を受けていることが必要です。
解除がなされても、債務不履行によって発生した損害について、賠償請求をすることができます。
解除における保証人の責任
契約締結上の過失
このような、契約締結に至るまでの間に落ち度のある場合を「契約締結上の過失」といいます。
例えば、ほぼ確実に契約が締結できる段階でありながら、何ら相手に落ち度がないのに、一方的に破棄した場合や、契約締結前段階において。契約締結するか否かを判断するために必要かつ重要な事実を説明せず、契約を締結させたような場合に、契約締結上の過失が認められ、損害賠償責任を認めることがあるといわれています。
判例の傾向
契約準備段階において、交渉に入った者同士の間では、誠実に交渉を続行し、一定の場合には重要な情報を相手方に提供すべき信義則上の義務を負います。
この義務に違反した場合は、それにより相手方が被った損害を賠償しなければなりません。
損害賠償請求権の性格
これに対し、最高裁平成23年4月22日判決は、「契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである」と論じ、契約責任ではなく、不法行為責任であるという考え方を採用しています。
終わりに
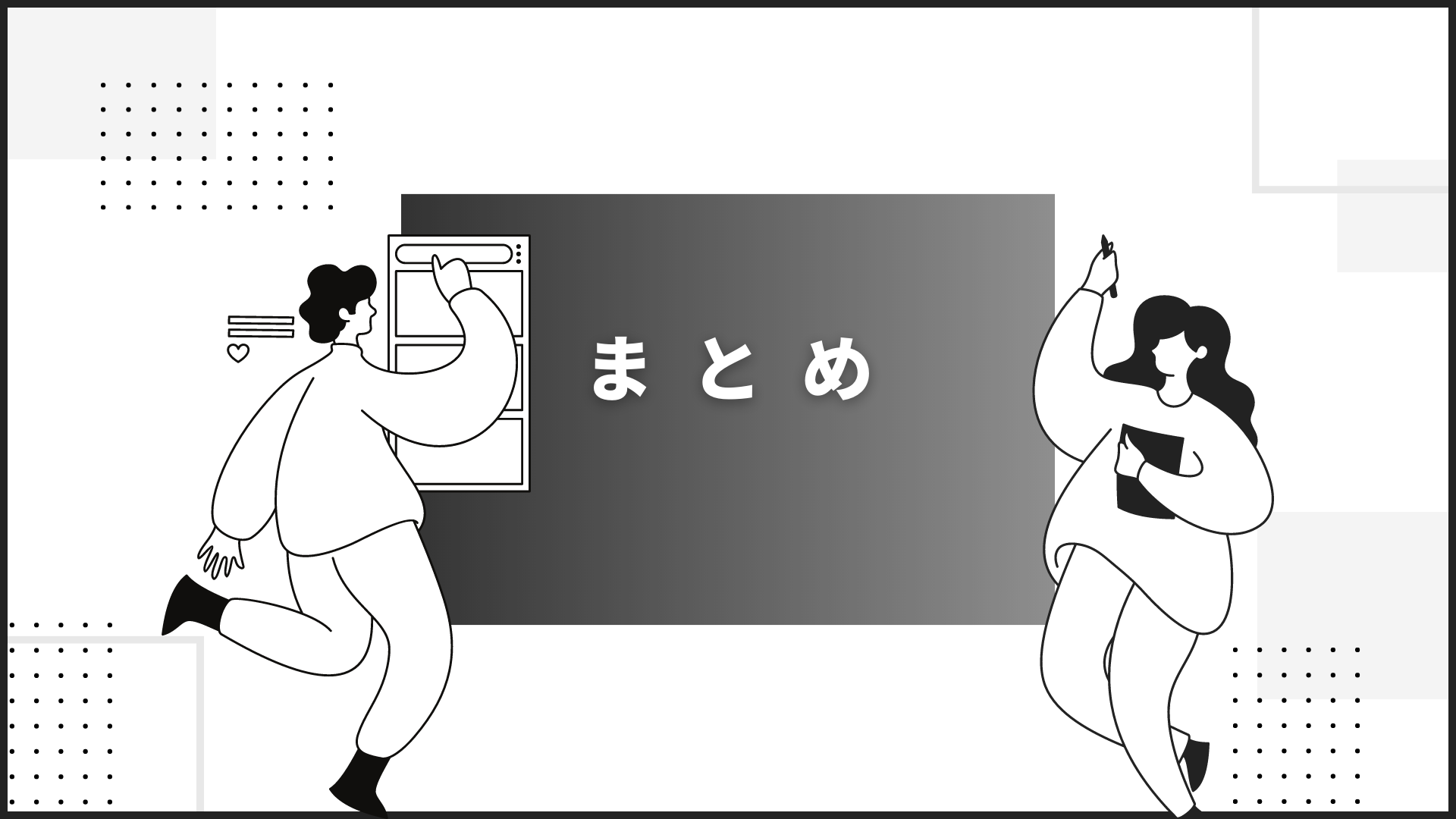
ここでは、契約の不履行の種類、損害賠償の請求、売主の担保責任、特別法に基づく特約、契約の解除や解約・取消しの違い、契約締結上の過失について取り上げました。
いずれも売買契約の約定に関する紛争について、重要な事柄です。
また、それぞれの言葉の違いについても、理解しておくことが望ましいです。
不動産取引のトラブルには、今回取り上げたものが関わってきます。
売買契約の約定を理解できるようにならなければ、判断することができないことはいうまでもありません。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
