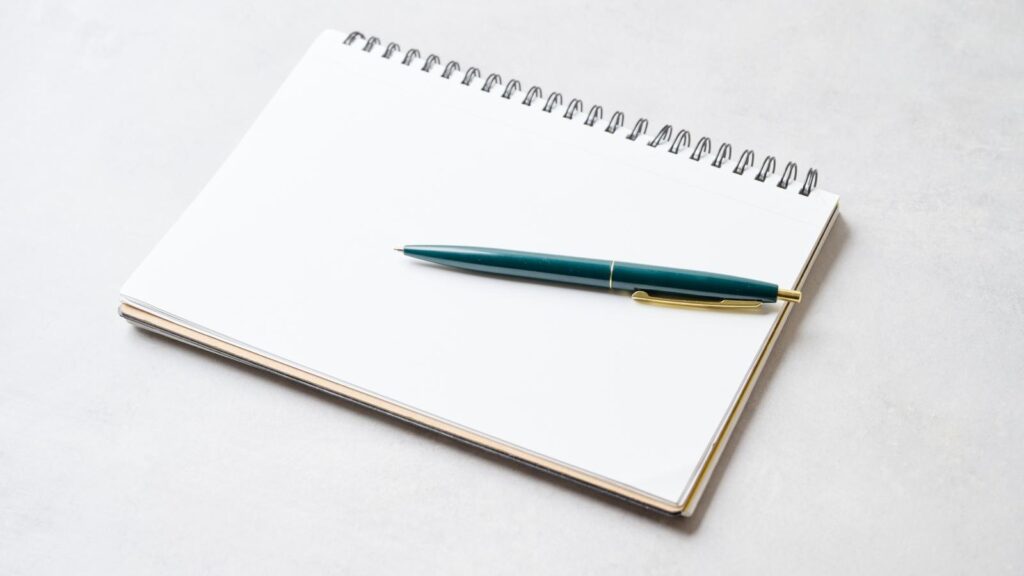
前回は、宅地建物取引士の事務の1つ「重要事項の説明」について、ブログで解説しました。
不動産取引は権利関係が複雑で、法令上の制限も多いほか、契約の取引条件も複雑かつ取引価額も高額です。
そのため、業務の運営の適正性や宅地建物取引の公正性を確保するため、宅地建物取引に関して専門的かつ広範な知識を有する宅地建物取引士の設置を義務付けられています。
特に重要事項の説明は、宅地建物取引についての経験や知識の乏しい消費者が、契約対象物件や取引条件について十分理解しないままに契約を締結し、後に契約目的を達成できず不測の損害を被るといった状況を防ぐため、契約締結の判断に重大な影響を与える事項について説明することを義務付けたものです。
では、契約締結の判断に重大な影響を与える事項にはどのようなものがあるでしょうか。
今回は、重要事項説明の各事項について、お話し致します。
登記された権利の種類・内容・名義人等

「当該宅地または建物の上に存する登記された権利の種類及び内容ならびに登記名義人または登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)」
趣旨
(1) 取引の対象となっている宅地建物の登記簿上の所有者はだれか
(2) 所有権以外の権利で登記されているものはあるか
(3) 所有権以外の権利で登記されているものがあれば、どのような種類の権利か、またその権利を有するのはだれか
これによって、購入者または借主(以下、「購入者等」という)は、売主または貸主を確認することができます。
これらの者が登記簿上の所有権者でない場合には、いかなる権限に基づいて売主または貸主となるのかについて確認できます。
登記された権利
仮登記された権利
仮登記自体は対抗力をもたないが、後に本登記がなされれば、本登記の順位は仮登記の順位より定まります。
そのため、説明の義務があります。
買戻権
買戻権は、売買契約と同時に、売主が買主に対して10年以内において契約を解除して不動産を買い戻すことを特約するものです。
登記することによって第三者への対抗力が生じます。
登記名義人または登記簿の表題部に記録された所有権の氏名
表示の登記は所有者に対して義務付けられており、また職権でも可能なので、全ての不動産についてこれがなされることとされています。
したがって、表示の登記しかない場合には、その表題部に所有者として記録されている者について記載させることとされています。
なお、表題部に記録された所有者の表示は、所有権の保存登記をすれば抹消することができます。
所有権の保存登記は、表題部に記録された者または相続人により、あるいは判決による所有権の帰属を確認された者などしか申請することができません(参照:不動産登記法第74条)。
登記の意味
登記名義人であるからといって、それを信用して取引をしても、真の所有者は別にいて購入者などが損害を被ることがあります。
したがって、取引の代理や媒介をする宅建業者としては、登記を調べることのみでは、必ずしも十分に調査義務を果たしたとはいえない場合があります。
法令に基づく制限の概要
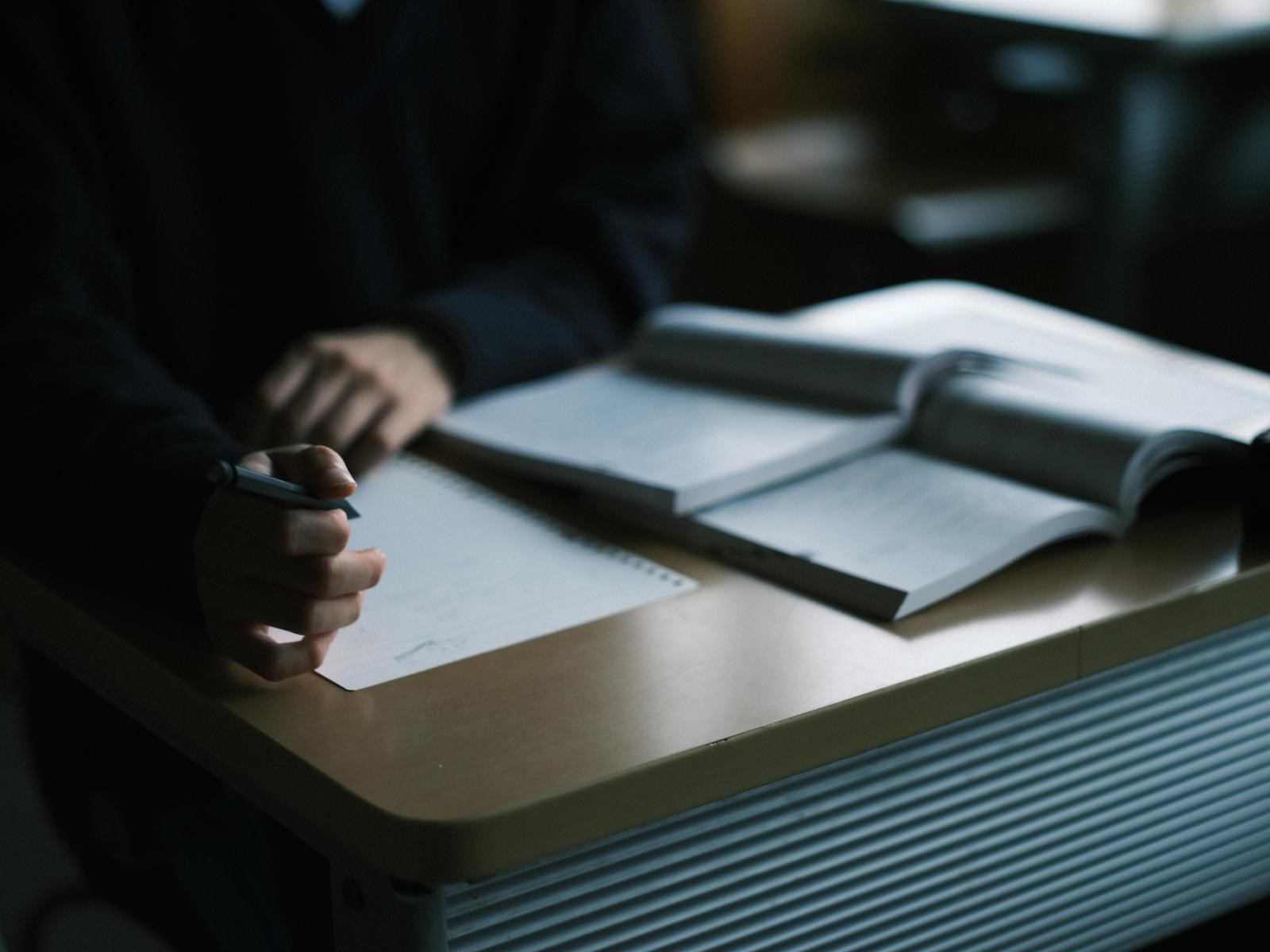
「都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要」
趣旨
購入者等が、これらの法令上の制限を知らないまま取引をすると、契約成立後、その制限のために取得の目的を達成できない等、思わぬ被害を被ることになります。
また、このような場合には、購入者等が担保責任などとして損害賠償を請求するなどして、当事者間で深刻な紛争が生じます。
このため、宅建業者に、取引の対象となっている宅地建物にかかる法令上の制限を、契約が成立するまでの間に説明することを義務付けて、購入者等の保護と当事者間の紛争の防止を図っています。
政令で定める法令に基づく制限
施行令第3条の概要
土地建物の所有者に適用される都市計画法、建築基準法等の法令に基づく建築制限、所有権等の譲渡制限等を規定します。
すなわち、施行令第3条第1項に規定されている法律の制限のすべてを説明事項とします。
2 宅地の貸借の契約の場合の法令制限
上記1の制限のうち、都市計画法等の法令に基づく土地の譲渡制限等、土地の所有者に限って適用される制限を除くものを説明事項とします。
すなわち、次に掲げる法律を除いたものを説明事項とします。
ア 土地の所有者に対する一定の建築義務および利用制限
・新住宅市街地開発法第31条
・新都市基盤整備法第50条
・流通業務市街地の整備に関する法律第37条第1項
イ 土地の所有者に対する所有権の譲渡制限
・都市計画法第52条の3第2項、第4項、第57条第2項、第4項、第67条第1項、第3項
・公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項、第8条
・文化財保護法第46条第1項、第5項
3 建物の貸借の契約の場合の法令に基づく制限
上記1の制限のうち、建物の賃借人にも適用される制限(建物の賃借権の設定・移転に関する制限)を説明事項とします。
すなわち、次に掲げる法律のみを説明事項とします。
・新住宅市街地開発法第32条第1項
・新都市基盤整備法第51条第1項
・流通業務市街地の整備に関する法律第38条第1項
業法の解釈・運用の考え方
宅建業者が、土地区画整理事業の施行地区内の仮換地の売買等の取引に関与する場合は、重要事項の説明時に、その売買、交換および貸借の当事者に対して「換地処分の公告後、当該事業の施行者から換地処分の公告の日の翌日における土地所有者および借地人に対して清算金の徴収または交付が行われることがある」ことを重要事項説明書に記載のうえ、説明することとされています。
借地権付き建物および借地権の損する宅地の売買等について
宅建業者が、借地権付き建物の売買等を行う場合においては、建物と敷地の権利関係の重要性にかんがみ、当該借地権の内容について説明することとされています。
売買等の対象である借地権付建物が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときには、宅地建物取引業法第35条第1項第6号に基づき、必ず当該借地権の内容を説明することとされています。
宅建業者が、借地権の存する宅地の売買等を行う場合において、当該借地権が登記されたものである場合は、宅地建物取引業法第35条第1項第1号に基づき、必ず借地権の内容につき説明することとされています。
当該借地権の登記がない場合においても、土地の上に借地権者が登記された建物を所有するときは第三者に抵抗できることにかんがみ、宅建業者は当該宅地上に建物が存する場合には、建物と当該宅地の権利関係を確認し、借地権の存否および借地権の内容につき説明することとされています。
また、借地権の縦登記がなく、宅地上に建物が存しない場合においても、借地権者が、借地借家法第10条第2項に基づき、土地の上に一定の掲示をしたときは、第三者に対抗できることにかんがみ、宅建業者は、当該宅地上に借地権の存在を知り得た場合においては、借地権の内容につき説明することとされています。
借地権付建物の賃貸借の代理または媒介について
宅建業者が、借地権付建物の賃貸借の代理または媒介を行う場合においては、当該借地契約の建物賃借人にとっての重要性にかんがみ、当該建物が借地権付建物である旨、および借地権の内容につき説明することとされています。
私道負担に関する事項

「当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項」
趣旨
また、私道の変更や廃止は制限されており、建ぺい率も私道予定部分の面積を除いて計算されます。
このため、購入者は、私道負担を知らないで取引をした場合に、思いがけない損害を被ることがあります。
したがって、宅建業者に、取引の際に前もって「私道に関する負担に関する事項」を説明することを義務付けています。
なお、私道負担については、直接には敷地の所有者、賃借人(借地人)に対する制限であって、建物の賃借人は直接制限を受ける立場にありません。
そのため、「建物の貸借の契約」では説明事項から除かれています。
説明すべき事項
① 私道負担の有無
② 私道の面積
③ 私道の位置
私道には、建築基準法上の道路である私道のほかに、通行地役権の目的となっている私道を含みます。
私道について、所有権や共有持分を有していないが、それを利用するために負担金を支払うことになっている場合、ここで言う私道に関する負担にあたります。
また、現在存在する負担のみならず、将来生じることになっている負担も含まれます。
供給施設・排水施設の整備の状況

「飲用水、電気およびガスの供給ならびに排水のための施設の整備の状況」
(これらの施設が整備されていない場合)
「整備の見通しおよびその整備についての特別の負担に関する事項」
趣旨
このため、これらの施設の整備の状況ならびにこれらの施設が整備されていない場合にあっては、その整備の見通しや整備のための特別の負担に関する事項を重要事項として説明すべきこととされています。
説明すべき事項
① 施設の内容はどのようなものか
② これらの施設は通常の状態で通常の用法により継続的に使用できるのかどうか
③ これらの施設は直ちに使用できる状態にあるのかどうか など
施設が整備されていない場合
① 誰が施設の整備を行う予定であるか
② 施設の整備のために購入者等はどの程度の負担をしなければならないか
③ 施設が整備されるのはいつか など
ガス配管設備等に関しては、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとする場合には、その旨の説明をすることとされています。
完了時における宅地建物の形状・構造等

「宅地建物が宅地の造成または建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項」
宅地の場合は、宅地に接する道路の構造および幅員
建物の場合には、主要構造部、内装および外装の構造または仕上げ、設備の設置および構造
趣旨
そこで、購入者が完成後のイメージを十分に形成できる程度に、図表および関連資料等を用いて、完成後の状態にかかる事項を重要事項として説明するすべきこととし、紛争の防止を図ることとされています。
宅地建物の形状や構造、宅地に接する道路の位置や幅員などについては、文章で説明することが難しく、また文章では相手方においても分かりにくく、かつ誤解が生じることが多いでしょう。
そこで本号では、図面で説明することが可能であるとされており、また、その場合には、説明に用いた図面を相手方に交付しなければなりません。
なお、図面を交付したときは、その図面に記載されている事項は改めて重要事項説明書に記載することを要しないこととされています(業法の解釈・運用の考え方)。
業法の解釈・運用の考え方(宅地の場合)
当該宅地の地積、外周の各辺の長さを記入した平面図を交付し、また、当該宅地の道路からの高さ、擁壁、階段、排水施設、井戸などの位置、構造等について説明することとし、特にこれらの施設の位置については、上記の平面図に記入することとされています。
なお、上記の平面図は、これらの状況が充分に理解できる程度の縮尺のものにすることとされています。
(2) 宅地に接する道路の構造および幅員について
道路については、その位置および幅員を上記(1)の平面図に記入し、また側溝等の排水施設の状況等について説明することとされています。
業法の解釈・運用の考え方(建物の場合)
当該建物の敷地内における位置、各階の床面積および間取りを示す平面図(マンション棟建物の一部にあっては、敷地および当該敷地内における建物の位置を示す平面図、ならびに当該物件の存する階の平面図、ならびに当該物件の平面図)を交付し、また当該建物の鉄筋コンクリート造、ブロック造、木造等の別、屋根の種類、階数などを説明することとされています。
なお、上記の平面図は、これらの状況が十分に理解できる程度の縮尺のものにすることとされています。
建物の主要構造部、内装および外装の構造または仕上げについて
主要構造部(建築基準法上の主要構造部をいう)については、それぞれの材質を、内装および外装については、主として、天井および壁面につきその材質、塗装の状況等を説明することとされています。
建物の設備の設置および構造について
建築基準法上の建築設備のほか、厨房設備、照明設備、備え付けの家具など当該建物に付属する設備(屋内の設備に限らず門、へいなど屋外の設備も含む)のうち主要なものについて、その設置の有無および概況(配置、個数、材質等)を説明することとし、特に配置については、図面で示すことが必要かつ可能である場合は、上記「建物の形状、構造について」の平面図に記入することとされています。
業法の解釈・運用の考え方(工事完了時売買の場合)
また、いずれの場合においても、図面その他の書面への記載にあたっては、建物の構造、設備、仕上げなどについて購入者が理解しやすいように、具体的に記載することとされています。
区分所有建物の場合

「当該建物が区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類および内容、共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物またはその敷地に関する権利およびこれらの管理または使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの」
趣旨
また、一棟の建物に多数の人々が居住するため、その居住者間の権利関係の調整も極めて難しい面をもっています。
さらに、区分所有法は、所有関係、管理関係の規制内容の大部分を区分所有者間の規約に委ねているが、マンション等の管理規約は、素人には一見分かりにくいものとなっています。
そこで、マンション等については、敷地の権利の種類や管理の内容等が説明すべき重要事項とされています。
なお、区分所有建物の貸借の契約の場合、取引の実情等を踏まえて簡素化を図るため、国土交通省令第16条の2第3号、第8号のみを説明事項としています。
第16条の2に関する各号の説明
敷地に関しては、総面積として、実測面積、登記簿上の面積、建築確認の対象とされた面積を記載することとされています。
なお、やむを得ない理由により、これらのうちいずれかが判明しない場合にあっては、その旨を記載すれば足りるものとされています。
また、中古物件の代理、媒介の場合にあっては、実測面積、建築確認の対象とされた面積が特に判明している場合のほかは、登記簿上の面積を記載することをもって足りるものとされています。
権利の種類に関しては、所有権、地上権、賃借権等に区別して記載することとされています。
権利の内容に関しては、所有権の場合は対象面積を記載することをもって足りるものとされています。
ただし、地上権、賃借権等の場合は、対象面積およびその存続期間を併せて記載することとされています。
なお、地代、賃借料等についても記載することを要するものとするが、これについては区分所有者の負担する額を記載することとされています。
共用部分に関する規約の定め
共用部分に関する規約の定めには、いわゆる規約共用部分に関する規約の定めのほか、いわゆる法定共用部分であっても、規約で確認的に共用部分とする旨の定めがあるときには、その旨を含みます。
なお、新規分譲等の場合には、買主に提示されるものが規約の「案」であることを考慮します。
共用部分に関する規約が長文にわたる場合には、その要点を記載すれば足りるものとされています。
専有部分の用途等の制限に関する規約の定め
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めには、例えば、居住用に限り事業用としての利用の禁止、フローリングへの張替え工事、ペットの飼育、ピアノの使用等の禁止または制限に関する規約上の定めが該当します。
なお、ここでいう規約には、新規分譲等の場合に買主に示されるものが契約の「案」であることを考慮して、その案も含むこととされています。
また、専有部分の利用制限について規約の細則等において定められた場合でも、その名称の如何にかかわらず、規約の一部と認められるものを含めて説明事項とされています。
また、当該規約の定めが長文にわたる場合においては、重要事項説明書にはその要点を記載すれば足りるものとされています。
その採用点の記載に代えて、規約等の写しを添付しても差し支えありませんが、当該箇所を明示する等により相手方に理解がなされるよう配慮しなければなりません。
専用使用権の内容
専用使用権の設定がなされているものに関するもの、例えば、専用庭、バルコニー等に設定されているものです。
これらについては、その項目を記載するとともに、専用使用料を徴収している場合は、その旨およびその帰属先を記載することとされています。
駐車場については、特に紛争が多発していることにかんがみ、その内容は使用し得る者の範囲、使用料の有無、使用料を徴収している場合はその帰属先等を記載することとされています。
管理費の負担を特定の者にのみ減免をする旨の定め
マンションの管理規約は、分譲マンションの区分所有者が組織する管理組合が定めるマンションの管理または使用に関する基本ルールです。
新築分譲マンションの場合は、分譲開始時点で管理組合が実質的に機能していないため、宅建業者が管理契約の「案」を策定し、これを管理組合が承認する方法で定められることがあります。
そのため、購入者にとって不利な金銭的負担が定められている規約も存在し、その旨が「中高層分譲共同住宅の管理等に関する行政監察報告書」(平成11年11月)においても指摘されています。
このような内容の契約を定めること自体望ましいものではない場合もありますが、契約自由の原則を踏まえつつ、購入者の利益の保護を図るため、管理規約中に標記に該当する内容の条項が存在する場合は、その内容の説明を宅建業者に義務付けています。
なお、この規定は、中古マンションの売買でもその適用を排除されず、その場合、当該売買の際に存在する管理規約について調査・説明を行うこととされています。
計画修繕積立金の定めおよび積立金
いわゆる大規模修繕積立金、計画修繕積立金の定めに関するものであり、一般の管理費でまかなわれる通常の維持修繕はその対象とはされていません。
また、当該区分所有建物に関し、修繕積立金等についての「滞納」があるときは、その額を告げることとされています。
ここでいう修繕積立金については、当該一等の建物にかかる修繕積立金積立総額、および売買の対象となる専有部分にかかる修繕積立金等を指しています。
なお、この積立額は時間の経過とともに変動します。
できる限り直近の数値(直前の決算期における額などを、時点を明示して記載することとされています。
通常の管理費
通常の管理費とは、共用部分にかかる共益費等に充当するため区分所有者が月々負担する経常的経費をいいます。
なお、国土交通省令第16条の2第6号の修繕積立金等に充当される経費は含まれません。
また、管理費用について「滞納」があれば、その額を告げることとされています
なお、この管理費用の額も人件費、物価等の変動に伴い変動するものと考えられます。
できる限り直近の数値を、時点を明示して記載することとされています。
管理の委託先
管理の委託を受けている者の氏名および住所を説明すべき事項とされています。
管理を受託している者が、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第44条の登録を受けている者である場合には。重要事項説明書に氏名と合わせてその者の登録番号を記載し、その旨を説明することとされています。
また、管理の委託先のほか、管理委託契約の主たる内容も併せて説明することが望ましいでしょう。
維持修繕の履歴
共用部分における大規模修繕、計画修繕を想定しています。
ただし、通常の維持修繕や専用部分の維持修繕を排除してはいません。
専用部分にかかる維持修繕の実施状況の記録が存在する場合は、売買等の対象となる専用部分にかかる記録についてのみ説明すれば足りるものとされています。
また、本説明義務は、維持修繕の実施状況の記録が保存されている場合に限って課され、管理組合、マンション管理業者または売主に当該記録の有無を照会のうえ、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。
規約等の内容の記載およびその説明
マンション等の規約その他の定めは、相当な量に達するのが通例であるため、重要事項としては「共用部分に関する規約の定め」、「専有部分に関する規約等の定め」、「専用使用権に関する規約等の定め」、「修繕積立金等に関する規約等の定め」および「金銭的な負担を特定のものにのみ減免する規約等の定め」に限って説明義務が課されています。
重要事項説明書にはその要点を記載すれば足りることとされていますが、この場合、契約等の記載に代えて契約等を別添しても差し支えありません。
なお、規約等を別添する場合には、国土交通省令第16条の2第2号から第6号までに該当する契約等の定めの該当箇所を明示する等により、相手方に理解がなされるよう配慮しなければなりません。
数棟の建物の共有に属する土地
一棟の建物が一団地に所在し、その団地内の土地またはこれに関する権利が当該一棟の建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合は、その共有に属する土地等についても区分所有者が共有部分を有するため、必要に応じ、共有の対象とされている土地の範囲、当該建物の区分所有者が有する共有持分の割合、およびその共有に属する土地の使徒等について、重要事項説明書に記載し、適宜その内容を説明するものとされています。
既存建物状況調査等

「当該建物が既存の建物であるときには、次に掲げる事項
イ 事項建物状況調査で定める期間(1年、ただし鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年を経過していないものに限る)を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合におけるその結果の概要
ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書類で国土交通省令が定めるものの保存の状況」
趣旨
また、建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存状況に関する重要事項説明は、既存住宅の購入判断等に大きな影響を与えると考えられる一定の書類の保存の有無等について、買主等が事前に把握したうえで取引に関する意思決定を行えるよう規定されたものです。
建物状況調査の有無と、ある場合の結果の概要に基づく説明
「宅地建物取引業法 法令改正・解釈について」内の「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」を参照ください。
当該建物状況調査を実施した者が既存住宅状況調査技術者であることを既存住宅状況調査技術者講習実施機関のホームページ等において確認する必要があります。
売主等に建物状況調査の実施の有無を照会し、必要に応じて管理組合および管理業者にも問い合わせたうえで、実施の有無が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。
実施後、1年(鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年)を経過していない建物状況調査が複数ある場合は、直近に実施された建物の状況調査を重要事項説明の対象とします。
ただし、直近に実施されたもの以外の建物状況調査により劣化事象等が確認されている場合には、消費者の利益等を考慮し、当該建物状況調査についても買主とに説明することが適当です。
なお、取引の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる建物状況調査を直近のもの以外に別途認識しているにも関わらず、当該建物状況調査について説明しない場合には、重要な事実の告知義務(宅建業法第47条第1号)違反になり得ます。
建物状況調査を実施してから1年(鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年)を経過する前に、大規模な自然災害が発生した場合など、重要事項の説明時の建物の現況が建物状況調査を実施した時と異なる可能性がある場合であっても、当該建物状況調査についても重要事項として説明することが適当です。
設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
また、書類の保存に代えて、当該書類にかかる電磁的記録が保存されている場合も含みます。
なお、国土交通省令第16条の2の3各号に掲げる書類の作成義務がない場合や当該書類が交付されていない場合には、その旨を説明します。
また、本説明義務については、売主等に当該書類の保存の状況を照会し、必要に応じて管理組合および管理業者にも問い合わせたうえで、当該書類の有無が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。
なお、管理組合や管理業者と売主等以外の者が当該書類を保存している場合には、その旨を合わせて説明します。
国土交通省令第16条の2の3で定める書類は、次のとおりです。
① 建築基準法第6条第1項棟の規定による確認申請書および確認済証
② 建築基準法第7条第5項等の検査済証
③ 法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の結果についての報告書
④ 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書
⑤ 建築基準法施行規則第5条第3項(建築物の定期報告)および同規則第6条第3項(建築設備の定期報告)に規定する書類
⑥ 当該住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法ならびにこれに基づく命令および条例の規定に適合するものまたはこれに準ずるものであることを確認できる書類で、次に掲げるもの
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
ロ 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項の建設住宅性能評価書
ハ 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の保険契約(瑕疵担保責任保険契約)が締結されていることを証する書類
二 イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
代金等以外に授受される金銭

「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」
趣旨
代金、交換差金および借賃以外に授受される金銭
手付金
契約締結の際に当事者の一方から相手方に交付される金銭です。
不動産の売買の場合に買主から交付されるものが多いが、賃貸借や請負などその他の有償契約でも行われます。
礼金
建物賃貸借の締結に際し、敷金、保証金、権利金などとはまったく性格の異なる金銭として賃借人から賃貸人に支払われる一時金です。
法的な性格は明確ではなく、慣行的に支払われているもので、契約終了時には返還されません。
敷金
不動産、中でも建物の賃貸借契約の締結に際し、賃借人の将来の賃料債務、損害賠償債務などを担保する目的で、賃借人から賃貸人に交付される金銭です。
契約終了時には返還されますが、もし賃借人の債務があれば、その額が控除されて返還されます。
権利金
借地、借家契約の締結に際し授受されますが、その性格には、権利設定の対価や営業上の利益、のれん代、営業権設定の対価あるいは賃料の前払い的性質のもの、賃料を低廉にする対象のものなど様々なものがあります。
多くは契約終了時には返還されません。
保証金
多くはビルや店舗などの事業用の建物の賃貸借契約の締結に際し授受されますが、その性格には、権利金の性格を持つもの、建設協力金の性格をもつもの、敷金の性格をもつもの、消費貸借の金銭であるもの、違約金としての性格をもつものなど、様々なものがあります。
現実に重視される金銭がどれにあたるかは当事者間の約定で決まります。
そのいずれかにより、契約終了時の返還の要否が決定されます。
説明すべき内容
そこで、次の事項を明らかにする必要があります。
① その名称
② 受理される額
③ 重視される目的
契約の解除

「契約の解除に関する事項」
趣旨
このため、契約の解除に関する事項を重要事項として契約の成立の際にあらかじめ説明することを義務付け、紛争を防止しています。
説明すべき内容
② どのような手続きで契約を解除できるか
③ 催告期間はどれくらいか
④ 解除すると、どのような効果が発生するか
業法の解釈・運用の考え方
なお、買主と建設業者等の間で予算、設計内容、期間等の協議が十分に行われていないまま、建築条件付土地売買契約の締結と工事請負契約の締結を同日または短期間のうちに行われることは、買主の希望等特段の事由がある場合を除き、適当ではありません。
損害賠償額の予定等
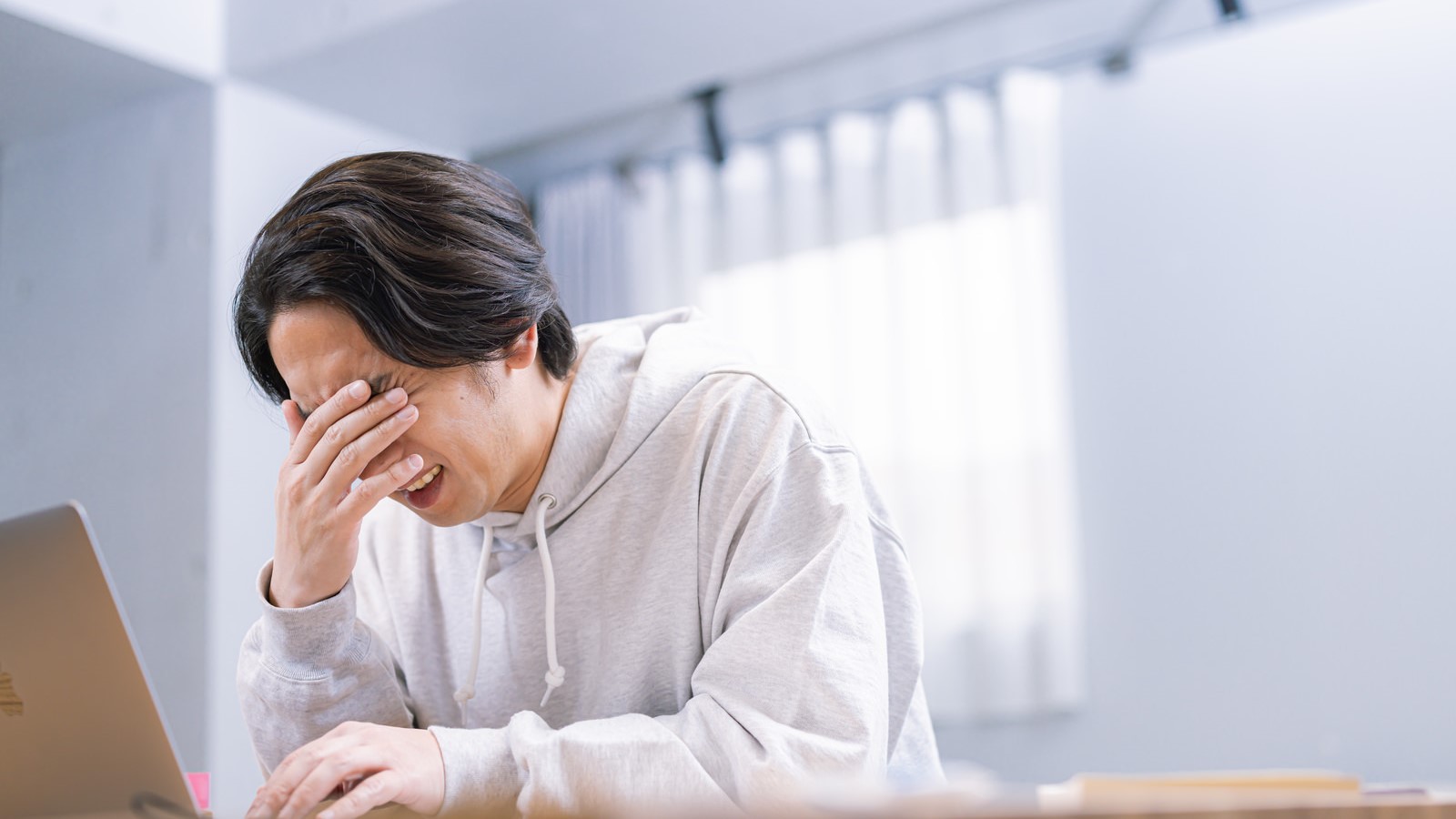
「損害賠償額の予定または違約金に関する事項」
趣旨
その内容をあらかじめ明確にしておくため、重要事項として説明させることとされています。
損害賠償額の予定と違約金
契約の当事者が債務不履行した場合、その実損額の額の証明を行うことは難しいため、あらかじめ損害賠償額を予定しておいて、債務不履行の事実さえあれば、実損額がいくらかを証明することなく、その額を支払うことを約定するものです。
違約金
賠償額の予定と同意義で使用される場合と、違約罰の意義で使用される場合があります。
民法では違約金を、前記「損害賠償額の予定」で解説した損害賠償の予定と推定しています(民法第420条第3項)。
違約金が、違約罰の意義で使われている場合は、違約金の請求のほか、別途損害賠償を行い得ることとなります。
説明すべき内容
② その額
③ その趣旨と定めの内容
これらはいずれも、宅建業者が自ら売主となる売買のときには、その合計額が代金の額の2割を超えてはならないとされています(宅地建物取引業法第38条第1項)
手付金等の保全措置の概要

「第41条第1項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条または第41条の2の規定による措置の概要」
参考:宅地建物取引業法第41条(手付金等の保全)【e-GOV】
趣旨
説明すべき内容
① 保証委託契約による措置か、保証保険契約による措置かの別
② 上記保全措置を行う期間の名称または商号
完成物件の場合
① 保証委託契約による措置か、保証保険契約による措置か、手付金等寄託契約および質権設定契約による措置かの別
② 上記保全措置を行う期間の名称または商号
業法の解釈・運用の考え方
宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置をとる場合においては、手付金薹寄託契約を締結した後に、売主と買主の間で質権設定契約を締結しなければならない旨を、買主に対して十分に説明しなければなりません。
なお、質権設定契約は、手付金と寄託契約の締結後であれば売買契約の締結前に行っても差し支えないこと、質権設定契約はあくまで手付金等の保全のための措置であり、売買契約の申込み、予約などとは異なるものであること、手付金と寄託契約の締結後の金銭の支払いは、買主から指定保管機関に対して直接行われることとされています。
支払金・預り金の保全

「支払金または預り金を受領しようとする場合において、宅地建物取引業法第64条の3第2項の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」
※「その措置の概要」とは、保全の措置を行う機関の種類およびその名称または商号です。
支払金または預り金
ただし、次のものは保全措置を講ずるかどうかの説明を要しません。
① 50万円未満のもの
② 未完成または完成物件の売買において法定の保全措置が講じられている手付金等
③ 売主または交換の当事者である宅建業者が登記以後に受領するもの
④ 報酬
保証措置または保全措置の内容
宅地建物取引業保証協会が、一般保証業務(社員である宅建業者との契約により、受領した支払金または預かり金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務)として行う保証措置
保証措置
① 銀行等が一般保証委託契約に基づいて行う保全措置
② 保険事業者が保証保険契約に基づいて行う保全措置
③ 一般寄託契約および一般試験設定契約による保全措置
ローンのあっせん

「代金または交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」
趣旨
したがって、宅建業者が、宅地建物の売買にあたり、これらのローンのあっせんをするときは、あっせんの内容、あっせんしたローンが不成立となった場合の措置を重要事項として、あらかじめ説明することを義務付けたものです。
金銭の貸借のあっせんの内容
① 宅建業者はローンのあっせんとしてどのようなことをするか
② 融資条件
a ローンの金額
b ローンの金利
c ローンの返済方法 など
金銭の貸借が成立しないときの措置
なお、ローンあっせんの場合だけでなく、金融機関等のローンを利用することを条件として契約する場合にも同様に書面に明記すべきです。
金融機関との金銭消費貸借に関する保証委託契約が成立しないとき、または金融機関の融資が認められないときは、売主または買主は売買契約を解除することができる旨、および解除権の行使が認められる期限を設定する場合にはその旨を説明します。
また、売買契約を解除したときは、売主は手付または代金の一部として受領した金銭を無利息で買主に返還しなければなりません。
契約不適合責任の履行に関する措置の概要
「当該宅地建物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」
国土交通省令で定める契約不適合責任の履行に関する措置
① 保証保険契約または責任保険契約の締結
② 保証保険または責任保険を付保することを委託する契約の締結
③ 債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
④ 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(履行確保法)」第11条第1項に規定する住宅販売瑕疵担保保証金の供託
担保責任(契約不適合責任)の履行に関する措置
保証保険契約または責任保険契約
当該保険を行う機関の名称または商号、保険期間、保険金額および保険の対象となる宅地建物の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合(以下「契約不適合」という)の範囲
保証保険または責任保険の付保を委託する契約
当該保険の付保を受託する機関の名称または商号、保険期間、保険金額および保険の対象となる宅地建物の契約不適合の範囲
保証委託契約
保証を行う機関の種類およびその名称または商号、保証債務の範囲、保証期間および保証の対象となる宅地建物の契約不適合の範囲
例えば新築住宅の売主Aが当該住宅を機関Bに登録し、機関Bが当該登録に基づいて売主Aの担保責任に関する責任保険の付保を行う場合には、機関Bへの登録に基づき機関Bが売主Aの担保責任に関する責任保険の付保を行う旨、保険期間、保険金額および保険の対象となる契約不適合の範囲を説明することとされています。
当該措置の概要として、当該措置に係る契約の締結などに関する書類を別添することとしても差し支えありません。
当該宅地または建物が、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前のものである等の事情により、重要事項の説明の時点で担保責任の履行に関する措置にかかる契約の締結が完了しない場合にあっては、当該措置に係る契約を締結する予定であることおよびその見込みの内容概要について説明するものとされています。
施工規則第16条の4の2第4号に掲げる担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、「その措置の概要」として、次に掲げる事項を説明することとされています
① 住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする供託所の表示および所在地
② 履行確保法施行令第7条第1項の販売新築住宅については、同項の書面に記載された2人以上の宅建業者それぞれの販売瑕疵負担割合(同項に規定する販売瑕疵負担責任割合)の合計に対する当該宅建業者の販売瑕疵負担割合の割合
(注意)
新築住宅を販売する宅建業者は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という)による住宅の構造耐力上主要な部分等にかかる契約不適合責任の履行を確保するために、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律により、新築住宅の引渡し戸数(国土交通大臣の指定する住宅瑕疵担保責任保険法人と締結した一定の保険契約にかかる新築住宅を除く)に応じた一定の額の住宅販売瑕疵担保保証金を供託していなければならないとされています。
これに違反した宅建業者は、各基準日の翌日から起算して、50日を経過した日以降に、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはなりません。
これに違反した場合は、宅地建物取引業法第65条で定める指示または業務停止処分を受けることになります。
その他省令で定める事項

「その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性および契約内容の別を勘案して、次のイまたはロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イまたはロに定める命令で定める事項
イ 事業を営む場合以外の場合において宅地または建物を買い、または借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 (施行規則第16条4の3)
ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合
趣旨
(以後の説明では、以下の記号で示します)
宅地の売買または交換の契約 【宅・売】
建物の売買または交換の契約 【建・売】
宅地の貸借の契約 【宅・貸】
建物の貸借の契約 【建・貸】
宅地建物が造成宅地防災区域内にある旨
当該宅地または建物が「宅地造成および特定盛土等規制法」第45条第1項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
宅地建物が土砂災害警戒区域内にある旨
当該宅地または建物が「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
宅地建物が津波災害警戒区域内にある旨
当該宅地または建物が「津波防災地域づくりに関する法律」第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
水防法の規定による図面における宅地または建物の所在
「水防法施行規則」第11条第1号の規定により当該宅地建物が所在する市町村の長が提供する図面に表示されているときは、当該宅地建物の所在地
本説明義務は、売買・交換・貸借の対象である宅地または建物が水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水(以下「内水」という)・高潮)ハザードマップ(以下「水害ハザードマップ」という)上のどこに所在するについて消費者に確認するものです。
取引の対象となる宅地または建物の位置を含む水害ハザードマップを、洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当該宅地または建物の概ねの位置を示すことにより行います。
石綿の使用の有無の調査結果
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
石綿の塩の有無の調査結果の記録が保存されているときは、「その内容」として、調査の実施機関、調査範囲、調査年月日、石綿の使用の有無および石綿の使用の箇所を説明することとされています。
ただし、調査結果の記録から、これらのうちいずれかが判明しない場合は、売主等に補足情報の告知を求め、それでもなお判明しないときは、その旨を説明すれば足りるものとされています。
なお、調査結果の記録から容易に石綿の使用の有無が確認できる場合には、当該調査結果の記録を別添しても差し支えはありません。
本説明義務については、売主および所有者に当該調査の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合、管理業者および施工会社にも問い合わせたうえで、存在しないことが確認された場合またはその存在が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。
なお、本説明義務については、石綿の使用の有無の調査の実施自体を宅建業者に義務付けるものではありません。
また、紛争の防止の観点から、売主から提出された調査結果の記録を説明する場合は、売主等の責任の下に行われた調査であることを、建物全体を調査したものではない場合は、調査した範囲に限定があることを、それぞれ明らかにしなければなりません。
耐震診断の結果
当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く)が建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法」という)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて、次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士
ハ 品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
建物の耐震診断の結果について、次の書類を別添しても差し支えありません。
① 品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し
(当該家屋について平成13年国土交通省告知第1346号の別表2-1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)にかかる評価を受けたものに限ります)
② 租税特別措置法施行規則に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類または地方税法施行規則に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類であって所定の税制特例を受けるために必要となる証明書(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、固定資産税減額証明書または耐震改修に関して発行された増改築等工事証明書)の写し
③ 指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体が作成した建築物の耐震診断結果報告書の写し
1981年(昭和56年)5月31日以前に確認を受けた建物であるか否かの判断にあたっては、確認済証または検査済証に記載する確認済証交付年月日の日付をもとに判断することととされています。
確認済証または検査済証がない場合は、建物の表題登記をもとに判断することとされており、その際、居住の用に供する建物(区分所有建物を除く)の場合は、表題登記日が1981年(昭和56年)12月31日以前であるもの、事業の用に供する建物および所有区分所有建物の場合は、表題登記日が1983年(昭和58年)5月31日以前であるものについて説明を行うこととされています。
また、家屋課税台帳に建築年月日の記載がある場合についても。同様に取り扱うこととされています。
本説明義務については、売主および所有者に当該耐震診断の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合および管理業者にも問い合わせたうえ、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。
なお、本説明義務については、耐震診断の実施自体を宅建業者に義務付けるものではありません。
耐震改修促進法の一部を改正する法律の施行前に行った耐震診断については、改正前の。耐震改修促進法第3条に基づく特定建築物の耐震診断および耐震改修に関する指針に基づいた耐震診断であり、耐震診断の実施主体が規則第16条の4の3第5号イから二までに掲げる者である場合には、同号に規定する耐震診断として差し支えありません。
住宅性能評価制度を利用する新築住宅である旨
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
ここでの説明義務は品確法の住宅性能評価制度を利用した新築住宅であるか否かについて消費者に確認するものです。
当該評価の具体的内容の説明義務を宅建業者が負うものではありません。
浴室、便所等建物の設備の整備の状況
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
建物の貸借の契約の場合においては、浴室、トイレ、台所等の建物の設備の整備の有無、形態、使用の可否等と日常生活において通常使用する設備の整備の状況を説明事項としています。
例えば、ユニットバスなどの設備の形態、エアコンの使用の可否が該当します。
また、ここで掲げた設備は、専ら居住用の建物を念頭に置いた例示です。
事業用の建物(オフィス、店舗等)にあっては、空調設備など事業用の建物に固有の事項のうち、事業の業種、取引の実情などを勘案し重要なものについて説明しなければなりません。
契約期間および契約の更新に関する事項
契約期間及び契約の更新に関する事項
例えば、契約の始期および終期、2年毎に更新を行うこと、更新時の賃料の改定方法などが該当します。
また、こうした定めがない場合には、その旨の説明を行わなければなりません。
定期借地権、定期建物賃貸借および終身建物賃貸借
「借地借家法」第2条第1号に規定する借地権で同法第22条第1項の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、または建物の賃貸借で同法第38条第1項もしくは「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第52条第1項の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
「定期借地権を設定しようとするとき」、「定期建物賃貸借契約または終身建物賃貸者契約をしようとするとき」は、その旨を説明することとされています。
なお、定期建物賃貸借に関する上記説明義務は、借地借家法第38条第2項に規定する賃貸人の説明義務とは別のものです。
また、宅建業者が賃貸人を代理して当該説明義務を行う行為は、宅建業法上の貸借の代理の一部に該当し、関連の規定が適用されることになります。
用途その他の利用の制限に関する事項
当該宅地建物の用途その他の利用の制限に関する事項(区分所有建物の場合は、第16条の2第3号に掲げる事項を除く)
例えば、事業用としての利用の禁止などの制限、事業用の業種の制限のほか、ペット飼育の禁止、ピアノ使用の禁止等の利用の制限が該当します。
なお、増改築の禁止、内装工事の禁止など、賃借人の権限に本来属しないことによる制限については、ここでは含まれないものとされています。
契約終了時における金銭の清算に関する事項
敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
例えば、賃料等の滞納分との相殺や一定の範囲の原状回復費用として敷金が充当される予定の有無、原状回復義務の範囲として定められているものなどが該当します。
なお、本事項は、貸借の契約の締結に際してあらかじめ定めている事項を説明すべき事項としたものです。
こうした事項が定まっていない場合には、その旨を説明しなければなりません。
管理委託を受けた者の氏名および住所
当該宅地建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号または名称)および住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
アパート等の賃貸においても、区分所有建物の場合と同様に、重要事項説明書に管理者の氏名、住所および賃貸住宅管理業者登録規程(第5条第1項第2号の登録番号を記載し。その旨を説明することとされています。
ただし、賃貸住宅管理業者登録規定の登録を受けていない場合には、管理者の氏名および住所を記載し、説明することとされています。
なお、ここでいう管理者には、単純な清掃等、建物の物理的な維持行為のみを委託されている者までも含む趣旨ではありません。
契約終了時における建物の取壊しに関する事項
契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
主に一般定期借地権を念頭に置いているものです。
例えば、50年後に更地にして返還する条件がある場合にあっては、その内容が該当します。
割賦販売の場合の条件

「宅地建物の割賦販売の場合にあっては、次の事項
① 現金販売価格
② 割賦販売価格
③ 宅地建物の引渡しまでに支払う金銭の額、賦払金の額ならびにその支払の時期・方法
趣旨
この場合、特にその条件を明らかにすることとされています。
現金販売価格と割賦販売価格
割賦販売価格とは、割賦販売の方法により販売する場合の価格をいいます。
つまり、現実の代金総額です
現金販売価格と対比させて、割賦販売価格を説明事項としている理由は、販売をする宅建業者の側からの信用供与に対応する価格の値上がり分がどれくらいか、いいかえれば、割賦販売の方法によって代金の支払いを繰り延べてもらった代わりに、物件の価格が現金支払いに比べてどれくらい高くなるかを明らかにするためです。
宅地建物の引渡しまでに支払う金銭の額および賦払金の額ならびにその支払いの時期および方法
賦払金は、代金の額から頭金を除いた残余のものが分離されて支払われる際の各回ごとの支払分をいいます。
イ これらの頭金や不払い金の額がいくらになるか
ロ これらの支払時期や、支払方法がどうなっているか
上記は、割賦販売における買主とって、買主が持つ購買力との見合いで非常に重要であり、説明事項とされています。
宅建業者が信託受益権の売主となる場合の説明事項

宅建業者は、自己の不動産を信託し、その受益権を販売する場合、当該信託財産にかかる宅地建物に関し、少なくとも次に掲げる事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
① 登記された権利の種類および内容、ならびに登記名義人または所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
② 法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
③ 私道に関する負担に関する事項
④ 飲用水、電気およびガスの供給施設・排水施設の整備の状況
⑤ 未完成物件のときは、工事完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
⑥ 区分所有建物のときは、敷地の権利の種類および内容、共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物またはその敷地に関する権利およびこれらの管理または使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
⑦ その他売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがないとして国土交通省令(施行規則第16条の4の4)で定める場合(例えば、相手方が特定投資家である場合)は、この限りではありません。
終わりに
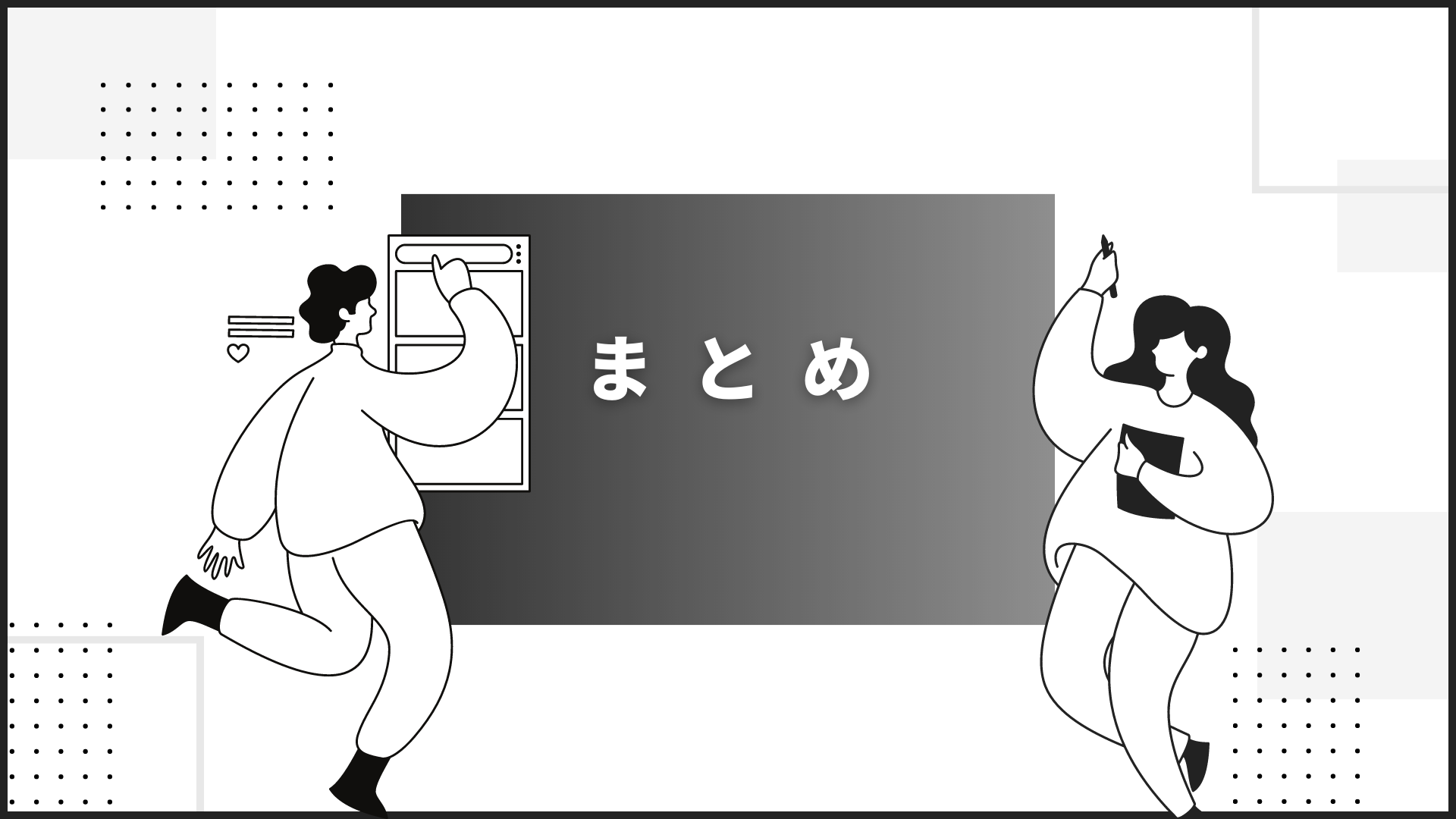
かなりのボリュームとなりましたが、1つ1つの事項がさらに掘り下げてお話しができるものばかりです。
重要事項説明は、説明する内容がどんどん増えていっており、説明する側の準備に対する負担が大きくなっています。
そして、説明を受ける側も、慣れない様々なことについて説明を受けなければならず、何が重要なのかわからなくなっているように感じます。
極論すればすべてが重要であり、説明をし出せばキリがありませんし、説明を聞く側にとっても、その場ではなんとなくでも理解ができても、あとで振り返ると正しく理解できていない方が実に多い。
このようなことで果たして良いのかと考えますが、ではどうすればよいかというと答えは簡単ではありません。
取引には様々な状況があり、対象の不動産も様々です。
定型化することではなく、個別の状況を理解し的確で柔軟な対応がより大切ではないでしょうか。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
