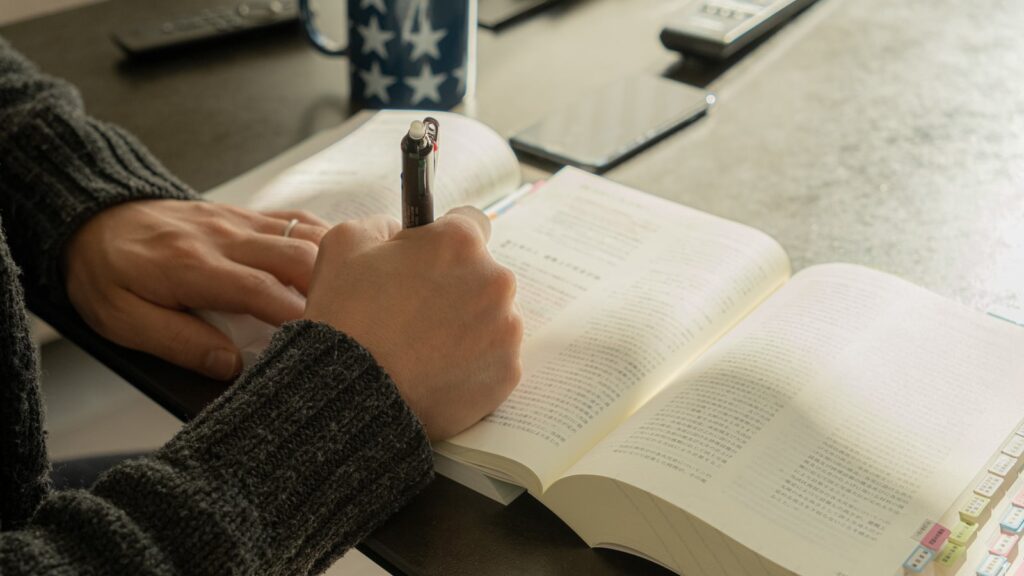
宅地建物取引業者は、宅地建物取引に関する知識および経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されています。
このため、宅地建物取引業法では、単に免許制度を実施するに止まらず、一定の試験に合格した有資格者を宅地建物取引士として業者のもとに置かなければならないこととされています。
当初は宅地建物取引士ではなく、宅地建物取引員という名称でしたが、1965年(昭和40年)の法改正により宅地建物取引主任者となりました。
しばらく宅地建物取引主任者という名称でしたが、その後2014年(平成26年)6月25日に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が公布され、「宅地建物取引主任者」は2015年(平成27年)4月1日から宅地建物取引士となりました。
当法改正と併せて、宅地建物取引士の定義や業務の明文化、信用失墜行為の禁止、知識および能力の維持向上などの義務が追加されています。
不動産取引の実務において、宅地建物取引士でなければ行うことができない独占業務(専権業務)が3つあります。
① 重要事項の説明
② 重要事項説明書(35条書面)への記名
③ 契約書(37条書面)への記名
不動産取引は権利関係が複雑で、法令上の制限も多いほか、契約の取引条件も複雑かつ取引価額も高額です。
そのため、業務の運営の適正性や宅地建物取引の公正性を確保するため、宅地建物取引に関して専門的かつ広範な知識を有する宅地建物取引士の設置を義務付けられています。
宅地建物取引士は、不動産取引を行ううえで極めて重要な立場であり、業務を行うことを改めて認識しなければなりません。
特に重要事項の説明は、宅地建物取引についての経験や知識の乏しい消費者が、契約対象物件や取引条件について十分理解しないままに契約を締結し、後に契約目的を達成できず不測の損害を被るといった状況を防ぐため、契約締結の判断に重大な影響を与える事項について説明することを義務付けたものです。
今回は、宅地建物取引士の事務の1つ「重要事項の説明」について、お話し致します。
重要事項説明の趣旨

また、建ぺい率や容積率などの法令上の利用の制限を知らないまま売買契約などを締結すると、予定した建築物が建てられないなど、契約の目的を達することができません。
さらに、契約の解除や違約金あるいはローンの利用等の取引上の諸条件が不明確で、これらについて当事者は十分納得しないまま契約を締結してしまうと、後になって当事者(特に買主が消費者の場合)が思わぬ損害を被ることがあります。
このような事態を防止するためには、宅地建物取引の当事者が取引の対象となる宅地や建物についての私法上、公法上の権利関係、取引条件などの取引上の重要事項について十分調査し、確認したうえで契約を締結しなければなりません。
しかしながら、一般の購入者などは、通常、取引しようとする物件についての権利関係や法令上の制限などを自分で調査する能力を充分に有しておらず、取引条件についても十分な知識を持ちあわせていません。
そのため、宅建業者は、宅地建物取引を業として専門に行っており、調査能力も備わっており、知識経験も豊富であり、また一般の購入者なども、そのような面での期待をもって注文し、依頼をします。
したがって、宅建業者に対して、契約成立までの間に取引の相手方などに、物件に関する事項や取引条件などの一定の重要事項を説明することが義務付けられています。
宅地建物取引士が説明をしなければならない理由
契約締結に先立って説明を義務付けられている法令上の制限や取引条件などの重要事項は、相当高度な知識や調査能力がなければ正確で十分な説明をすることができません。
そのため、宅建業者はその従事者のうちでも、宅地建物取引士の資格を持つ者に重要事項の説明をさせなければならないとし、購入者等が誤りのない情報に基づいて。的確な判断のもとに契約を締結することができるようにしています。
宅建業者が買主または借主となる場合の取扱い
なお、対面説明が不要とされる場合でも、重要事項説明書の交付義務を負う宅建業者は、交付すべき書面の作成にあたって宅地建物取引士に記名させなければなりません。
制度の概要

説明をしなければならない相手
(説明すべき相手) 買主となろうとする者 (※注1)
(宅建業者の立場) 自ら交換の当事者となる場合
(説明すべき相手) 取得しようとする者
(宅建業者の立場) 売買の代理をする場合
(説明すべき相手) 買主となろうとする者
(宅建業者の立場) 交換の代理をする場合
(説明すべき相手) 取得しようとする者
(宅建業者の立場) 賃借の代理をする場合
(説明すべき相手) 借主となろうとする者 (※注2)
(宅建業者の立場) 売買の媒介をする場合
(説明すべき相手) 買主となろうとする者
(宅建業者の立場) 交換の媒介をする場合
(説明すべき相手) 取得しようとする者
(宅建業者の立場) 賃借の媒介をする場合
(説明すべき相手) 借主となろうとする者 (※注2)
※注1
「自ら売買の当事者となる場合」とありますが、売主が非業者、買主が宅建業者の直接売買取引では、宅建業者が自分に説明しても無意味ですので、実際には宅建業者が売主として売買する場合となります。
※注2
宅建業者が自ら貸主として賃貸する行為は、宅建業法の規制対象外です。
そのため、貸主が重要事項説明を行う義務はありません。
説明すべき時期
相手方がその物件や取引条件について十分に理解し、熟考したのち契約を締結するように、できるだけ早い時期、すなわち取引物件がある程度特定した時期に説明をするのが望ましいでしょう。
説明の方法
この書面は重要事項説明書と呼ばれ、宅地建物の売買・交換用、区分所有建物の売買・交換用、宅地の貸借用、建物の貸借用に分けて、国土交通省の標準様式が示されています。
ただし、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づく宅建業法の改正により、2022年(令和4年)5月18日以降は、書面の交付に代えて、政令で定めるところにより説明すべき相手方などの承諾を得たうえで、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって宅地建物取引士の記名に変わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することも可能となりました。
重要事項の説明は、相手方と対面で行うことが原則とされています。
ただし、宅地または建物の所有者または借主となる者が宅建業者である場合における重要事項説明では、重要事項説明書の交付のみで足り、対面説明は不要です。
IT重説について
IT重説では、パソコンやテレビ、タブレットなどの端末の画像を利用して、対面と同様に説明を受け、あるいは質問を行える環境が必要です。
これまで、賃貸契約に係る取引(宅地または建物の賃貸の代理または媒介)に限り運用されていましたが、2021年(令和3年)3月30日から売買等に係る取引(宅地または建物の売買・交換、売買・交換の代理または媒介)の重要事項説明において、下記の4つの条件の全てを満たしている場合に限り、対面による重要事項説明と同様に扱うこととされました。
また、宅地建物取引士は、ITを活用した重要事項の説明を開始したのち、映像を視認できない、または音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消されたのちに説明を再開しなければなりません。
① 宅地建物取引士および重要事項の説明を受けようとする者が、図面などの書類および説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやり取りできる環境において実施していること。
② 宅地建物取引士により記名された重要事項説明書および添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ交付(電子的方法による提供を含む)していること。
③ 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書および添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること、並びに映像および音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。
④ 宅地建物取引士が、宅地建物取引証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。
説明に先立って
宅建業法第35条第1項各号に掲げる事項は、宅建業者がその相手方または依頼者に説明すべき事項のうち最小限の事項を規定したものであり、これらの事項以外にも場合によっては説明を要する重要事項があり得ます。
重要事項の説明は、説明を受ける者が理解しやすい場面で分かりやすく説明することが望ましく、取引物件に直接関係する事項であるため、取引物件を見ながら説明する方が相手方の理解を深めることができると思われる事項については、重要事項の全体像を示しながら取引物件の現場で説明することが望ましい。
ただし、このような場合でも、説明を受ける者が重要事項全体を十分に把握できるよう、従来どおり契約の締結までの間に改めて宅地建物取引士が重要事項全体の説明をしなければなりません。
宅地建物取引士証の提示義務
提示しなかったときは、10万円以下の過料に処せられます。
宅地建物取引所の提示義務に違反した場合、「宅地建物取引士として行う事務に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき」に該当するものとして、同項の規定により指示処分または宅建業法第68条第2項の規定により、1年以内の期間を定めて事務禁止処分が行われます。
提示の方法としては、宅地建物取引証を胸に着用するなどにより、相手方または関係者に明確に示すようにするとよいでしょう。
なお、宅地建物取引証の提示の際は、住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えありません。
ただし、シールは容易に剥がすことができるようにして、宅地建物取引証を汚損しないように注意しなければなりません。
宅地建物取引士の記名
重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名を要することとされています。
これは、宅地建物取引士が重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致して誤りなく記載されていることを確かめたうえで記名するという方法をとっています。
これによって、重要事項説明書の作成とこれに基づく重要事項の説明等を担当した宅地建物取引士の責任を明確にしています。
宅建業法35条の重要事項と宅建業法47条の重要な事項の関係
【宅建業法第47条(業務に関する禁止事項)】
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項
ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
本条の趣旨は、宅建業者は、顧客などに最初に接触した段階から最後の取引の簡潔に至るまでの間に、一定の事項について故意に事実を告げなかったり、あるいは不実(真実でないこと)を告げてはならないということです。
宅建業法では、これらの事項で顧客などの判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて、故意の不告知または不実告知の行為を重い罰則をもって禁止しています。
説明すべき重要事項

参考:宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)【e-GOV】
説明すべき事項
(1) 登記された権利の種類および内容、ならびに登記名義人または所有者の氏名(法人はその名称)
(2) 法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものの概要
(3) 建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道負担に関する事項
(4) 飲用水、電気およびガスの供給、排水のための施設の整備の状況
(5) 未完成物件のときは、完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
(6) 区分所有建物のときは、敷地に関する権利の種類等の国土交通省令・内閣府令で定めるもの
① 敷地に関する権利の種類および内容
② 共用部分に関する規約の定め
③ 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め
④ 専用使用権の内容
⑤ 管理費用等の負担を特定の者にのみ減免する旨の定め
⑥ 計画修繕積立金の定めおよび既に積み立てられている額
⑦ 通常の管理費用の額
⑧ 管理の委託先の氏名(法人はその名称)およ住所(法人はその主たる事務所所在地)
⑨ 維持修繕の記録
(6)の2 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合におけるその結果の概要
ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
【取引条件に関する事項】
(7) 代金、交換差金および借賃以外に授受される金銭の額および当該金銭の授受の目的
(8) 契約の解除に関する事項
(9) 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
(10) 手付金等を受領する場合は、その保全措置の概要
(11) 支払金または預り金を受領する場合は、その保全措置の有無および概要
(12) 金銭の貸借(ローン)のあっせんの内容および金銭の貸借が不成立の場合の措置
(13) 宅地または建物の契約不適合責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、措置を講ずる場合は措置の概要
(14) その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性および契約内容の別を勘案して、次のイまたはロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イまたはロに定める命令で定める事項
イ 事業を営む場合以外の場合において宅地または建物を買い、または借りようとする個人である宅建業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合
ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合
【割賦販売の場合に追加される説明事項】
(15) 宅地または建物の割賦販売(代金の全部または一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売すること)に関する事項
① 現金販売価格
② 割賦販売価格
③ 宅地または建物の引渡しまでに支払う金銭の額および賦払金の額、ならびにその支払の時期および方法
【信託の受益権売買の場合に追加される説明事項】
(16) 宅地または建物に係る信託の受益権の売主となる場合における説明事項
① 登記された権利の種類および内容、ならびに登記名義人または所有者の氏名(法人はその名称)
② 法令に基づく制限で政令で定めるものの概要
③ 私道負担に関する事項
④ 飲用水、電気およびガスの供給施設、排水施設の整備の状況
⑤ 宅地または建物が未完成の場合は、完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
⑥ 区分所有建物の場合は、敷地の権利の種類等の省令で定める事項
⑦ その他売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
賃貸の代理・媒介の場合の説明すべき事項
【対象物件に関する事項】
(1) 登記された権利の種類および内容、ならびに登記名義人または所有者の氏名(法人はその名称)
(2) 法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものの概要
(3) 建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道負担に関する事項
(4) 飲用水、電気およびガスの供給、排水のための施設の整備の状況
(5) 未完成物件のときは、完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
(6) 区分所有建物のときは、敷地に関する権利の種類等の国土交通省令・内閣府令で定めるもの
① 敷地に関する権利の種類および内容
② 共用部分に関する規約の定め
③ 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め
④ 専用使用権の内容
⑤ 管理費用等の負担を特定の者にのみ減免する旨の定め
⑥ 計画修繕積立金の定めおよび既に積み立てられている額
⑦ 通常の管理費用の額
⑧ 管理の委託先の氏名(法人はその名称)およ住所(法人はその主たる事務所所在地)
⑨ 維持修繕の記録
(6)の2 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合におけるその結果の概要
ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
【取引条件に関する事項】
(7) 代金、交換差金および借賃以外に授受される金銭の額および当該金銭の授受の目的
(8) 契約の解除に関する事項
(9) 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
(11) 支払金または預り金を受領する場合は、その保全措置の有無および概要
(14) その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性および契約内容の別を勘案して、次のイまたはロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イまたはロに定める命令で定める事項
イ 事業を営む場合以外の場合において宅地または建物を買い、または借りようとする個人である宅建業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合
ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合
【補足】
(6) 区分所有建物のときは、敷地に関する権利の種類等の国土交通省令・内閣府令で定めるもの
施行規則第16条の2に定めるもののうち、次の2項目を説明します。
③ 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め
⑧ 管理の委託先の氏名(法人はその名称)およ住所(法人はその主たる事務所所在地)
(7) 代金、交換差金および借賃以外に授受される金銭の額および当該金銭の授受の目的
賃貸の場合には、礼金、権利金、敷金、保証金等が問題となる場合が多いため、特に明確に説明を行う必要があります。
(14) その他の事項について
宅地の貸借の契約の場合には、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3の第1号から第3号までおよび第8号から第13号までに掲げられているものを説明します。
建物の貸借の契約の場合には、同16条の4の3の第1号から第5号までおよび第7号から第12号までに掲げられているものを説明します。
終わりに
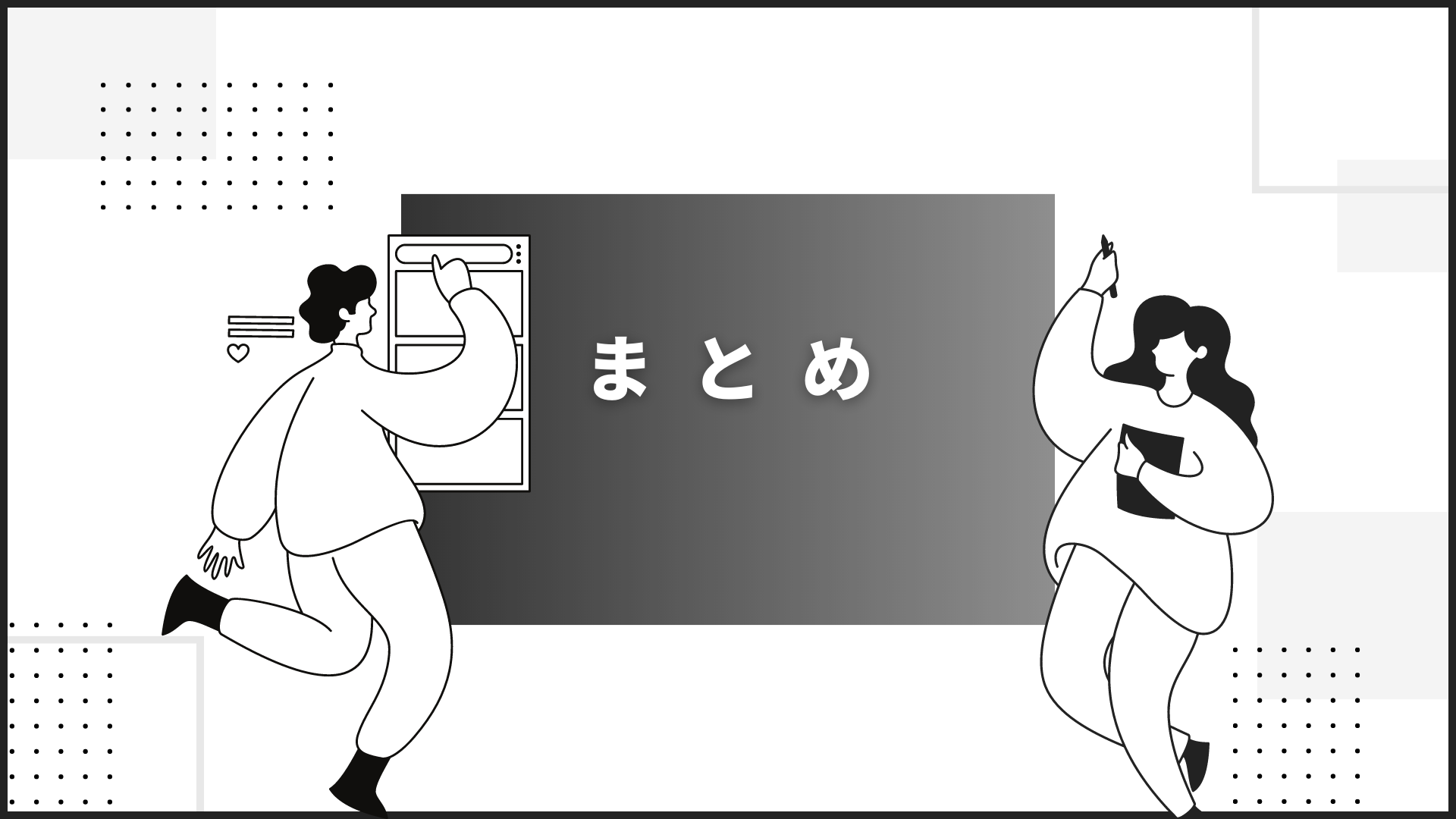
不動産業の業務には、専門知識を備えた宅地建物取引士にしか扱えない「独占業務」があります。
重要事項の説明を含めた3つの独占業務は、たとえ不動産会社の社長であっても、宅地建物取引士の資格を持っていない限り行うことはできません。
重要事項の説明は、宅地建物取引についての経験や知識の乏しい消費者が、契約対象物件や取引条件について十分理解しないままに契約を締結し、後に契約目的を達成できず不測の損害を被るといった状況を防ぐため、契約締結の判断に重大な影響を与える事項について説明することを義務付けたものです。
不動産取引は権利関係が複雑で、法令上の制限も多いほか、契約の取引条件も複雑かつ取引価額も高額です。
重要事項の説明を含めた3つの独占業務にかかわらず、有資格者を通じて取引を行うことは、安全に取引を行うための1つの方法です。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
