
前回は、「借家」契約の規制の要点について、お話ししました。
建物所有を目的とする他人の土地への利用権には、地上権と土地の賃借権および使用借権がありますが、借地借家法で借地権というのは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことです。
地上権は物権であり、土地を直接支配できる強い機能を持ちます。
すなわち、地上権者は地主の承諾を得ないで、第三者に地上権を譲渡したり、賃貸することができます。
これに対し、賃借権は、債権であり賃貸人の行為を通じて土地を間接的に支配できるのみで、機能は弱い。
そこで、賃借権を強化して両者の機能の差を少なくし(賃借権の物権化)、賃借人を保護するため1921年(大正10年)に借地法が制定され、1992年(平成4年)施工の改正法(新法)に引き継がれています。
なお、建物所有以外を目的とする、例えば露天の駐車場、材料置き場、露店などのための土地賃借権は、借地借家法でいう「借地権」ではありません。
このような土地賃貸借契約は、民法に基づいて対応することとなります。
いわゆる民法上の土地賃借権です。
「借地権」は「借家権」に比べてなじみが薄く、一般的に知られていないことも多くあります。
今回は、借地契約の規制の要点について、お話し致します。
借地権の存続期間

それぞれ分けてご説明します。
新借地借家法の存続期間
借地権の存在期間は、堅固、非堅固の区別なく、一律に30年となります(借地借家法第3条)。
ただし、当事者が特約によりこれより長い期間を定めたときは、その期間となります。
旧借地法の堅固、非堅固の区別を廃止した理由は、建築技術の向上により、木造とそれ以外のものを区別する合理的根拠がなくなり、また実際にも堅固か非堅固か区別がつかず、争われる例がたくさんあったためです。
当初の存続期間が満了したのち借地契約が更新された場合は、1回目の更新のときはその存続期間は20年、2回目以降の更新からは10年となります(借地借家法第3条)。
いずれの場合も、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間となります。
更新後の期間が当初の期間より短くなっているのは、契約が更新されたのちは当事者双方の事情の変化を考慮して適切に権利調整を行える機会を多くすることが妥当と考えられるためです。
旧借地法における存続期間
① 存続期間の定めがある場合
(1) 最短期間の制限
借地上に建築する建物が、石造、レンガ造り、土造、コンクリート造、ブロック造など堅固な建物である場合は30年、その他の建物(木造など)である場合は20年となります。
また、これらよりも短い期間を定めた場合には、期間の定めがないものとみなされます。
なお、これ以上の期間を定めることは自由です。
(2) 建物の朽廃の場合
朽廃(建物が古くなって自然に朽ちて使用できない状態になること。滅失とは異なります)によって借地権は消滅しません。
② 存続期間の定めがない場合
(1) 法定期間
堅固な建物は60年、その他の建物は30年です。
堅固かどうかを契約で定めなかったときは、非堅固建物所有の目的とみなされます。
(2) 期間満了前の建物朽廃の場合
法定存続期間満了前に建物が朽廃した場合は、借地権は消滅します。
借地権の対抗力

借地権が対抗力を有する方法には、「借地権の登記」と「借地上の建物の登記」があります。
借地権が対抗できれば、借地関係はそのまま新しい土地所有者に承継され、また土地の抵当権者に対しても自己の権利を主張することができ、何の影響も及ぼされません。
借地権の登記
地上権は物権ですから、地主に登記協力義務があり、地主がこれに応じなければ裁判所の確定判決で登記の強制をすることができます。
ところが、賃借権は債権であるため、特約がない限り地主に登記協力義務がなく、その登記を法律で強制できません。
したがって、一般に土地賃借権の登記は行われず、新地主に対抗することができなくなってしまいます(売買は賃貸借を破る)。
民法の一般原則によれば、そのような結果となります。
そこで、借地人を保護するため、借地借家法第10条の規定があります。
次の「借地上の建物の登記」をご覧ください。
借地上の建物の登記
前述の民法の不備を補い、登記請求権のない土地斟酌人を保護しています(建物登記は借地権者が単独ですることができます)。
この登記は表示の登記でも足りますが、建物の登記名義人が借地権者本人でない場合(借地権の妻や長男である場合など)には、判例では対抗力がないとされています。
建物滅失の場合の対抗力の保持
対抗力も失われ、滅失後にその土地を譲り受けたもののような第三者に対抗できなくなってしまうという問題が、かねてから指摘されていました。
そこで、新法では、建物の滅失があっても、借地権者がその建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日および建物を新たに築造する旨をその土地の上の見やすい場所に掲示すれば、滅失の日から2年を経過するまでの間に建物を再築し、かつ登記する限りその間は対抗力を有することとなりました(借地借家法第10条第2項)。
正当の事由(借地契約の更新・更新拒絶の要件)

しかし、更新の合意ができない場合でも、借地人を保護するため、法は規定を設けています。
借地権の存続期間が満了するとき、借地上に建物がある場合に限り、借地権者は契約の更新を請求することができるものとしました。
この更新請求を地主が拒絶するためには、遅滞なく異議を述べ、しかも後述の「正当の事由」がなければいけません。
また、借地権の存続期間が満了したのち、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある限りこれと同じです。
更新された場合、更新後の存続期間は前述(借地権の存続期間)のとおり、最初の更新のときは20年、2回目以降の更新のときは10年となります。
ただし、旧法の適用を受ける借地権の場合の更新後の存続期間は、更新のときから堅固建物は30年、非堅固建物は20年となります。
正当事由
旧借地法は、正当事由の内容を「土地所有者が自ら土地を使用することを必要とする場合その他正当の事由」と概括的に規定していたが、新法ではこれを明確にしています(借地借家法第6条)。
① 借地権設定者および借地権者(転借地権者を含む)が土地の使用を必要とする事情
② 借地に関する従前の経過
③ 土地の利用状況
④ 借地権設定者が土地の明渡しの条件として、または土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申し出
以上の4項目が「正当事由」の考慮要素であるとしています。
なお、①が基本的な要素であるとされており、また④はいわゆる立退料のことです。
借地権の譲渡・転貸

「転貸」とは、借地人が、自己と地主との借地関係はそのまま残しておいて、借地を第三者に自ら貸主として賃貸することです。
地上権については譲渡・転貸を自由にすることができますが、賃借権の場合には地主(賃貸人)の承諾なしに行うことはできません。
地主の承諾がある場合
譲渡のときは、従来と同内容の契約が継続します。
しかし、存続期間は。従前の契約の残存期間のみとなります。
また、転貸のときも従前の契約の残存期間の範囲内の契約となります。
なお、借地人から転借した者は地主と直接には契約関係が生じませんが、地主は借地に転借人のいずれにも地代を請求することができます。
2020年(令和2年)4月1日施行の改正民法により、適法に転貸借を行った場合には、賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除しても転借人には対抗できないことが明記されました(民法第613条第3項)。
ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していた場合は除きます。
地主の承諾がない場合
もっとも、地主が承諾しないときは、建物の譲受人は地主に対して建物買取請求権を行使できます(借地借家法第14条)。
● 地主の承諾に代わる裁判所の許可。
賃借人がその建物を他人に譲渡する場合に、地主が土地の賃借権の譲渡または転貸を拒むときは、裁判所は賃借人の申立てにより、地主の承諾に代わる許可をすることができます(借地借家法第19条)。
なお、この場合、地主に優先的な買受権が認められています(借地借家法第19条第3項)。
参考:民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)【e-GOV】
地代等の増減額請求

ただし、当事者間において、一定期間増額しない旨の特約があった場合には、経済事情の変動があっても増額請求はできません。
地代等の増減額をめぐる紛争については、原則として、訴訟を提起する前に、調停申立てをしなければなりません(民事調停法第24条の2)。
これを調停前置主義といいます。
また、当事者が調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面の合意を調停申込みした場合には、調停委員会の定める調停条項に拘束されます。
これらは民事調停法に規定されています。
建物買取請求権

借地人の建物買取請求権
ただし、借地権の買取を請求できるわけではありません。
なお、借地人の賃料不払いによって賃貸借契約が解除された場合には、建物買取請求権は発生しないと解釈されています。
このような場合まで借地人を保護するのは不公平だからです。
建物取得者の建物買取請求権
建物買取請求権を行使した場合の効果
買主の地位に立つ借地権設定者が建物の代金を支払うまで、借地人は建物とその敷地の引渡しを拒絶できます。
ただし、建物については同時履行の抗弁権あるいは留置権、土地についてはそれらの権利の反射的効果に基づきます。
しかし、引渡しを拒む間の地代・賃料相当額は、借地権設定者に支払わなければなりません。
定期借地権

一般定期借地権
なお、上記の特約は、その内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)によって行うこともできる旨が「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により改正されました(借地借家法第22条第2項)。
事業用定期借地権等
また、存続期間を10年以上30年未満とする場合には、存続期間、更新等に関する規定などは、特約による排除がなくても適用されないこととしています。
これらの借地権を、事業用定期借地権等といいます(借地借家法第23条第1項、第2項)。
この存続期間は、法が制定された当初は、10年以上20年以下とされていましたが、その後の社会情勢の変化に伴う土地の利用形態の多様化に対応するために改正され、2008年(平成20年)1月1日から設定されるものについては、上記のとおり50年未満の契約期間のものが可能となりました。
この事業用定期借地権などの設定契約は、必ず公正証書によって締結しなければなりません(借地借家法第23条第3項)。
そのような借地契約であることを当事者に明確に認識してもらうことと、公証人の目を通して適法性を確保しようという目的があります。
建物譲渡特約付借地権
この特約によって借地権が消滅したときに、その借地権者あるいは建物の賃借人が建物の使用をしている場合には、それらの者が請求をすれば、その者と借地権設定者との間に期間の定めがない者契約が締結されたものとみなされます(借地借家法第24条第2項)。
自己借地権と一時使用目的の借地

自己借地権
民法では、所有権と制限物権その他の用益権が同一人に帰すると、所有権以外の権利は消滅するという混同の法理というものがあり、土地所有者が自らその土地の借地権者になることはできないものと考えられています。
しかし、これを貫くと、借地権付きマンションを分譲する場合、土地所有者はあえて形の上だけ誰かに借地権を設定し、その準共有持分を専有部分と共に譲渡するという遠回りな方法をとらざるをえません。
そこで、このような不便を解消するため、新法では借地権を設定するにあたって、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者(土地所有者)が借地権を有することができることとしました(借地借家法第15条第1項)。
また、借地権が借地権設定者に帰した場合でも、他の者とともにその借地権を有するときには、混同が生じず借地権は消滅しないものとなっています(借地借家法第15条第2項)。
一時使用目的の借地
一時使用にあたるかどうかは、契約書の文言にとらわれず、諸般の事情を総合的、客観的に判断して決定されます。
新法(借地借家法)の適用関係
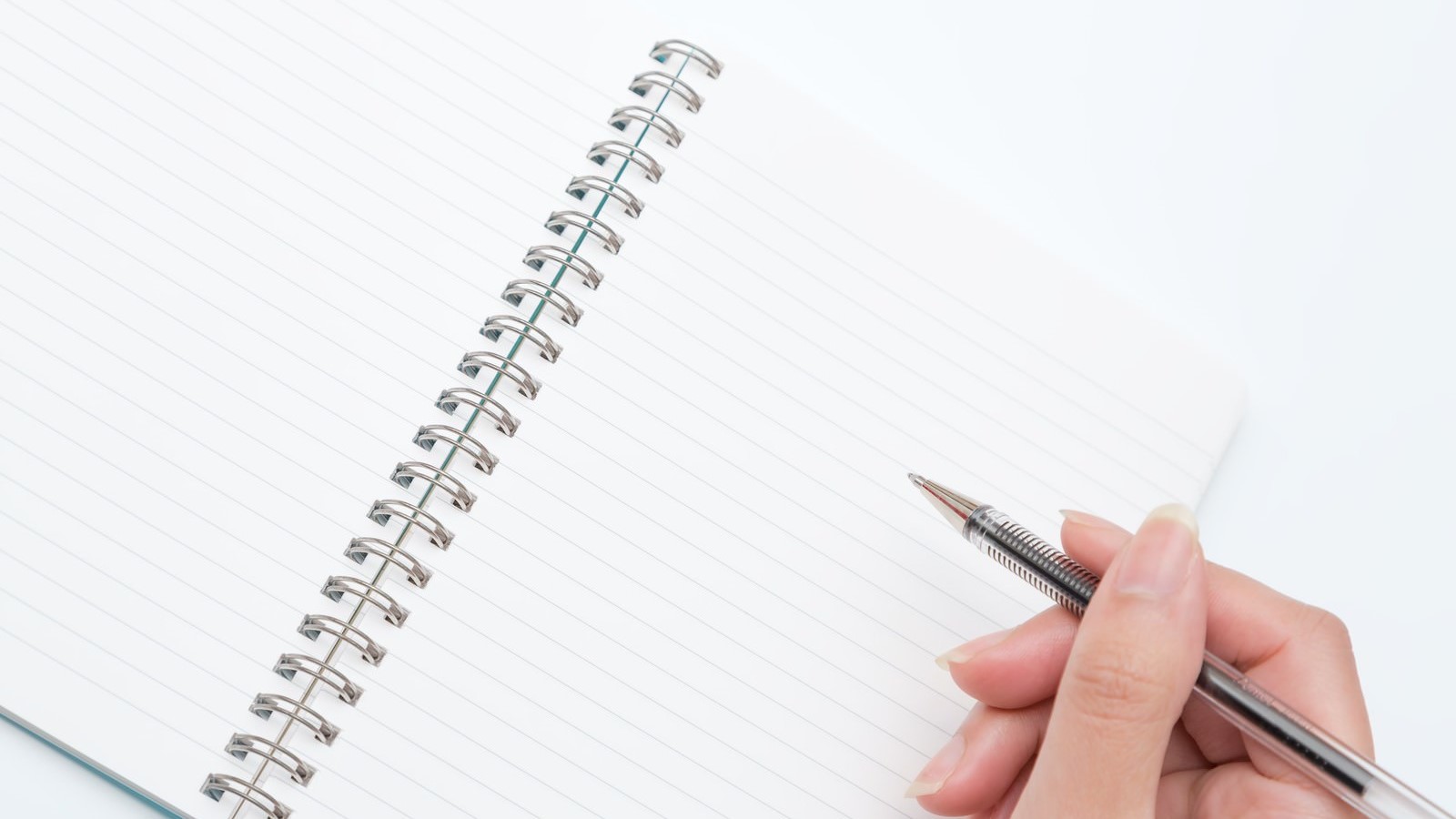
しかし、新法の施行前から既に締結されている借地契約、借家契約(既存の契約)には、新法の定める存続期間や更新などに関する多くの規定が適用されず、「なお従前の例による」とされ、旧法が適用されることになっています(借地借家法附則第5条以下)。
終わりに
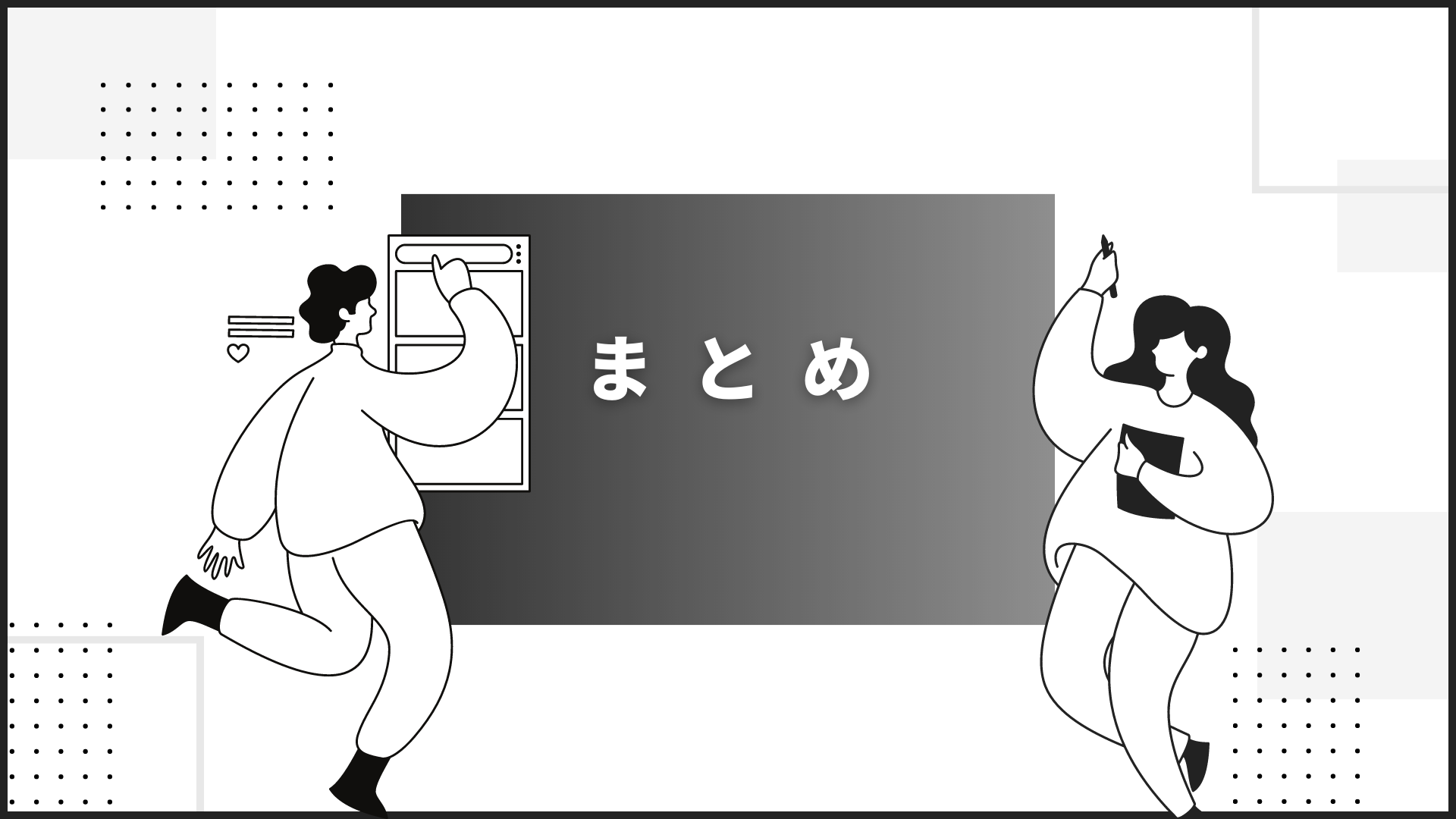
前回は「借家」契約に関する法規制についてまとめましたので、今回の「借地」契約に関する法規制とならべてお読みいただけると理解を深めていただけるでしょう。
今回最初にお話ししましたように、借地借家法で借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことをいいます。
建物所有以外を目的とする土地賃貸借は、借地借家法では借地権に該当しないため、民法に基づいて対応することとなります。
借地借家法では、土地と建物が密接にかかわっており、その時々で法ではどのようにされているか確認し対応するとよいでしょう。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
