
借家権とは、広くは建物の賃借権のことをいいますが、一般的には借地借家法の適用を受ける賃借権のことをいいます。
借地借家法の適用を受ける物件とはどのような物件でしょうか。
建物の一部であってもアパートの1室のように独立性のある場合は借地借家法の適用があります。
間借りの場合は、その部屋が他の部分と区画されており、構造や規模から独立・排他的利用が可能であれば借地借家法の適用があり、その部屋自体に独立性がない場合は借地借家法の適用はありません。
借家権に関して、トラブルになりやすい事項がいくつかあります。
今回は、借家契約の規制の要点について、お話し致します。
借家権の存続期間

借家権の存続期間の定めがある場合
しかし、1年未満の期間を定めた場合は、定期建物賃貸借契約とする場合を除き、後述します「期間の定めのない契約」とみなされます。
期間満了と同時に明け渡しを求めるには、期間満了前1年から6か月前までの間に賃借人に対し予告しなければ更新の拒絶ができず、これをしなければ従前と同一条件で更新されることになります。
また、賃貸人が更新を拒絶するには、「正当の事由」が存在しなければなりません(借地借家法第28条)。
賃借人に不利な特約は無効となります(借地借家法第30条)。
そのため、契約書の条項に「賃貸人の都合によっていつでも解約し、また更新を拒絶することができる」旨の記載をしても、その部分は効力を生じません。
借家権の存続期間の定めがない場合
しかし、そのためには「正当の事由」がなければなりません。
解約の効果は、その解約申入れから6か月を経過したときにはじめて生じます(借地借家法第27条)。
したがって、賃借人は、賃貸人の解約申し入れが正当の事由によるものであっても、6か月間は居住を継続できます。
また、6か月を経過した場合でも、賃借人が立ち退かず、それに対して賃貸人が、遅滞なく異議を述べないときは、6か月前の解約申入れの効力が失われ、改めて解約申し入れをしなければなりません。
期間の定めがない場合は、賃借人もいつでも解約の申し入れをすることができます。
賃借人の解約申入れには、「正当の事由」は不要です。
解約の効果は、申込みから3か月経過したときに生じます(民法第617条第1項)。
借家権の対抗力

そのうえ、借地借家法では、登記がなくても建物の引渡さえあれば第三者に対抗することができるものとして、賃借人を保護しています(借地借家法第31条)。
なお、借家権は対象の建物が滅失すれば消滅します。
目的の建物が存在しなくなるためです。
正当の事由(借家契約の更新拒絶または解約の申入れの要件)

この有無の判断はかなり困難であり、個々のケースについて具体的に決定されなければならず、従来から裁判では、賃貸人、賃借人、双方の建物使用の必要度の比較や賃貸借の解約をすることによって生じます。
双方の利害得失などを比較衡量して、さらに社会公益的見地からも公平に判断したうえで、「正当の事由」の存否が判断されてきました。
しかし、1992年(平成4年)8月より施行された新借地借家法は、その判断基準を明確にしました(借地借家法第28条)。
判断基準は、以下のようにされています。
(1) 建物、賃貸人および賃借人が、建物の使用を必要とする事情
(2) 建物の賃貸借に関する従前の経過
(3) 建物の利用状況および建物の現況
(4) 建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として、または建物の明渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申し出
なお、(1)が基本的な要素であるとされています。
また、(4)はいわゆる立退き料のことです。
「正当の事由」を具備せずに賃貸人が更新拒絶等を行なっても契約終了とはなりません。
賃貸者契約は、期間の定めがない賃貸者契約となることを除き、従前と同一の条件で更新されたものとして取り扱われます。
いわゆる、法定更新となります(借地借家法第26条)。
定期建物賃貸借契約と取壊し予定の借家

定期建物賃貸借契約の要点
この場合、期間を1年未満とすることもできますし、50年を超える契約を締結することもできます(借地借家法第38条第1項、第29条第1項、第2項)。
ただし、この契約を締結しようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ建物の賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了によって賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならず、その説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効となります。
なお、定期借家契約は、その内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)によって行うこともできる旨が「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により改正されました。
また、上記の事前説明も同様に、賃借人の承諾を得れば、電磁的記録によって行うこともできる旨が、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により改正されました。
取壊し予定建物の借家
ただし、この場合も、契約内容を明確にするとともに、脱法的な契約を防止するため、その特約について建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならないとされています。
なお、上記の契約は、その内容を記録した電磁的記録によっても行うことができる旨が「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により改正されました。
造作買取請求権

また、賃借人が、賃貸人より買受けた造作も同様です(借地借家法第33条)。
なお、この規定は、旧法化においては強行規定とされ、造作買取請求をしない旨の特約をしても無効でした。
しかし、1992年(平成4年)8月より施行された新法では、この規定を任意規定とし、造作買取請求権を排除する旨の特約を有効とすることとなりました。
その理由は、旧法化において、例えば、賃借人がエアコンを取り付けようとして賃貸人に同意を求めても、将来これを買い取りたくない賃貸人は同意をしないこととなり、結局賃借人がエアコンを取り付けられないという事態が生じていたためです。
そこで、造作買取請求権を特約で排除することを認め、賃貸人の同意を得やすくしようとされました。
家賃の増減額請求

ただし、一定の期間家賃を増額しないという特約があるときは、その特約に従うものとされ、また定期建物賃貸借契約において家賃の改定にかかる特約(例えば、契約期間内は賃料を定額とし、増額も減額もしない)などがある場合には適用されません(借地借家法第38条第9項)。
家賃をめぐる紛争については、原則として、訴訟を提起する前に調停の申立てをしなければなりません(民事調停法第24条の2)。
これを調停前置主義といいます。
また、当事者が、調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面の合意を調停申立後にした場合には、調停委員会の定める調停条項に拘束されます。
これらは、民事調停法に規定されています。
一時使用目的と終身借家契約

一時使用目的の借家
終身借家契約
賃借人が生きている限り存続し、死亡したときに終了するという意味で、不確定期限付き建物賃貸借であり、かつ、その賃借権については相続権が排除されています(高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条、57条)。
終身借家契約を締結するためには、その契約は公正証書などの書面によって行わなければなりません。
なお、この契約も、その内容を記録した電磁的記録によってされたときは書面によってなされたものとする旨が、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により改正されました。
また、終身借家制度を利用して賃借人になろうとする者は、60歳以上の高齢者でなければなりません。
同居する者も配偶者もしくは60歳以上の親族に限られていますが、配偶者は60歳以上の者には限られません(高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条第1項)。
終身借家契約について、借賃の改定に関わる特約がある場合には、借地借家法第32条の賃料増減額請求権の規定の適用は排除されます(高齢者の居住の安定確保に関する法律第63条)。
参考:高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条(事業の認可及び借地借家法の特例)【e-GOV】
終わりに
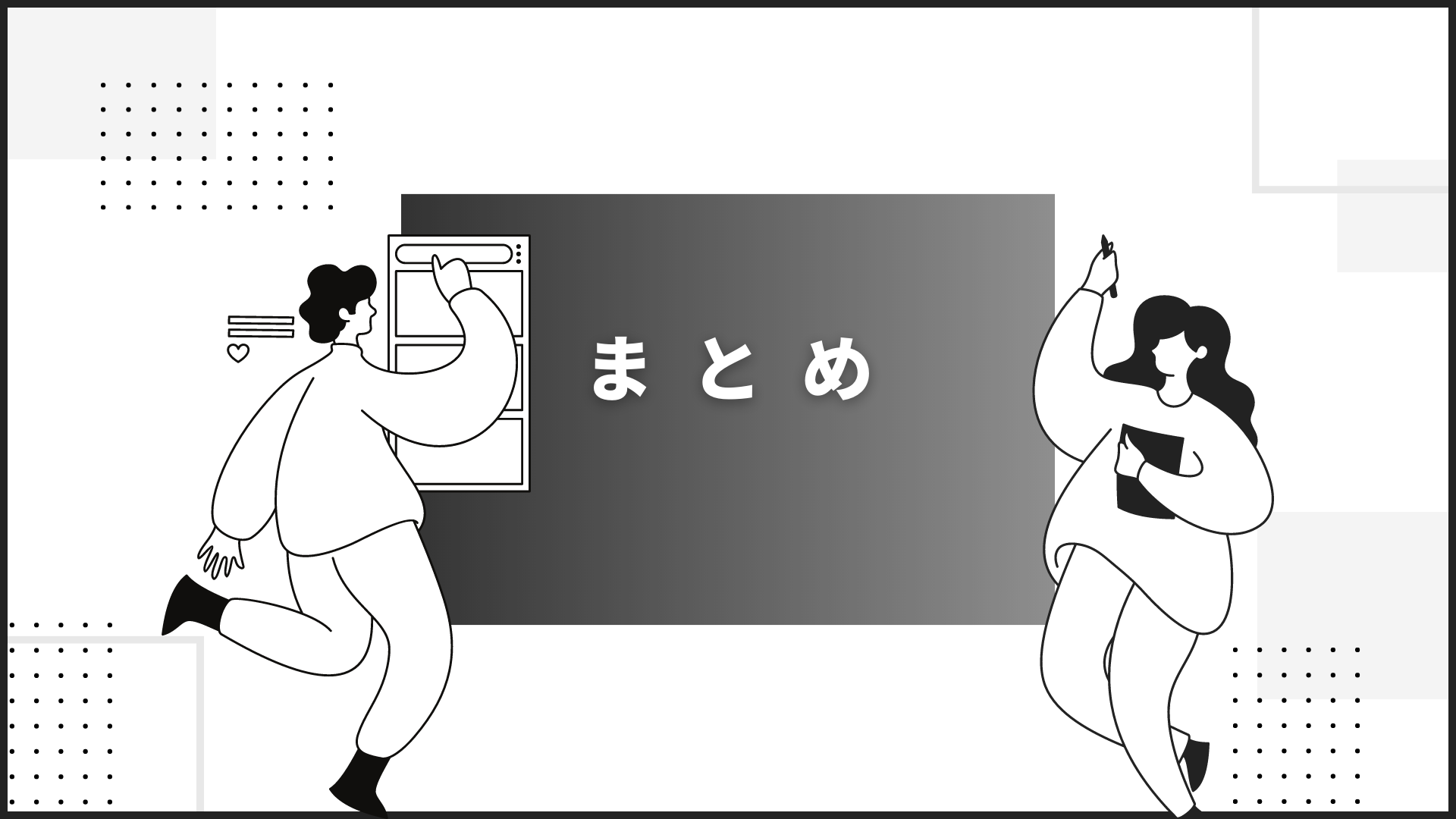
賃貸マンションやアパートなどに借りている人、または貸している人は多く、多くの人にとっての生活基盤となっています。
そのため、賃貸借、特に建物賃貸借は多くの人が関わっており、関わりが多いがためにトラブルも多く発生します。
今回取り上げた中でも「期間の定めがある場合とない場合」や「正当の事由」、「造作買取請求権」、「家賃の増減額」は、実務でもたびたび関わってきます。
既に知っている方も多いトピックかもしれませんが、しっかりと理解し誤った利用をしないように心がけましょう。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
