
高齢化社会の進展に伴い、さまざまな経済活動において高齢者との取引に関する問題や紛争が増えています。
不動産においても、当事者としての意思能力の問題や、賃借人の孤独死などがクローズアップされています。
2020年(令和2年)4月1日に改正された民法では「法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする」と明文化されています。
最近増加傾向にある認知症の心配がある場合は、特に慎重な対応が求められます。
日によって症状に差があったり、過去の記憶は比較的明確であったりするなど、短時間の面談では意思能力に問題があるかどうか判別できないケースがあります。
当事者のプライバシーとの兼ね合いもあって、調査や確認は容易ではない面もあるが、重要な問題として実施しなければなりません。
今回は、認知症によって売買契約が無効となった事例について、お話し致します。
認知症により売買契約が無効に

なお、この事例には「第1の売買契約」と「第2の売買契約」があります。
善意の第三者である「第2の売買契約」の買主が保護されるべきかという点においても、参考になります。
紛争の内容
2008年(平成20年)3月24日、売主Xと買主Y1との間で、土地付き建物の売買契約(第1の売買)が締結され。3月26日に所有権移転登記がなされた。
Xは、契約時に、本件不動産を2008年(平成20年)6月末日までに明け渡す旨の明渡承諾書をY1に差し入れた。
Xは第1の売買当時、本件建物に居住しており、老人保健施設や介護施設などへの具体的な入居の予定はなかった。
司法書士Aは、2008年(平成20年)3月23日にX宅を訪れた。
約20分間、Xの娘Bの元夫であるCによる立会いのもと、第1売買についての所有権移転登記手続の委任状、登記原因証書への署名・押印を求めた。
また、登記権利証紛失により必要となる本人確認のため、年金手帳や健康保険証などの身分証明書の交付を受け、本件不動産の取得経過なども聴取した。
この第1の売買は、 Cは自己の事業資金を得るため、Xが認知症であることを利用し、X所有の本件不動産を担保にしてY1から300万円を借り入れることを企て、Xには本件不動産を売却してその売買代金を取得するとして勧めたものであった。
2008年(平成20年)年6月26日、Y1が売主となって、Y2との間で売買契約(第2の売買)がなされ、同日所有権移転登記がなされた。
Y2から本件不動産の売却を依頼された媒介業者Dは、X宅を訪れ明渡しを求めたが、Xは第1の売買による売買代金を受領していないなどとして、所有権の移転を否定した。
一方、Xの在宅介護ノートによると、2008年(平成20年)3月頃、正常とは思われないXの言動が記録されていた。
またXには、次のような事実があった。
医師Eによる2007年(平成19年)8月2日付主治医意見書および2008年(平成20年)8月26日付診断書によると、Xは、2007年(平成19年)4月11日に初診を受けて、特定不能の認知症および器質性精神病と診断された。
2007年(平成19年)8月2日には、短期記憶に問題があり日常の意思決定を行うための認知能力や意思の伝達能力がなく、妄想や暴言などの認知症の周辺症状も認められているとされている。
医師Fによる診断や回答書によると、Xは、2007年(平成19年)10月25日以降定期的に診察を受けていたが、認知症が徐々に進行し、2008年(平成20年)5月12日の診断書作成時点において幻覚妄想、失見当識があり、正当な判断ができない状況でアルツハイマー型認知症と診断された。
自己の財産を管理、処分することができない後見相当の判断能力との判定意見がなされており、2008年(平成20年)3月27日に診察した際にも同様の状態にあったとされている。
2008年(平成20年)8月8日、Xについて、東京家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てがなされた。
2008年(平成20年)8月20日に、成年後見開始とXの法定代理人成年後見人をZとする選任の審判がなされた。
法定代理人成年後見人Zは、第1の売買当時、Xには意思能力がなかったので第1の売買は無効であり、よって、第2の売買も無効であるとして、登記名義人であるY2に対し、登記抹消手続きを求めた。
これに対しY2は、Xには判断能力があったとし、また、Y2は善意の第三者であると主張してこれを拒否した。
そこで、X(Z)は提訴した。
各当事者の言い分と本事例の問題点
1. 第1の売買の締結前後における司法書士AとXとのやりとりや、Y2から物件の売却を依頼されたDへのXの応対から考えて、Xには判断能力の低下はうかがわれないと考える。
2. 私は善意の第三者であるから、たとえ第一の売買が無効であっても、不動産の取得は有効である。
【Xの法定代理人(Z)の言い分】
第1の売買当時、Xには意思能力がなかったので、第1の売買は無効であり、よって第2の売買も無効である。
【本事例の問題点】
1. 司法書士との受け答えに不自然さがなく、その後、立退きを求めた相手に対する受け答えもしっかりしていたにもかかわらず、売買契約当時、意思能力がなかったといえるか。
2. 転売によって、不動産を購入した善意の第三者でも、所有権移転登記の抹消登記に応じなければならないか。
本事例の結末
第1の売買当時のXの意思能力について
・第1の売買の際、Xはアルツハイマー型認知症に罹患していた。
・本件不動産の売却に伴って、自己が居住を失い、代わりの居住先が必要になるという極めて容易に予想できる問題点にすら思い至らないほど、既にその症状が相当程度進行していた。
・自己の財産の処分や管理を適切に行うに足りる判断能力を、欠くに至っていたものと認める。
・Y2は、第1の売買の締結前後における、Xの司法書士Aや媒介業者Dとの応対からは判断能力の低下はうかがわれないと主張。
・しかし、主に登記手続に必要な限度で第1の売買に関与したに過ぎないAが、短時間で、かつ第1の売買を主導したCが立ち会った場でXと接触した際にXの意思能力に疑問を感じなかったとしても、その認識を重要視することは相当ではない。
・また、Dとの会話において、売買代金を取得する目的を秘して第1の売買の締結を勧めたCに騙されたとの認識をXが示したとしても、それ自体は比較的単純な事柄である。
・居住用不動産の売買という不自然な行動に照らしてみても、かかる事情をもってXの判断能力が保たれていたと認めるのは相当ではない。
よって、第1の売買の際、Xは意思能力を欠いていたというべきである。
第1の売買は無効と認めるのが相当であるから、Y1は本件不動産の所有権をXから取得できない。
また、Y2も無権利者であるY1から、本件不動産の所有権を承継取得することはできないと認めるのが相当である。
Y2は善意の第三者として保護されるか
・Xは、第1の売買の当時、認知症により意思能力を欠いていたものと認められる。
・第1の売買は、Xが意思能力を欠く状態であることを利用したCが主導して締結されたものというべきである。
・そのため、第1の売買により、Y1が本件不動産の所有権移転登記を得たとの外観が作出されるにつき、Xには何ら責められるべき事情は認められない。
よって、Y2の善意・悪意について判断するまでもなく、Y2は民法第94条第2項の善意の第三者として保護されるべきものと認めることはできず、この点のY2の主張には理由がない。
本事例からの考察
意思能力を欠くものが行った法律行為に関しては、2020年(令和2年)4月1日より前の改正前民法には明文の規定はありませんが、当然に無効と考えられていました。
なお、この点に関し、改正民法では「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする(民法第3条の2)。」と明文化されています。
取引当事者の意思能力や、真の権利者であるか否かの確認は、基本的な行為です。
高齢化社会の進展に伴って、経済活動において高齢者との取引に関する問題や紛争が増えています。
不動産においても、当事者としての意思能力の問題や賃借人の孤独死などがクローズアップされています。
最近増加の傾向にある認知症は、日によって症状に差があったり、過去の記憶は比較的明確であったりするなど、短時間の面談では意思能力に問題があるかどうか判別できないケースがあります。
金融商品に関しては、一定の高齢者との取引について、親族を同席させることによって、本人の意思確認やリスク説明などの義務を補完するという例も見られます。
しかし、高額となる不動産取引に関しては、本事例にも見られるように、推定相続人などの親族間の争い(将来の遺産分けに起因する争い)などが絡んで、不動産取引に関与していない他の親族が無効などを申し立てる場合があります。
単に親族が取引に同席関与しているということだけでは、紛争などを防止する手段にならないことがあり得ます。
また、当事者のプライバシーの問題もあります。
調査や確認は容易ではありませんが、重要な問題と考えなければなりません。
調査などの実務上の留意点としては、次のようなものが考えられます。
1. 担当者と上司など、司法書士も含めて必ず複数の人間が、別の時間に面談する。
2. 聞き取り調査において、さりげなく次のような事項を質問してみる。
・売買等の目的、理由。売却代金の使いみちや購入代金、費用の調達方法。
・自宅売却の場合には、次の転居先確保の目途。
・本人の年齢や千支。面談日の朝や昼の食事のメニューなど。
※論理的な回答がなかったり、同席した親族が回答を誘導したりするような場合は、さらに慎重な確認が必要です。
当事者の意思能力に疑いがある場合は、民法が定める成年後見制度の利用を検討することが基本となります。
ただし、この制度を利用するためには、家庭裁判所による後見開始の審判と成年後見人の選任が必要です。
また、成年後見人が、成年被後見人の居住用不動産の売却などの処分を行う際には、家庭裁判所の許可を要します。
手続きに時間を要するため、余裕を持って事前準備や取引の段取りを行わなければなりません。
なお、本事例では、売主の認知症を理由とする意思表示(売買契約)の無効が認められましたが、ケースによっては有効とされる場合も考えられます。
いずれにしても、高齢者との取引には慎重な対応が求められます。
さらに、本事例は、第1の売買が有効に成立しているか、第2の売買の売主が真の所有者であるかが争われたケースともいえます。
特に短期売買では、現在の登記名義人が、前所有者から、適正に物件を取得したかどうかの調査を入念に行うべきでしょう。
元の売買契約が無効であるから以後の取引も無効であるとした本判決は、調査や確認について考え直す事例と言えるでしょう。
終わりに
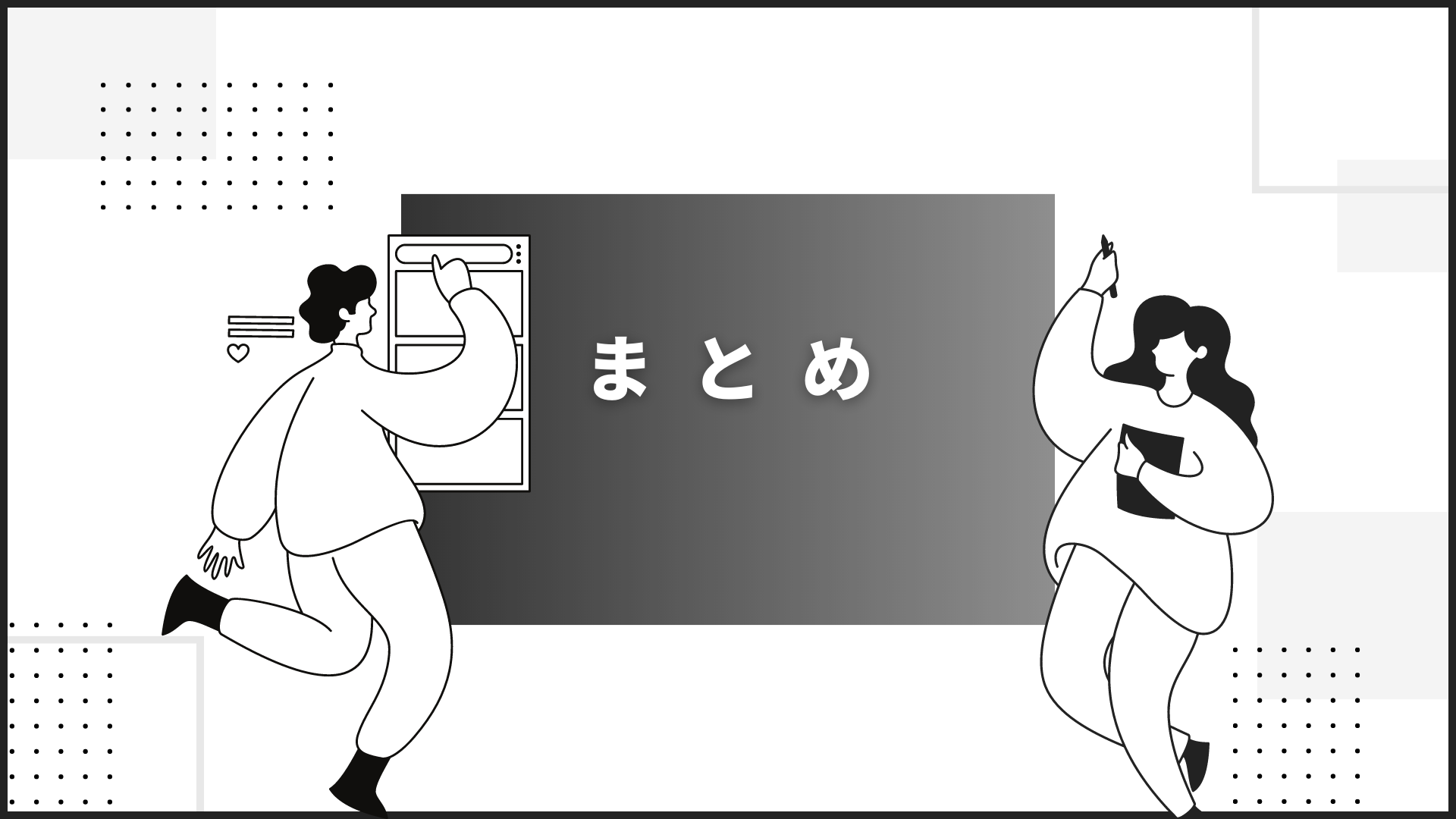
不動産取引に関しては、本事例で紹介したように、親族間による将来の遺産分けに起因する争いなどが絡んで、不動産取引に関与していない他の親族が無効などを申し立てる場合があります。
また、当事者のプライバシーの問題もあります。
そのため、調査や確認は容易ではありません。
しかし、司法書士が立ち会った点について、短時間であり、登記手続に必要な限度で関与したに過ぎず、意思能力に疑問を感じなかったとしても重要視できないとされた点は軽視できません。
高齢者との取引には慎重な対応が求められます。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
