
2020年(令和2年)4月1日に改正民法が施行され、債権関係について改正されました。
賃貸借契約にて、連帯保証人をつける場合、「極度額」という連帯保証人の責任の上限額を定めなければならないことになりました。
つまり、「極度額」の定めがなければ、連帯保証は無効になります。
連帯保証については、賃貸実務でも問題になることがあります。
賃料滞納が発生したときに連絡が取りにくかったり、場合によっては連帯保証している認識がないような人もいます。
賃貸人もしくは管理業者にとって、連帯保証人には賃借人ほど連絡を取る機会がないことが、原因の1つでしょう。
住居用の賃貸借契約では、契約期間が2年間程度設定されていることが多いでしょう。
普通借家契約の場合、正当事由がなければ賃貸人から契約終了をさせることができません。
そのため、賃借人が賃貸借を継続する意思であれば、法定更新であっても合意更新であっても、一般的には契約が更新されます。
ここで先ほどの連帯保証人の問題がでてきます。
賃貸借契約更新時に、連帯保証人にその意思確認をしておく必要はないでしょうか。
今回は、賃貸借契約更新後の連帯保証人の責任について、お話し致します。
更新後の賃貸借契約における連帯保証人の責任
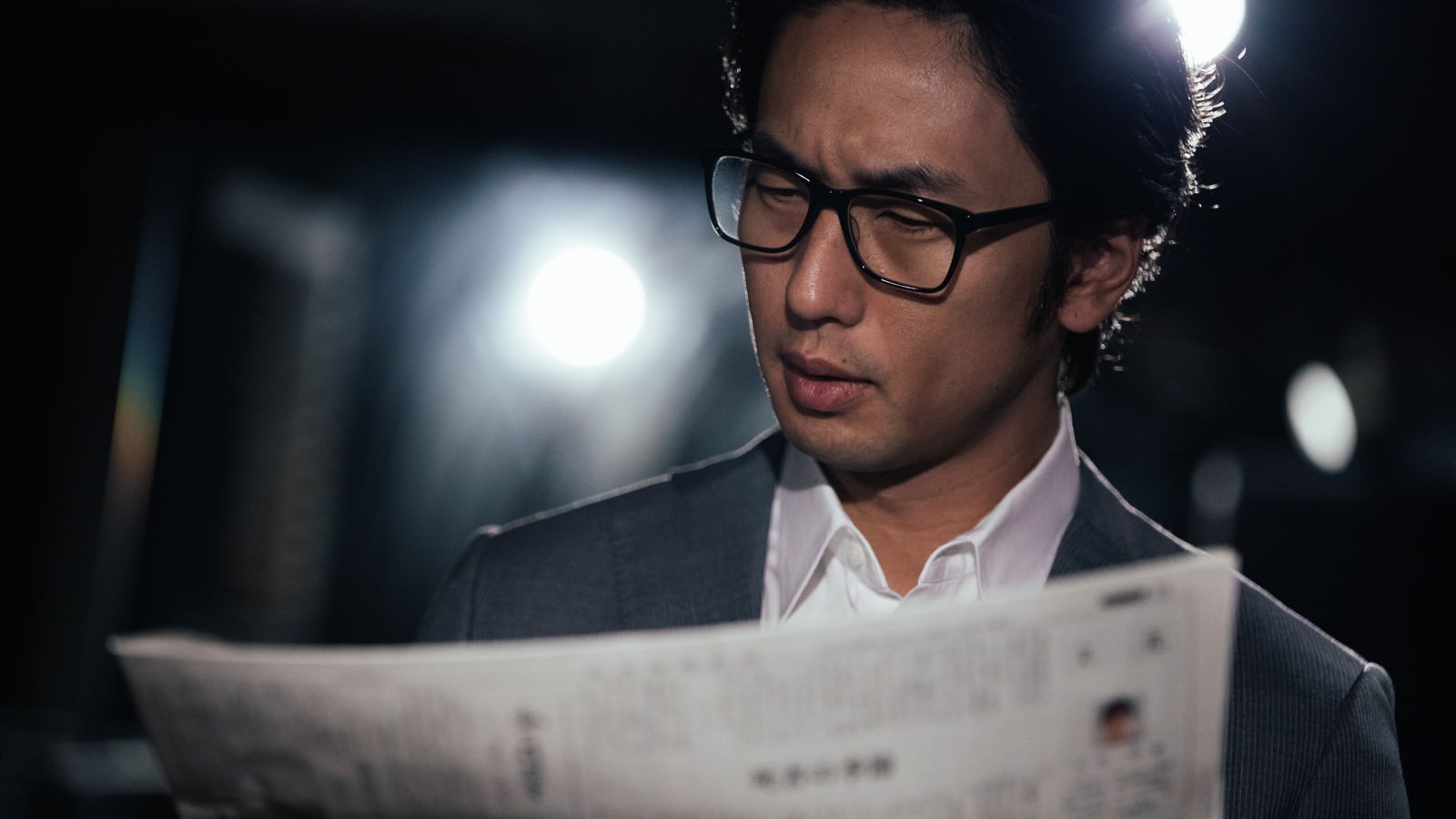
過去に、賃貸借契約更新後の賃借人の賃料不払いについて、連帯保証人として責任を負うことが認められた判例があります。
この判例を参考に参考にお話しします。
紛争の内容
1. 賃貸人(X)は賃借人(Y1)との間で、1985年(昭和60年)5月31日、賃貸人(X)が所有するマンションの1室を、契約期間1985年(昭和60年)6月1日から1987年(昭和62年)5月31日までの2年間、賃料月額26万円の約定で賃貸する契約を締結した。
2. その後、連帯保証人(Y2、借主Y1の実兄)は、賃貸人(X)との間で、本件賃貸借契約に基づき賃借人(Y1)が賃貸人(X)に対して負担する債務につき連帯保証した。
3. その後、本件賃貸借契約は2年ごとに3回にわたり合意更新したが、その更新に際して、賃貸人(X)は、連帯保証人(Y2)に対して、保証意思確認の問い合わせをしたことはなかった。
また、連帯保証人(Y2)は、引き続き連帯保証人になることを明示的に了承したこともなかった。
4. なお、2度目の更新において、賃料は月額31万円に、3度目の更新において、月額33万円に改定されていた。
5. ところが、2度目の更新後から、次第に賃借人(Y1)の賃料滞納が始まり、3度目の更新の1991年(平成3年)6月以降はほとんど賃料の支払がされない状態となった。
そこで、賃貸人(X)は、賃借人(Y1)に対して、1992年(平成4年)7月に本件賃貸借契約の更新を拒絶する旨通知し、1993年(平成5年)6月には、連帯保証人(Y2)に対して、賃借人の賃料不払いを通知した。
賃借人(Y1)は、1993年(平成5年)6月18日にマンションから退去した。
6. 以上の経緯のもと、賃貸人(X)は、賃借人(Y1)の賃料不払いによる滞納賃料853万円余の支払いを連帯保証人(Y2)に求める訴訟を起こした。
各当事者の言い分と本事例の問題点
賃貸借契約の連帯保証人(Y2)は、賃借人(Y1)が建物を明け渡すまでの一切の金銭債務の履行について、賃借人(Y1)と共に責任を負う。
更新契約に署名押印したか否かは関係ない。
【連帯保証人(Y2)の言い分】
1. 更新前の契約と更新後の契約との間には法的同一性はない。
更新前の契約に付された敷金以外の担保は、特別の事情がない限り、更新後の契約には及ばないはずである。
当初の契約にしか署名・押印せず、更新に際しては、連帯保証人(Y2)に対して保証意思の確認の問い合わせがされた事も、引き続き保証人になることを明示的に了承した事もなかった。
更新後の賃料不払いについて責任を負う必要はない。
2. 仮に連帯保証人(Y2)が更新後の賃料不払いについて責任を負わなければならないとしても、賃貸人(X)は、長期にわたり賃借人(Y1)の賃料不払いを放置して、契約解除や連帯保証人への連絡もせず、未払い賃料額を 853万8,000円に増大させた。
連帯保証人(Y2)への請求は信義則に反する。
【本事例の問題点】
当初の契約に署名押印した連帯保証人(Y2)は、賃借人(Y1)が建物を明け渡すまでの一切の金銭債務について、責任を負わなければならないかどうか。
本事例の結末
これに対し、最高裁判所は、二審の大阪高裁の判決を支持して、次のように判決し、賃貸人(X)から連帯保証人(Y2)に対する滞納賃料の請求853万円余を認めました。
【判決の内容】
1. 建物の賃貸借は、一時使用のための賃貸借を除き、期間の定めの有無にかかわらず、本来相当の長期間にわたる存続が予定された継続的な契約関係である。
2. 期間の定めのある建物の賃貸借においても、賃貸人は、自ら建物を使用する必要があるなどの正当事由がなければ、更新を拒絶することができず、賃借人が希望する限り、更新により賃貸借関係を継続するのが普通であるから、賃借人のために連帯保証人になろうとする者も、このような賃貸借関係の継続は当然予測できる。
3. 保証における主たる債務が定期的かつ金額の確定した賃料債務を中心とするものであって、連帯保証人の予期しないような保証責任が一挙に発生することはないのが一般であるから、賃貸借の期間が満了した後における保証責任について特別の定めがなされていない場合であっても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃貸借から生じる債務についても保証の責めを負う趣旨で保証契約をしたものと解するのは、当事者の通常の合理的意思に合致する。
4. ただし、賃借人が継続的に賃料の支払を怠っているにもかかわらず、賃貸人が連帯保証人に連絡するようなこともなく、いたずらに契約を更新させているなどの場合に保証債務の履行を請求することが信義則に反するとして否定されることもあり得る。
5. 本件の事実関係では、特段の事情がうかがわれないから、本件保証契約の効力は、更新後の賃貸借にも及び、賃貸人(X)が連帯保証人(Y2)に対し保証債務の履行を請求することが信義則に反するという事実もないから、賃貸人(X)の請求は認められる。
本事例からの考察
宅建業者や賃貸人は、契約当初の段階で印鑑証明書付で書類を徴求し、連帯保証人の意思をきちんと確認するなど行い有効な連帯保証契約を締結するように心がけることが大切です。
実際に家賃滞納などでいざトラブルになったときに、契約書の賃借人の署名と連帯保証人の署名が同じで、印鑑も三文判が押印されているものがあります。
このような場合に連帯保証人に不払い賃料を請求しても、「賃借人が勝手にやったことなので、私は知らない」と言われることがあります。
また、連帯保証人の中には、「最初の2年間だけ保証したもので、その後の更新契約に署名押印していない以上責任はない」と考えている場合もあるかもしれません。
賃貸借契約を締結する際には、契約書あるいは連帯保証人引受書に、「連帯保証人は、賃借人と連帯して本契約から生じる一切の債務を負担するものとします。本契約が合意更新あるいは法定更新された場合も同様とします」というような文言で連帯保証人の責任の範囲を明示しておくとよいでしょう。
さらに、前述のような書類を徴求することや文言の記載を確実に励行することは、連帯保証人になろうとする者にとっても、不測の損害を与えない結果になるでしょうし、連帯保証人に対する説得材料にもなります。
なお、 2005年(平成17年)4月1日施行の民法改正により、保証契約は書面で行わなければ無効になります。
その意味からも、賃借人が建物を明け渡すまでの責任を明記する書面は意義があるでしょう。
ただし、本判決は、更新がある普通建物賃貸借契約に関するものであって、更新がない定期借家契約には適用されません。
「定期借家契約」は、再契約をした場合でも全く新規の契約なので、新たな連帯保証人の署名・押印を徴求しなければなりません。
改正民法による影響
ただし、民法改正によって、賃貸借契約の保証人が個人の場合には、保証契約に責任を負う上限額である極度額を文書(または電磁的記録)で定める必要があります。
極度額の定めがなければ、保証契約そのものが無効とされてしまうことになりました。
賃貸借契約の保証のように、一定の取引(賃貸借契約)から生じる不特定の債務を将来にわたって保証する保証契約を根保証契約といいます。
この保証契約について、極度額を定めなければ、個人の保証人が予想を超える過大な責任を負う恐れがあります。
そのため、極度額を定めることによって、個人の保証人を保護しようというのが改正の趣旨です。
この極度額に関する規定は強行規定であるため、賃貸借契約の保証人が個人の場合に極度額を定めなければ保証契約が無効となります。
滞納賃料等が発生しても、一切保証人に責任を追及できなくなります。
根保証契約に関する民法の改正は、2020年(令和2年)4月1日から施行されました。
同日以降に新規に個人の連帯保証人を立てる場合には、極度額を定めなければなりません。
これに対し、2020年(令和2年)4月1日より前に締結された賃貸借契約について、2020年(令和2年)4月1日以後に賃貸者契約を更新する場合、当初の賃貸者契約の連帯保証人(個人)について、更新時に契約書(もしくは連帯保証人引受書)を作成し直して、極度額を定める必要はありません。
本判決が判示しているように、当初の賃貸借契約の連帯保証人の責任は更新後も存続するため、連帯保証人から署名・押印をもらい直さなくても、民法改正前の責任の上限額のない保証契約が有効に存続します。
他方で、2020年(令和2年)4月1日より前に締結された賃貸者契約について、2020年(令和2年)4月1日以後の合意更新時に、新たな連帯保証契約が締結され、または合意によって新たな連帯保証確約書が作成された(保証人が保証条件のある契約書に署名・押印したり、新たな保証確定書に署名・押印した)場合には、この保証契約については極度額を定めなければならないと法務省担当官の見解があります(参照「一問一答 民法(債権関係)改正 商事法務Q205」)。
また、本判決は、実務においても重要な示唆が与えられています。
「賃借人が継続的に賃料の支払を怠っているにもかかわらず、賃貸人が連帯保証人に連絡することもなく、いたずらに契約を更新させているなどの場合に、保証債務の履行を請求することが信義則に反するとして否定されることもあり得る」と明言されています。
長期間、連帯保証人に通知しないような場合には、公平の観点から連帯保証人の責任の全部あるいは一部が否定される可能性もあるということです。
賃料不払い状況はこまめに連帯保証人に連絡し、督促することを心がけることが望ましいでしょう。
そのことが、賃借人の、賃料長期不払いを回避することにもつながります。
終わりに
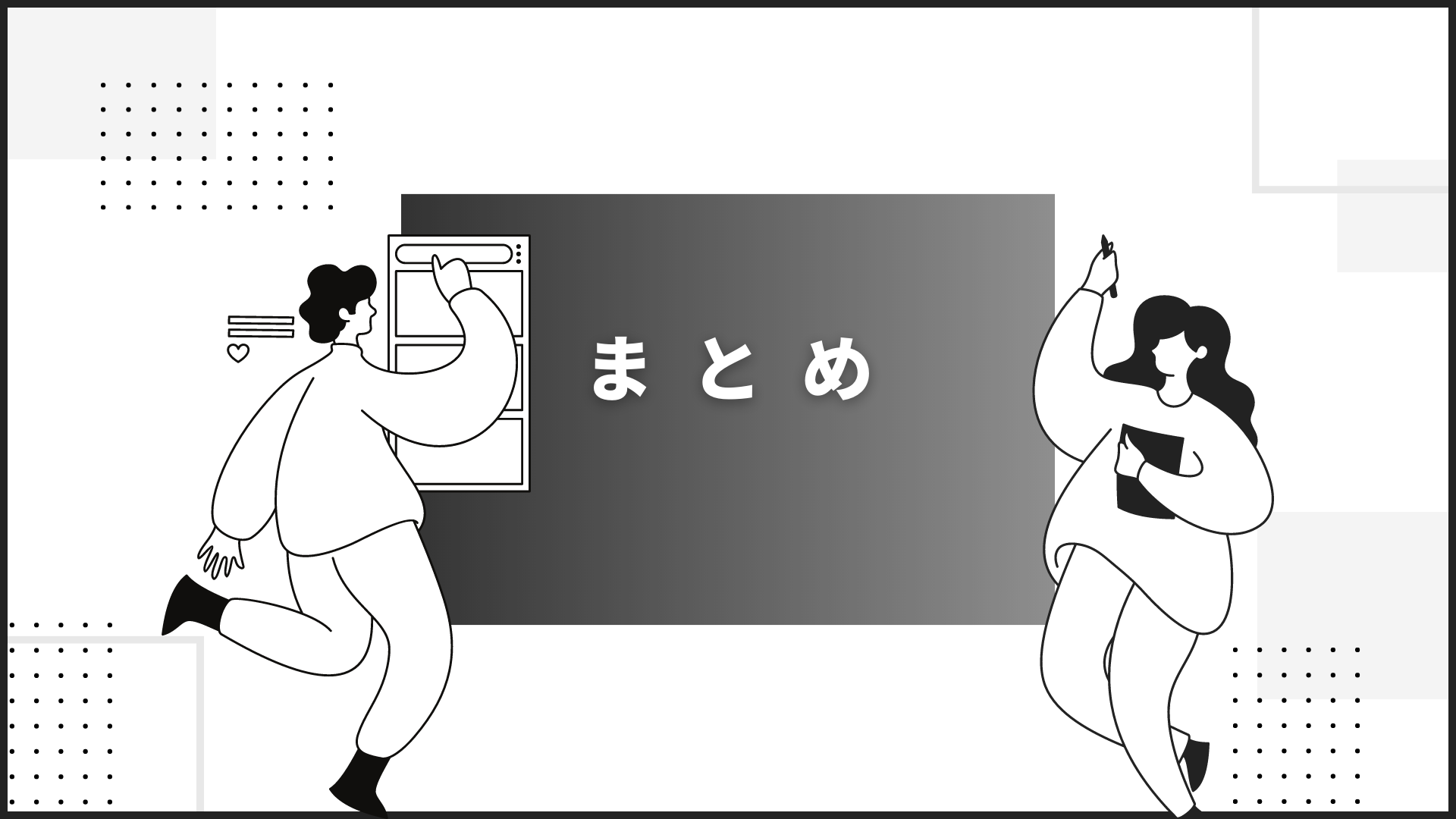
前述しました「賃貸借契約の連帯保証人の保証責任は、更新後の賃借人の賃料不払いについて及ぶ」という判決の意義は大変大きなものでしょう。
ただし、「賃借人が継続的に賃料の支払を怠っているにもかかわらず、賃貸人が連帯保証人に連絡することもなく、いたずらに契約を更新させているなどの場合に、保証債務の履行を請求することが信義則に反するとして否定されることもあり得る」とも明言されています。
賃貸借契約を行うときには、賃貸人や連帯保証人などの当事者は、その重要性をしっかり認識したうえで手続きを行わなければなりません。
また、賃料不払いが生じたときには、連帯保証人にもこまめに連絡し督促を行うべきです。
ほとんどの賃貸借は、保証人ではなく連帯保証人として契約を締結していることでしょう。
このこともしっかりと認識したうえで、実務を行えば良いでしょう。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
