
区分所有マンションに関係する法として、「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」があります。
この区分所有法に基づいて、国土交通省が作成したマンション管理規約の指針となる、マンション標準管理規約があります。
マンション標準管理規約をもとに、各マンションの管理組合によって管理規約が作成されます。
管理規約には様々なルールが定められており、賃貸を想定したルールも定められています。
区分所有者だけではなく、賃借人にも影響を及ぼします。
それにも関わらず、管理規約が軽視されているケースが散見されます。
管理規約の確認をせずに賃貸を行うと、大きなトラブルが生じることがあります。
今回は、区分所有マンションの管理規約の説明義務について、お話し致します。
マンション管理規約の説明義務

過去に、マンション管理規約の説明を怠ったことにより、媒介業者と宅地建物取引士、そして賃貸人に対し損害賠償の支払いが認められた判例があります。
この判例を参考に参考にお話しします。
紛争の内容
1. 2018年(平成30年)1月16日、賃借人(X)は、媒介業者(Y1)の媒介のもと、賃貸人(Y3・非宅地建物取引業者)から賃貸人(Y3)が所有する5階建てマンションの1階にある店舗区画を賃借した。
2. 本件マンションの管理規約第16条は、本件マンションの使用については別に使用細則等を定めるものとすると規定している。
これを受けて定められた使用細則(管理規約と併せて以下「本件管理規約等」という)では、「店舗部分を臭気を発生する業種またはおびただしい煙を発生する業種などの営業の用に供してはならない」こと、「同規定に抵触する恐れのある業種を営業しようとする場合は事前に管理組合に届け出、承認を得る必要がある」ことなどの定めがあった。
しかし、そうした事実は賃借人(X)に知らされなかった。
3. 賃貸人(Y3)は、本件マンションの隣接建物も所有しており、過去に媒介業者(Y1)の媒介によって隣接建物で焼鳥店を営むためにこれを賃貸人(Y3)から賃借した事業者がいた。
しかし、煙が多く出るとして営業が認められず、和食店での出店に切り替えたということがあった。
4. 本件賃貸借契約締結後、賃借人(X)が本件区画で焼肉店を営業するための内装工事を始めたところ、本件マンションの管理組合は、賃借人(X)による焼肉店の営業は本件規約等に違反するとして、賃借人(X)に対し、内装工事を即刻中止するよう申し入れを行った。
また、本件マンションの管理組合は、賃借人(X)による工事続行禁止などを求める仮処分を裁判所に申し立てるなどした。
5. そのため、賃借人(X)は、本件価格での焼肉店営業は事実上不可能であると判断した。
2018年(平成30年)4月25日、賃貸人(Y3)の債務不履行を理由に本件賃貸借契約を解除し、本件区画を賃貸人(Y3)に明け渡した。
6. その後、賃借人(X)は、媒介業者(Y1)並びに媒介業者の代表者(Y2)および賃貸人(Y3)を被告として、店舗撤退により被った損害の賠償を求める訴訟を提起した。
各当事者の言い分と本事例の問題点
本件区画で焼肉店を営業できないことについて、媒介業者(Y1)、媒介業者の代表者(Y2)、賃貸人(Y3)には説明義務違反がある。
【媒介業者(Y1)の言い分】
媒介業者(Y1)は、賃借人(X)が飲食店を開業することは聞いていたが、焼肉店を経営するとは聞いておらず、これを前提に本件賃貸借契約を締結するとは認識していなかった。
【本事例の問題点】
媒介業者(Y1)、媒介業者の代表者(Y2)、賃貸人(Y3)には説明義務違反があるか。
本事例の結末
1. 媒介業者(Y1)および媒介業者の代表者(Y2)は、本件賃貸借契約の締結時において、賃借人(X)が本件区画で焼肉店を出店するために本件賃貸借契約を締結することを知っていた。
また、本件管理規約等などの具体的な内容を知っていたか否かは定かではないものの、隣接建物における焼肉屋の出店時に煙が多く出るとして認められなかったことを認識しており、同様に多くの煙が出ることが想定される焼肉店を本件区画に出店しようとした場合、出店できない可能性が高いことを認識していた。
2. 媒介業者の代表者(Y2)は、宅地建物取引士の資格を持つ者として、上記「1」のような情報が、焼肉店出店のため本件賃貸借契約を締結しようとしていた賃借人(X)にとって極めて重要な情報であることは容易に理解できたはずである。
ところが、媒介業者の代表者(Y2)は、借主であった賃借人(X)にその点を説明せず、これによって賃借人(X)は本件区画に焼肉店を出店することは十分に可能であるとの認識のもと、本件賃貸借契約を締結したものである。
そのため、媒介業者の代表者(Y2)には説明義務違反があり、これは不法行為にあたる。
3. 賃貸人(Y3)は、賃借人(X)が焼肉店出店を目的としていたこと、本件管理規約等などの具体的な内容を知っていたか否かは定かではないものの、隣接建物における焼肉屋の出店時に煙が多く出るとして認められなかったことを認識しており、同様に多くの煙が出ることが想定される焼肉店を本件区画に出店しようとした場合、出店できない可能性が高いことを認識していた。
本件建物の賃貸人(Y3)は、不動産賃貸取引の専門家であるとは認められないから、媒介業者(Y1)ないし媒介業者の代表者(Y2)に課されるような、高度の注意義務を負うものではない。
しかし、賃貸人(Y3)は所有する隣接建物において焼鳥屋の出店が認められず業態を変更して出店したことがあり、本件マンションにおいては多くの煙が出る業態の飲食店が許容されない可能性が高いことを認識していたことなどから、本件賃貸借契約の締結に当たっては、多くの煙が出る業態である焼肉店の出店が認められない可能性が高いことを、自らあるいは媒介業者を介して賃借人(X)に説明する義務を負っていた。
賃貸人(Y3)は、本件賃貸借契約の締結段階における信義則上の説明義務に違反し、不法行為責任を負うというべきである。
4. 法人としての媒介業者(Y1)についても、不動産媒介業者として説明義務を尽くさなかったものとして、不法行為責任を負うものである。
本事例からの考察
媒介業者は、区分所有建物について賃貸媒介を行うときには、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」について、宅地建物取引士をして賃借の相手方に説明させる義務を負います。
また、業法の解釈・運用の考え方によれば、上記にいう「規約の定め」とは、事業用としての利用禁止のほか、ペット飼育やピアノ禁止などもこれに該当するとされています。
実務上、そうした専用部分における利用制限を看過して賃貸借契約を締結してしまい、事後的にトラブルになるケースが散見されます。
本裁判例においては、媒介業者および宅地建物取引士が賃借人の利用目的を知っていたことや、過去に隣接建物で同様のトラブルがあったことも踏まえて説明義務違反が認められているが、そうした事情がなくとも媒介業者および宅地建物取引士としては、賃貸人から管理規約等を取り付けて、賃借人の賃借目的が阻害されるような規定がないか確認したり、管理組合に賃借人の賃借目的を伝えてその可否お問い合わせたりするなどの対応が求められます。
賃貸人にも、媒介業者に説明義務があることを踏まえ、管理規約等の貸し出しに協力したり、賃借人の賃借目的が阻害されるような規定がないか、管理組合に賃借人の賃借目的を伝えてその可否を確認するといったが求められます。
また近頃、建築基準法、消防法などの制限によって、借主の目的に使用できなかったというトラブル例がよく見られます。
宅建業者は、賃借人に対し、建築の専門家に目的使用ができるかの確認を行っておく必要がある旨のアドバイスをしておくことが望ましいでしょう。
終わりに
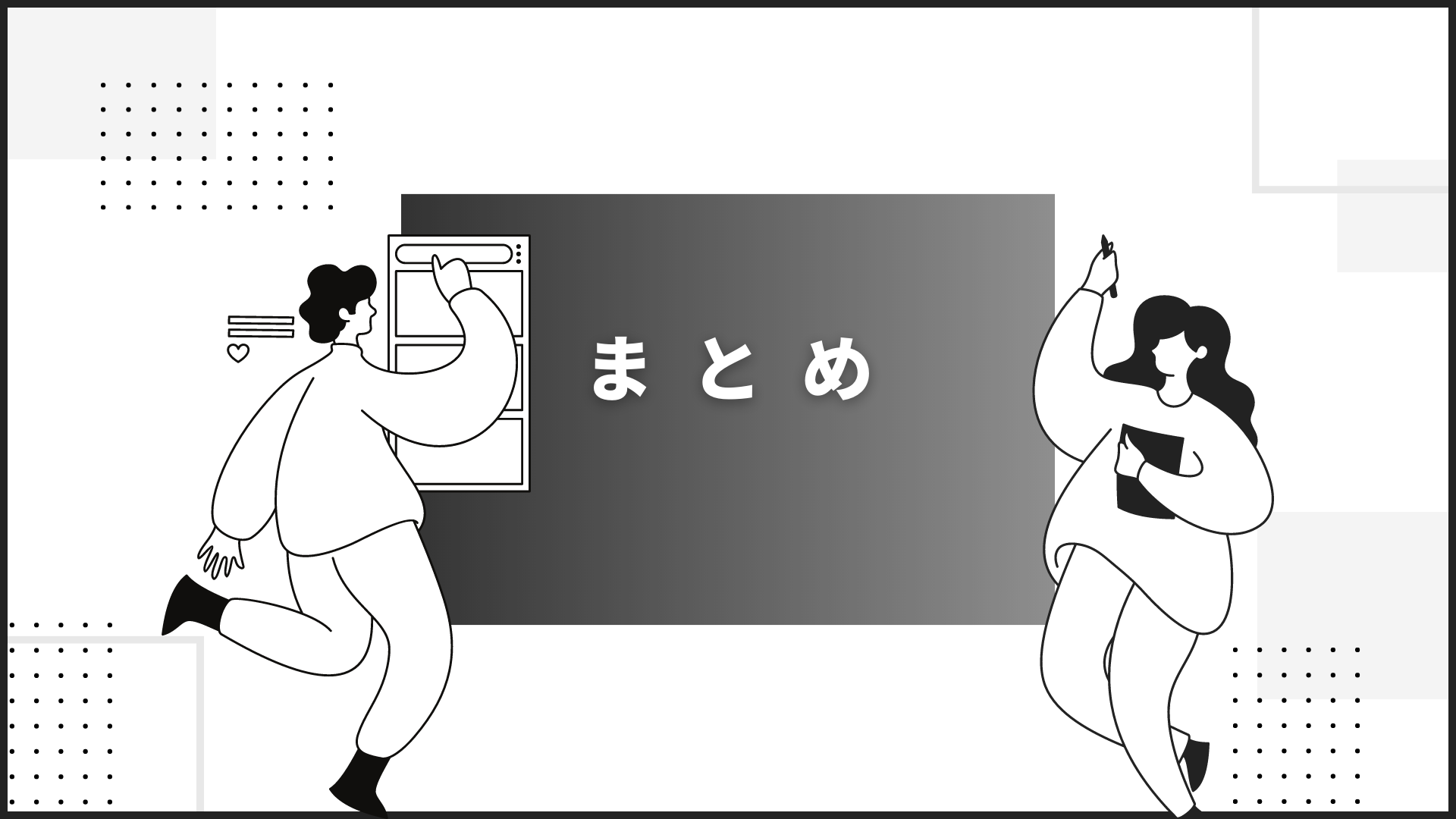
今回紹介した判例では、事業目的に関する制限でしたが、ペット飼育やピアノ禁止など居住目的に関する制限について規約による定めがあることが考えられます。
しかし、賃貸借の媒介業務の実務において、媒介業者から事前に管理規約等の確認を求められないケースは珍しくありません。
特に経験が乏しい媒介業者や担当者には注意が必要です。
賃貸物件のオーナー様には、賃貸借を行うに際して、管理規約や使用細則を事前に確認していただくことを強くお勧め致します。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
