
普通借家契約では、建物を賃貸すると、賃貸人は正当事由がなければ解約や賃借人からの契約の更新を拒むことができません。
そのため、普通借家契約には、契約期間の不確実性、家賃改定の硬直性、立退き料など収益見通しの不確実性が存在します。
その結果、賃貸住宅市場では、回転が早い狭小な賃貸住宅の供給に偏り、空き家などの有効利用が阻害される懸念がありました。
定期借家制度では、契約で定めた期間が満了することによって、更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了します。
それによって、契約期間や収益の見通しが明確になり、賃貸住宅経営の可能性が広がることが期待されます。
しかし、定期借家契約には、普通借家契約にはない説明義務や通知義務があります。
これを怠ると、大きなトラブルになる可能性があり、場合によっては定期借家契約とは認められないケースが生じてしまいます。
定期借家契約では、特に「契約の更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面の交付と説明」と「期間満了の終了通知を出すこと」の2点が重要です。
今回は、定期建物賃貸借で特に注意するべきことについて、お話し致します。
契約の更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面の交付と説明

借地借家法第38条第3項には、次のように定められています。
「(一部省略)建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。」
これは、賃貸借契約書とは別個の、独立の書面でなければなりません。
過去に、賃貸人が所定の書面交付を怠ったことにより定期借家契約が無効とされた判例があります。
この判例を参考に参考にお話しします。
紛争の内容
① 賃貸人(X)は、不動産賃貸などを業とする会社である。
賃借人(Y)は、貸室の経営などを業とする会社であり、本件建物において外国人向けの短期滞在型宿泊施設を営んでいる。
② 賃貸人(X)は2003年(平成15年)7月18日、賃借人(Y)との間で定期建物賃貸借契約書と題する書面(以下「本件契約書」という)を取り交わし、本件建物につき賃貸借契約を締結した。
本件契約書には、本件賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了する旨の条項(以下「本件定期借家条項」という)がある。
③ 賃貸人(X)は、本件賃貸借の締結に先立つ2003年(平成15年)7月上旬頃、賃借人(Y)に対し、本件賃貸借の期間を5年とし、本件定期借家条項と同内容の記載をした本件契約書の原案を送付し、賃借人(Y)は、同原案を検討した。
④ 賃貸人(X)は、2007年(平成19年)7月24日、賃借人(Y)に対し、本件賃貸借は期間の満了により終了する旨の通知をした。
⑤ 賃借人(Y)は、本件においては借地法第38条第2項(現第3項)の事前説明文書の交付がないので、本件契約は定期借家契約ではないと主張し、契約の終了を争った。
各当事者の言い分と本事例の問題点
賃借人(Y)の代表者は、本件契約書には、本件賃貸借が定期建物賃貸借であり契約の更新がない旨明記されていることを明記していたうえ、事前に賃貸人(X)から本件契約者の原案を送付され、その内容を検討していた。
さらに別途の書面が交付されたとしても、本件賃貸借が定期建物賃貸借であることについて、賃借人(Y)の基本的な認識に差が生ずるとは言えない。
したがって、本件契約書とは別個独立の書面を交付する必要はなく、本件の定期借家条項は無効ではない。
【賃借人(Y)の言い分】
借地借家法第38条第2項(現第3項)では、賃貸人(X)が定期建物賃貸借をしようとするときは、賃借人(Y)に対し、あらかじめ書面を交付して説明することを要求している。
そのため、賃貸人(X)が書面の交付および説明を果たさなければ、更新がないとする特約は無効になるというべきである。
したがって、賃貸人(X)が説明書面を交付して説明していないにも関わらず、賃借人(Y)が定期建物賃貸借であることを認識していたことを根拠に本件の賃貸借が定期建物賃貸借であるとすることは、同条第2項(現第3項)及び第3項(現第5項)に違反する。
【本事例の問題点】
賃借人(Y)が、これから締結される契約は更新がなく、期間の満了により終了する旨を認識したうえで契約を締結した。
しかし、別の書面の交付による事前説明がなされていないときに、定期借家契約として認められるか。
本事例の結末
「法第38条第1項の規定に加えて、同条第2項(現第3項)の規定が置かれた趣旨は、定期建物賃貸借に係る契約の締結に先立って、賃借人になろうとする者に対し、定期建物賃貸借は契約の更新がなく期間の満了により終了することを理解させ、当該契約を締結するか否かの意思決定のために十分な情報を提供することのみならず、説明においても更に書面の交付を要求することで契約の更新の有無に関する紛争の発生を未然に防止することにあるものと解される。
以上のような法第38条の規定の構造および趣旨に照らすと、同条第2項(現第3項)は、定期建物賃貸借に係る契約の締結に先立って、賃貸人において、契約書は別個に、定期建物賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了することについて記載した書面を交付したうえ、その旨を説明すべきものとしたことが明らかである。
そして、紛争の発生を未然に防止しようとする同項の趣旨を考慮すると、上記書面の交付を要するか否かについては、当該契約の締結に至る経緯、当該契約の内容についての賃借人の認識の有無および程度等といった個別具体的事情を考慮することなく、形式的、画一的に取り扱うのが相当である。
したがって、法第38条第2項(現第3項)所定の書面は、賃借人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了すると認識しているか否かに関わらず、契約書とは別個独立の書面であることを要するというべきである。
本事例からの考察
これは、同一当事者間で同じ物件を、再契約をするときでも同様です。
さらに、賃貸借契約書を公正証書で作成し、その中に事前説明文書を交付され、説明がなされた旨の記載があっても、その記載のみから事前説明文書の交付・説明の事実を証明することはできない、とされています(最高裁平成22年7月16に璃判決・裁判集民234号307頁)。
本判決のとおり、法第38条第2項(現第3項)の書面(事前説明文書)は、契約書は別個独立の書面であることを要します。
ただし、賃貸人から代理権を授与された宅地建物取引士が、次に掲げる事項を記載した重要事項説明書を交付し、重要事項説明を行うことによって、事前説明文書の交付および事前説明を兼ねることができます。
① 本件賃貸借については、借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借であり、契約の更新がなく、期間の満了により終了すること。
② 本重要事項説明書の交付をもって、借地借家法第38条第2項の規定に基づく事前説明に係る書面の交付を兼ねること。
③ 賃貸人から代理権を授与された宅地建物取引士が行う重要事項説明は、借地借家法第38条第2項(現第3項)の規定に基づき、賃貸人が行う事前説明を兼ねること。
賃貸オーナー様は、入居者の仲介業務や管理業務を委託されていると、委託業者に任せてしまいがちです。
しかし、定期借家契約に関する契約の更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面の交付と説明は、賃貸人に課せられた義務です。
実務では、代理権を授与し、代理権を授与された宅地建物取引士が説明を行えば良いですが、これを怠ってはなりません。
賃借人が期間の満了により終了することを認識しているか否かにかかわらず、別個の書面の交付と説明を怠れば、定期借家契約とは認められません。
定期建物賃貸借の期間満了の終了通知を出すこと

「(一部省略)期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。
ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。」
過去に、賃貸人が終了通知を出すことを怠り、遅れて終了通知を出した事案に関する判例があります。
この判例を参考にお話しします。
紛争の内容
なお、物件は2件あり、それぞれ契約書が締結されていました。
① 期間 3年間
期間の満了をもって契約は終了し、更新がない。
ただし、賃貸人(X)および賃借人(Y)は、協議のうえ、本契約の期間の満了の日の翌日を始期とする、新たな賃貸者契約を締結することができる。
② 賃料 月額57,246円
③ 賃借人(Y)が明け渡しを遅延したときは、賃借人(Y)は、賃貸人(X)に対し、契約終了日(または明渡し猶予期間終了日)の翌日から明渡し完了までの間の賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
2. 賃貸人(X)は、期間満了後約3ヶ月半経過して初めて、賃借人(Y)に対し、「賃貸借終了通知」を送付し、本件定期建物賃貸借契約の期間が満了していることと、同通知到達後6ヶ月の経過をもってこれら賃貸借契約が終了することを通知した。
3. 賃貸人(X)は、上記「2」の通知から6ヶ月経過後、賃借人(Y)に対して本件建物の各明渡しおよび約定損害金の支払を求める訴訟を提起した。
各当事者の言い分と本事例の問題点
1. 本件定期建物賃貸借契約は、借地借家法第38条所定の契約の更新がない借家契約(定期建物賃貸借契約)であり、賃貸借期間満了日の経過により確定的に終了し、賃借人(Y)は不法占有状態となった。
2. 借地借家法第38条第4項(現6項、以下同じ)にいう通知は、借地借家法の適用のある普通賃貸借契約における更新拒絶の要件としての通知とは意味が異なり、契約を終了させるための要件として認められているものではない。
3. 賃借人(Y)は、期間満了前の終了通知がなかったことを根拠に普通建物賃貸借契約と同様の法律関係となった旨を主張するが、期間満了前の通知がないことをもって、賃借人(Y)が定期建物賃貸借契約中の地位以上に保護された地位や利益を確保することになるという結論は、借地借家法第38条第4項が賃貸人(X)に求めている通知に予想外の効果を与えることとなり失当である。
4. 賃貸人(X)による本件通知は、期間満了時点から3か月半程度でされており、明示はもちろんのこと、黙示によっても両者間に新たな普通建物賃貸借契約が成立しているともいえない。
【賃借人(Y)の言い分】
1. 本件定期建物賃貸借契約は、終了通知が発せられないまま期間が満了したことから、普通建物賃貸借契約と同様の法律関係となり、本件通知には正当事由がないから、かかる契約は終了していない。
2. 期間満了後にされた本件通知到達後6か月の経過で定期建物賃貸借契約が終了とすると、賃貸人(X)は、定期建物賃貸借契約を結べば、終了通知を故意に出さないことで、賃貸人(X)の都合のよい時期に契約を終了させることができることになる。
3. 期間満了後、いつでも終了通知することができるとすると、定期建物賃貸借契約以外に、不定期のいつでも解約告知ができる新たな作家形式を立法したことになり、解釈論の範囲を超えている。
4. 借地借家法第38条第4項ただし書が、通知期間経過後も終了通知をすれば通知到達から6ヶ月経過後に明渡し請求できるとするのは、例外を定めたものということができる。
期間満了後はいつでも終了通知をすることができると解釈することは、例外としてあまりに大きすぎるものであり、甚だ不当である。
定期建物賃貸借制度が貸家経営に合理的計算可能性を与えようとするものであるからこそ、賃料改定特約の有効性も規定されたのであり、いつまでも終了通知を可能とすることは定期建物賃貸借制度の根本趣旨に反する。
5. 賃貸人(X)は、期間満了前に終了通知を出すことは容易であったのだから、これを行ったことによる不利益の無辜の賃借人に帰すことは、賃借人保護の目的を有する借地借家法の解釈として不適切である。
6. 賃貸人(X)が期間満了までに終了通知をせず、本件定期建物賃貸借契約終了の意思表示がなかった以上、これらの契約が期間満了により終了するという特約上の権利を賃貸人(X)は放棄したものと解され、賃借人(Y)は、普通建物賃貸借契約における賃借人と同じ立場に立つ。
7. 賃借人(Y)の賃借部分全体のうち事務所部分は普通建物賃貸借契約であるため、正当事由がない賃貸人(X)はその明渡しを求めることができない。
そこで、特に利用する予定もなく、単独では全く利用価値がないにもかかわらず、本件建物について明け渡しを求め、賃借人(Y)に嫌がらせをしようとするものである。
8. 賃貸人(X)は、訴訟外で、隣接するバッティングセンターが既に明渡し予定であるなどと虚言を弄しており、詐欺的であり、上記「7」とあいまって、権利の濫用である。
【本事例の問題点】
1. 借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約において、同条第4項の期間満了の1年前から6ヶ月前までの間になすべき終了通知をなさなかった場合でも、当該定期建物賃貸借は終了したのか否か。
2. 定期建物賃貸借において、同条第4項の期間の終了通知がなかった場合、期間満了後の終了通知によって、当該定期建物賃貸借が終了する場合には正当事由が必要か。
本事例の結末
2. 期間満了後に賃借人が建物の使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったとしても、同条第2項(現第3項)に基づいて従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされることはない。
また、更新しない旨の明示かつ有効な合意が存在することから、民法第619条第1項に基づいて従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定されることもない。
3. 期間の満了によって直ちに賃借人が建物を明け渡さなければならないとすると、賃借人が期間を失念していたような場合には、代替する借家を見つけていないこともあり得るので、賃借人にとって酷な事態になりかねない。
そこで、借地借家法第38条第4項では、契約期間が1年以上である場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、契約が終了する旨の通知を賃貸人に義務付け、賃借人に契約終了に関する注意を喚起し、代替物件を探すためなどに必要な期間を確保することとされている。
そして、通知期間内に通知を怠った場合には、これにより賃借人が不測の損害を被ることにもなりかねない。
そこで、賃借人を保護する観点から、賃貸人が通知期間後の通知をしてから6ヶ月間、賃貸借の終了を対抗することができないものとした。
4. 借地借家法第38条所定の定期建物賃貸借契約のうち、契約期間が1年以上のものについて、賃貸人が期間満了に至るまで同条第4項所定の終了通知を行わなかった場合、定期建物賃貸借契約は期間満了によって確定的に終了し、賃借人は本来の占有権限を失う。
このことは、契約終了通知が義務付けられていない契約期間1年未満のものと異ならない。
ただし、契約期間1年以上のものについては、賃借人に終了通知がされてから6ヶ月後までは、賃貸人は賃借人に対して定期建物賃貸借契約の終了を対抗することができないため、賃借人は明渡しを猶予される。
このことは、契約終了通知が期間満了前にされた場合と期間満了後にされた場合とで異なるものではない。
5. これに対し、賃借人(Y)が主張するように、この場合に賃借人(Y)に対して普通建物賃貸借契約における賃借人と同じ立場となること、すなわち期限の定めのない普通建物賃貸借契約における賃借人になるとすると、賃貸人において契約終了を主張できないばかりか、賃借人においても直ちに契約関係から離脱することはできない。
解約申入れを3ヶ月間を経ないと建物賃貸借契約は終了しないことになるところ、かかる事態は、定期建物賃貸借契約を締結した賃貸人のみならず、賃借人の合理的予測に反するものといわなければならず妥当ではない。
6. 期間満了後、賃貸人から何らの通知ないし意義もないまま、賃借人が建物を長期にわたって使用を継続しているような場合には、黙示的に新たな普通建物賃貸借契約が締結されたものであると解し、あるいは法の潜脱の趣旨が明らかな場合には、一般条項を適用する等の方法で統一的に対応するのが相当である。
賃借人(Y)が主張するように。終了通知が契約期間内に行われたか否かを指標とする方法は、終了通知の義務がない契約期間1年未満のものには対応できないのであって、法がかかる方法を予定しているとも解し難い。
7. 賃貸人(X)は、本件定期建物賃貸借契約が期間満了日をもって終了する旨の通知はなかったこと、その約3カ月半後に初めて本件通知をもって契約終了を通知し、この間、本件建物の賃料等を受領していたことなどが認められるものの、これらの事情をもって、本件建物につき黙示的に期間満了日の翌日から普通建物賃貸借契約を締結したものとまでは認められない。
8. 賃借人(Y)は、賃貸人(X)が賃借人(Y)の賃借部分全体の明け渡しがうまくいかないことから、賃借人(Y)に対する嫌がらせのため、利用予定もないのに本件建物についてのみ明渡しを求めていることなどを主張する。
しかし、賃貸人(Y)が単に賃借人(X)は家の嫌がらせのために本件訴訟を行っているとまでは認めるに足りない。
9. また、賃借人(Y)は賃貸人(X)が訴訟外で隣接するバッティングセンターが既に明け渡し予定であるなどと虚言を弄した旨も主張する。
しかし、仮に訴訟外の交渉時において賃借人(Y)主張のような言動があったとしても、それによって本訴における請求自体が許されないものとなるとはいい難い。
※明渡し通知の対抗を認め、権利濫用を否定して明渡しを認容した。
本事例からの考察
本件では、裁判所の判断は、終了通知を6ヶ月前までにしていなかった事案について、その後の終了通知後6ヶ月で賃借人は建物を明け渡すべきものとしました。
しかし、そもそも、終了通知を期間満了1年前から6ヶ月前までになされていれば係争にはなりませんでした。
2. 定期建物賃貸借の賃貸人が、期間満了6ヶ月前までの終了通知を遅滞した場合は、できる限り早く終了通知を出しましょう。
終了通知が届いたときから6ヶ月で、賃貸借の終了を賃借人に対抗できるようになります。
ただし、本判決では期間満了後、約3ヶ月半後に期間満了通知を出していますが、期間満了後長期間が経過した場合には違う見方がなされる可能性があるため、要注意です。
判旨では、「期間満了後、賃貸人から何らの通知ないし異議もないまま、賃借人が建物を長期にわたって使用継続しているような場合には、黙示的に新たな普通建物賃貸借契約が締結されたものと解し、あるいは法の潜脱の趣旨が明らかな場合には、一般条項を適用するなどの方法で、統一的に対応するのが相当である」としています。
つまり、期間満了後、長期間を経過した場合には、黙示的に新たな普通建物賃貸借契約が締結される余地があるとしています。
その場合は、終了に対し正当事由が必要となります。
3. 仲介する宅地建物取引業者は、定期建物賃貸借を仲介する場合、賃借人に対し、「期間満了により賃貸借が終了し、賃貸人が期間満了6ヶ月前までの終了通知を遅滞した場合であっても、終了通知が遅れてなされた場合は、その後6ヶ月終了を対抗される」ことを説明しておくべきでしょう。
本件では、終了後3ヶ月半ほど経って終了通知がなされ、賃借人からは、定期建物賃貸借終了後、普通建物賃貸借となるとの主張がなされました。
このことについて、本判決では、長期間そのまま継続していたり、あるいは法の潜脱の趣旨が明らかな場合には、普通建物賃貸借が成立したとみる余地があるとしているものの、定期建物賃貸借は期間満了により終了することを明らかにしています。
終わりに
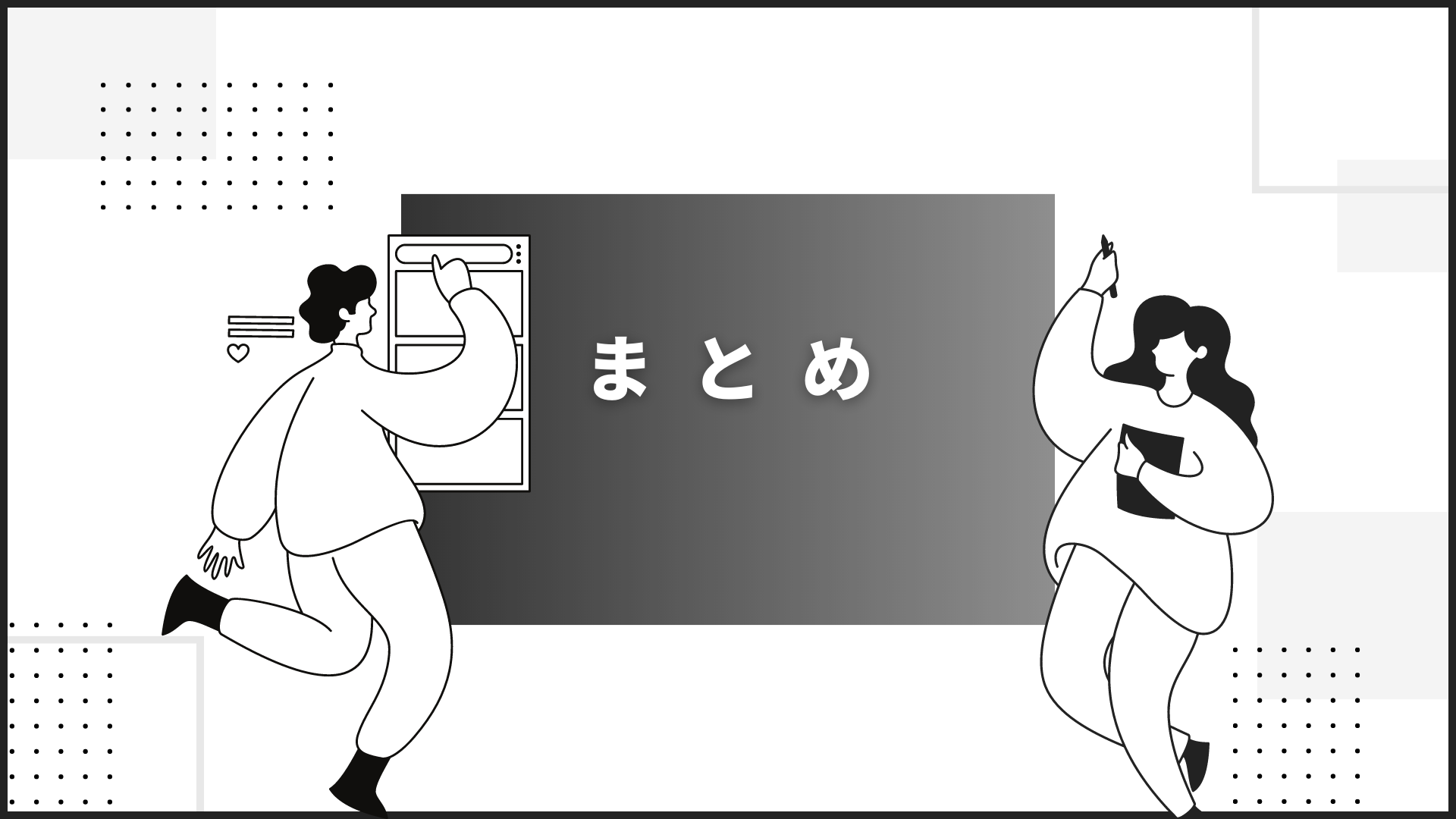
冒頭でお話ししましたとおり、定期借家制度では、契約で定めた期間が満了することによって、更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了します。
それによって、契約期間や収益の見通しが明確になり、賃貸住宅経営の可能性が広がります。
しかし、定期借家制度は普通借家とは異なり、賃借人に対して制限を設けるものです。
定められた説明や通知は、必ず規定どおりに行わなければなりません。
賃貸人自らに課された義務であることを認識し、運用するようにしましょう。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
