
賃貸住宅に関する相談の中でも、原状回復に関する相談は今も多く占めています。
原状回復費用に対するトラブルは賃借人にも広く知られており、さまざまなメディアでも取り上げられています。
現在では敷金・礼金がない賃貸借は珍しいことではないため、不動産オーナーには預かり金がなく、物件明渡し後に賃借人から原状回復費用を回収することが困難な状況になりがちです。
そのため、不動産オーナーは、賃貸借契約を締結するまでに対策をしなければなりません。
今回は、建物賃貸借の原状回復費用の対策についての考察について、お話し致します。
賃借建物の通常損耗について賃借人が原状回復義務を負うための要件(平成17年12月16日の判示)

建物賃貸借の終了に伴い、建物の通常の使用によって生ずる損耗について、賃借人が原状回復義務を負う旨の特約が成立してないとするとともに、賃借人が原状回復義務を負うための要件を示した事例です。
通常の使用による損耗汚損を原状に回復させる費用は、原則として賃貸人が負担すると解されています。
これを当事者間の特約で、賃借人の負担とすることは有効か、また有効とする場合はどのような内容であればよいかについて、考えるにあたって参考になります。
紛争の内容
① 賃借人(X)は、賃貸人である地方住宅供給公社(Y)と住宅の賃貸者契約を締結し、3ヶ月分の家賃相当額の敷金を差し入れた。
② 契約書には、本件契約が終了して賃借住宅を明け渡すときは、契約書の別紙「修繕費負担区分表」に基づいて補修費を負担するとの条項が定められており、その負担区分表において、賃借人の負担とされている範囲には、襖紙、障子紙に関する「汚損(手垢の汚れ、タバコの煤けなど生活することによる変色を含む)・汚れ」、各種床仕上げ材、各種壁・天井など仕上げ材に関する「生活することによる変色・汚損・破損」が明記されていた。
③ 事前の入居説明会において、その負担区分表について具体的な説明がなされなかった。
④ 賃借人(X)は、入居後約2年半後に、本件住宅から退去することとなった。
⑤ 賃貸人(Y)は、その負担区分表の定めるとおり、通常損耗の補修費を含めた補修相当額を敷金から控除して残りを返還した。
⑥ これに対して、賃借人(X)は、敷金全額の返還を請求した。
各当事者の言い分と本事例の問題点
「修繕費負担区分表」において、賃借人が負担すべきとされている「汚損」、「破損」などの記載は、通常損耗の補修費用を賃借人の負担としない内容である。
もし通常損耗の補修費用も賃借人に負担させる定めであるとすれば、賃借人に不当な負担となる賃借条件を定めるものとして、公序良俗に反し無効の特約である。
【賃貸人(Y)の言い分】
本件賃貸借契約においては、当事者間で、賃借人が通常損耗にかかる補修費を負担する内容の特約を含む「修繕費負担区分表」による旨の合意が成立している。
このような特約は、契約自由の原則から認められる。
【本事例の問題点】
賃借人が通常の使用をした場合に生ずる賃借建物の劣化、価値の減少である通常損耗の原状回復費用については、賃貸人が負担するのが原則と解されているが、当事者間の特約で、これを賃借人の負担とすることは有効か。
また、有効と解するとしても、どのような内容のものであれば、その特約といえるのか。
本事例の結末
そのうえで、本件では、契約書の原状回復に関する条項には、賃借人が補修費を負担することになる通常損耗の範囲が具体的には明示されていませんでした。
その条項において引用する修繕費補修区分表の記載は、通常損耗を含む趣旨であることが一義的に明確であるとはいえず、賃貸人が行った入居説明会における説明でも、賃借人が負担すべき範囲を明らかにする説明がありませんでした。
そのため、通常損耗の原状回復費用を、賃借人が負担する旨の特約が成立しているとはいえないとされました。
なお、通常損耗の原状回復費用を賃借人に負担させる特約の有効性に関しては、消費者契約法の適用が問題となります。
本事例は、消費者契約法の施行日(平成13年4月1日)より前の賃貸借契約であったため、同法の適用はなく、同法との関係は取り上げられていません。
本事例からの考察
改正民法では、原則として、特約がない限り、原状回復義務には「通常損耗」「経年変化」は含まれない旨の蒸気解釈が明文で定められました(改正民法第621条)。
通常損耗の原状回復費用は賃貸人負担が原則であるが、これを賃借人の負担とする旨の特約(いわゆる通常損耗特約)が存在する場合、この通常損耗特約の有効性が問題となります。
本判決は、通常損耗の原状回復費用を賃借人に負担させる旨の特約(通常損耗特約)の有効要件について、「少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要である」と判示しています。
通常損耗の原状回復費用を賃借人の負担とする特約(通常損耗特約)を定める場合は、本判決を踏まえて、賃借人の負担すべき通常損耗の範囲を具体的に明記し、賃借人にそのことを明確に認識させることが必要です。
例えば、「汚損・汚れがない場合でも、新品に交換する費用を負担する」と明示して、通常損耗であっても借主が原状回復義務を負担することを明らかにし、また通常損耗について借主が原状回復義務を負う項目や単価を明示して、契約時に借主が将来退去時に負担することになる通常損耗の原状回復費用の金額を予想できるような定めにしておくことが必要と考えられます。
本事案は、消費者契約法が適用される前の事案であったため、消費者契約法の適用については判断していません。
消費者契約法の適用がある居住用賃貸借契約の場合(貸主が事業者、借主が消費者である居住用賃貸借契約の場合)、通常損耗特約が消費者契約法第10条に定める「消費者の利益を一方的に害する」条項にあたり、無効とならないかも問題となります。
通常損耗特約が消費者契約法第10条に反するかどうかは、賃貸借契約全体から見て負担のないように合理性があるかどうかによって決まります。
例えば、東京地裁平成26年5月29日判決では、まず有効な通常損耗特約となるかを判断したうえで、「賃貸開始時に貸主側で補修を行っていること」、「賃料相場に照らして賃料が平均的または下回る価格であること」、「礼金や敷引きの定めがないこと」、「通常損耗の補修費用が賃料の2か月分にも満たないこと」を理由として、消費者契約法第10条に反しないと判断しています。
そのため、通常損耗特約を設けるにあたっては、借主に負担させる金額があまり大きくならないようにするべきでしょう。
その対象を、畳表、ふすま紙、障子紙の交換費用などの消耗品的なもの(小修繕に近いもの)や、適正額のハウスクリーニング代など、金額が高額にならないものに限定した方が特約が無効となるリスクを抑えることができるでしょう。
なお、経年変化自然損耗が原状回復の対象とならず、借主による既存・破損のみが原状回復の対象となるとしても、自然損耗との区別や、借主が原状回復費用を負担する場合の修繕範囲・借主の負担割合の判断については、国土交通省が2011年(平成23年)8月に再改訂版を策定公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」に準拠して処理することが望ましいでしょう。
原状回復費用の負担

1998年(平成10年)1月の改正民事訴訟法によって創設された少額訴訟制度では、この問題から生ずる敷金返還請求も多く利用されています。
原状回復費用の負担について整理しましょう。
原状回復費用の負担
また、敷金は、賃借人の負うべき債務を担保するものであるため、敷金から控除することができます。
問題は、「自然損耗」、「経年変化」による汚損、褐色などを元の状態に戻す費用でしょう。
これは、それに関する特約がある場合とない場合に分けて考える必要があります。
また、2020年(令和2年)4月1日から施行された改正民法により、原状回復についての規定が修正されました(改正民法第621条)。
① 賃借人に原状回復の義務があることが明記されました。
② ただし、賃借人の責めに帰すべき事由がないとき、および、建物の経年劣化による通常損耗については、賃借人は原状回復義務を負わないことが規定されました。
特約がない場合
したがって、返還すべき敷金から控除することはできません。
目的建物が自然に損耗し、経年変化することは当然のことであり、賃借人には何ら責任がないこととされています。
そのため、原状回復負担は賃料収入を得る賃貸人がすべきものであるとされています。
賃借人に負担させる旨の特約がなければ、自然損耗、経年変化によるものを回復する費用は、賃貸人の負担とするのが従来の通説判例の考えでした。
2020年(令和2年)4月1日施工の改正民法では、賃貸借契約が終了した時点における賃借人の原状回復義務を明文化されるとともに、通常使用による損耗、経年変化によるもの、賃借人の責任によらない損傷については、原状回復義務の対象ではないことが明記されました。
「原状に回復」「原状に復す」旨の特約がある場合
まず、賃貸借契約が終了した時点における原状回復費用の負担に関して、契約書の条項に、契約が終了して賃借人が建物を明け渡すときは、賃借人は、自己の費用を持って「原状に回復して明け渡す」「原状に復して明け渡す」といった文言が明記されていることが多いでしょう。
この場合、賃借人に何ら責任(故意または過失)がない、いわゆる自然損耗、経年変化による建物の保存などの修復費用を、そのような契約条項を根拠に賃借人に負担させることができるか、賃借人に返還すべき敷金から控除できるか、という問題がありました。
しかし、今日ではもはやこの問題点はほぼ解決したものとみてよいでしょう。
そのような条項が定められている場合、「原状に回復して」とか「原状に復して」という意味は、賃借人に責任がある汚損、損壊の原状回復の費用を賃借人が負担するというものであって、自然損耗、経年変化によるものは含まないと考えるのが多数の見解でした。
裁判例でも契約書の「賃借人は、本契約が終了したときは、賃借人の費用をもって本物件を当初契約時の原状に復旧させ、賃貸人に明け渡さなければならない」との文言は、通常の使用による損耗汚損を原状に回復させる費用を賃借人が負担する特約とは解されない旨を判示したものがあります(大阪高裁平成12年8月22日判決)。
この裁判例の判決要旨は、ただ単に「原状に復して」とか「原状に回復して」というときには、自然損耗、経年変化によるものの回復費用の負担を賃借人に求めることはできないということであり、この解釈は、前述のとおり多数の見解となっています。
さらに、この点については、上記のとおり、改正民法第621条に、通常使用による損耗・経年変化によるものについては、原状回復義務の対象ではないことが明記されました。
【参考】
第621条(賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後に、これに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下、この条において同じ。)がある場合において。賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
賃借人の費用負担の範囲を明確に定めた特約がある場合
このような特約については、その特約の有効性について、従来学説も分かれており裁判でもまちまちでした。
しかし最高裁が、先述の2005年(平成17年)12月16日に判示した賃借人の原状回復義務の存否が争点となったケースにおいて、傍論ですが賃借人が自らに責任のない損耗について原状回復義務を負うための要件を述べています。
「通常損耗について賃借人が原状回復義務を負う旨の特約の成立が認められるためには、同特約の内容が契約書自体に明記されている、もしくは、契約書では明らかでない場合には、少なくとも賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められることが必要であるというべきである」
ガイドライン
同ガイドラインでは、原状回復にかかるトラブルを未然に防止するために必要な事項として、次のことが掲げられています。
① 契約時における物件の確認の徹底
入居時にチェックリストを作成し、部位ごとの現況を当事者が立会いのうえで十分に確認すること。
② 原状回復に関する契約条件などの開示
賃貸人は、賃借人に対して、原状回復の内容などを契約前に開示し、賃借人の十分な認識を得ること。
③ 特約について
賃貸借契約において特約を設ける場合は、以下の点に留意する必要があります。
1. 特約の必要性があり、かつ暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること。
2. 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕などの義務を負うことについて認識していること。
3. 賃借人が、特約による義務負担の意思表示をしていること。
同ガイドラインは、その後、2011年(平成23年)8月に同改定が行われました。
原状回復の負担原則の契約書への添付による明確な合意の推奨、 Q&Aの見直し、新裁判例の追加などが行われました。
再改定のポイントは次のとおりです。
① 原状回復にかかるトラブルの未然防止
1. 賃貸住宅標準契約書との連動を意識した原状回復条件様式の追加
2. 原状回復費用精算書様式の追加
3. 特約の有効性、無効性の考え方の明確化
② 税法改正による残存価値割合の変更
賃借人の負担は、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多くなるほど負担割合が減少することになります。
従来、償却期間経過後の賃借人負担を10%としてきたものを、2017年(平成19年)の税法改正に従い、1円まで償却できるようになりました。
ガイドラインの設備などの経過年数と賃借人の負担割合も、これに伴い改訂されました。
③ Q&Aおよび裁判事例の追加
2004年(平成16年)改定後の主な関連判例21例を追加し、42例となりました。
原状回復に対する賃貸オーナーの対策

特に、物件を大切に扱ってきた不動産オーナーには受け入れ難いことかもしれません。
しかし、民法が改正された意義は大きく、これまでのように「ガイドラインは法律に明記されたものではない」という認識や主張は通りません。
リフォーム費用の単価も高騰しており、賃貸オーナーには原状回復に対する対策が必要です。
なお、改正民法の対象となるのは、2020年4月1日以降に締結された賃貸借契約です。
旧民法の賃貸借契約でも、施行後に賃貸人と賃借人が合意して更新した賃貸契約(いわゆる合意更新)は改正民法が適用されますが、合意更新ではなく自動的に更新された賃貸借契約(いわゆる法定更新)は対象外と考えられています。
旧民法の賃貸借契約を終了した際に原状回復のトラブルが発生した場合は、賃貸借契約書の特約を確認したうえで、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを参考にして、相手方と話し合うことになります。
リフォーム費用のシミュレーション
これは、通常損耗を回復するための経費が、すでに賃料に含まれているという考えに基づいています。
そのため、賃貸オーナーは、通常損耗による修繕費用を賃料に含めて、収支をシミュレーションしなければなりません。
そこで、まずは過去に行った修繕項目や費用を振り返る必要があるでしょう。
それがわからなければ、そもそも今の賃料設定が妥当かどうかの判断すらできません。
空調機や給湯器などの設備は耐用年数からある程度は想定できますが、内装は立地条件や入居者層によっても損耗の程度に違いが出ます。
南向きで日当たりのよい部屋は日焼けしやすい一方で、湿気には強い可能性があります。
子どもがいて家にいる時間も長いファミリー物件と、家にいる時間が短い社会人単身用マンションでは、同じ通常損耗でも程度は異なるでしょう。
所有する賃貸物件によって、修繕項目や費用は違います。
修繕は部屋の室内だけではありません。
マンションなどの外壁や共用部などの修繕等に要する費用も考えなければなりません。
区分所有マンションで管理費や修繕積立金の価格が上がっていくことが問題視されますが、これは区分所有マンションに限ったことではありません。
新しいマンションが建設されれば、修繕だけでなく設備投資を行っていかなければ選ばれなくなります。
修繕費用も将来高騰していくことが予想されます。
そのため、収支のシミュレーションは都度見直すべきでしょう。
賃貸収益は、すぐに改善できるものではありません。
収支が厳しいからといって賃料を値上げすることなど、簡単にはいきません。
賃貸借契約で、経済状況の変化により価格を見直すことができるという約定を付けていたとしても、賃借人の承諾が必要です。
また、値上げを行うことによって賃借人が違う物件へ転居することになるかもしれません。
中長期的な目線で計画し、対策をしなければなりません。
管理会社への対応について
その管理会社が、退去立会いや退去清算など、どのような対応をしているか把握しておきましょう。
故意・過失部分の損傷等の見落としは、多くの現場で起こっています。
そもそも、入居時の状況を把握できていないこともあります。
入居時には損傷がないことを立証できなければ、明渡し時に請求しても認められません。
部屋を全改装したリフォームの見積等の記録や物件引渡し前の写真、物件引渡し時の入居者との立会い等による記録など、物件引渡し前の記録を残しておかなければなりません。
また、不動産管理会社は、賃借人よりも賃貸人の方が費用を請求しやすいと考えています。
例えば、賃貸借契約成約時の仲介料についても同じです。
賃借人に対しては仲介手数料を減額しますが、賃貸人に対しては仲介手数料以上の費用を請求しています。
また管理会社には他にも問題があります。
物件のことを、入居者の方が管理会社の担当者よりもはるかに理解していることです。
以前は、入居者よりも、管理会社の担当者の方が、当然に知識や経験がありましたが、今では入居者も知識を持っています。
管理会社の担当者がしっかりとした準備なく、退去立会いを行っているケースが多いです。
特に1月から3月の繁忙期は数が多いため、準備が足りないことが多く見受けられます。
賃貸オーナーだけでなく、管理会社も事前の準備がどれだけできているかが重要です。
サブリース物件の問題
サブリース契約では、部屋の修繕費用は、賃借人であるサブリース業者の負担としていることも多いでしょう。
サブリース業者としては、当然部屋の修繕費用は抑えたいと考えます。
そのため、安価な設備や修繕方法を選択することが多いでしょう。
すぐには大きな影響は出ないでしょう。
しかし、安価な修繕方法を繰り返せば、物件の質が下がることは避けられません。
これが採算が合わない原因の1つになってしまいます。
そして、この状態でサブリース契約を解除されてしまうと、その後は所有者が対応することになります。
言葉は悪いですが、使えるだけ使って、あとは放り出されてしまうのです。
賃借人の費用負担の範囲を明確に定めた特約
ただし、通常損耗の原状回復費用を賃借人の負担とする特約(通常損耗特約)を定める場合は、賃借人の負担すべき通常損耗の範囲を具体的に明記し、賃借人にそのことを明確に認識させることが必要です。
また、特約が消費者契約法第10条に定める「消費者の利益を一方的に害する」にも注意しなければなりません。
特約を設けるにあたっては、借主に負担させる金額があまり大きくならないようにしましょう。
対象を、畳表、ふすま紙、障子紙の交換費用などの消耗品的なもの(小修繕に近いもの)にすること、また適正額のハウスクリーニング代など金額が高額にならないものに限定することによって、特約が無効となるリスクを抑えることができるでしょう。
終わりに
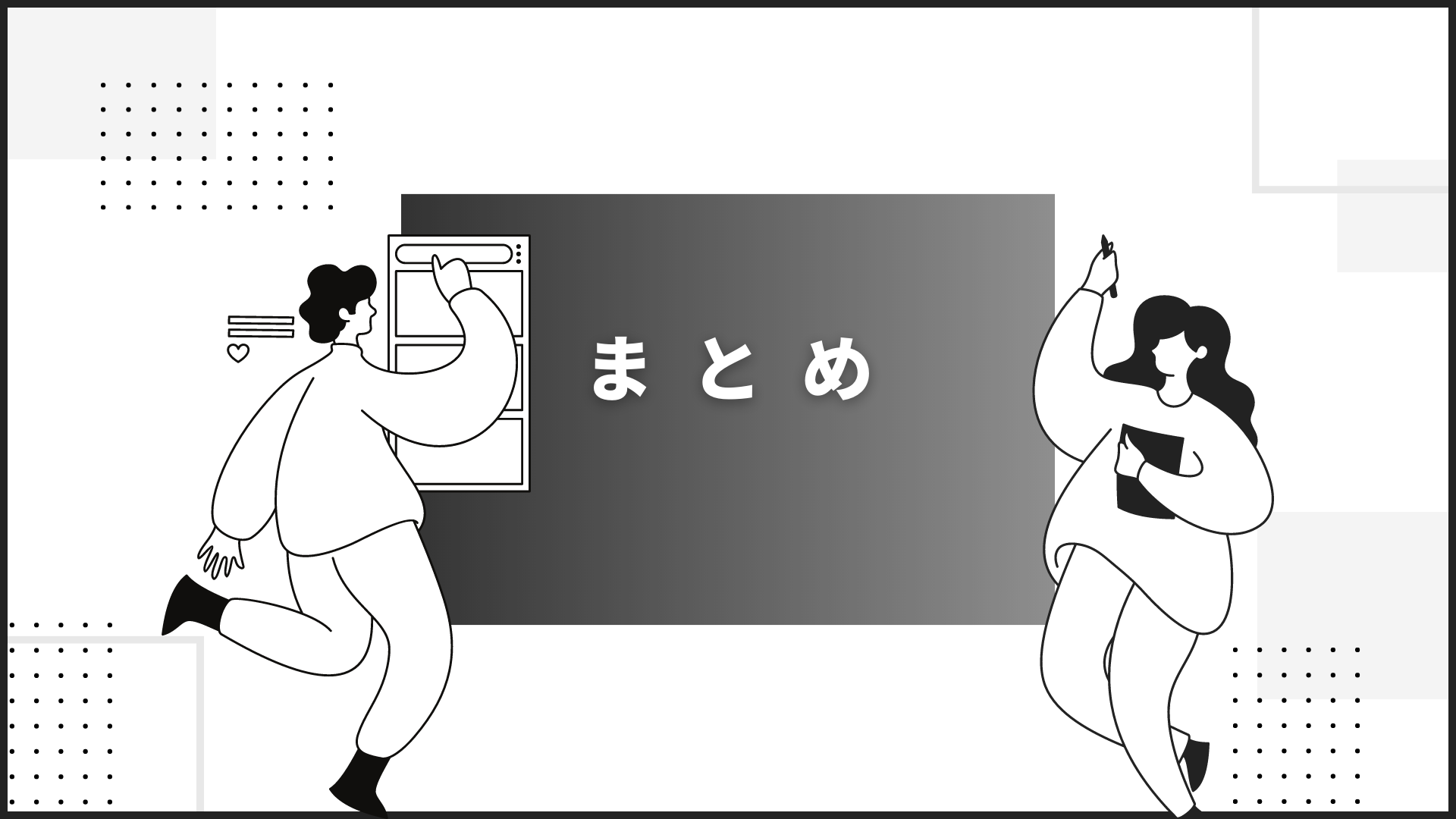
消費生活センターに寄せられる賃貸住宅に関する消費生活相談は、毎年3万件以上寄せられているようですが、そのうち、原状回復に関する相談件数は毎年1万3,000~1万4,000 件程度となっており、賃貸住宅に関する相談のうち約4割を占めています。
賃貸オーナーにとって、避けられないトラブルの1つです。
また、賃貸には繁忙期と閑散期があり、繁忙期に問題が多く発生する傾向があります。
原状回復に関する消費生活相談を月別にみると、12月から1月頃は相談が最も少なく、2月から4月にかけて相談が増え、5月以降には減少するという傾向がみられるそうです。
賃貸オーナーにとって、今後は厳しい情勢が続くことが予想されます。
地主の方でも、むかしは明渡し後の修繕費用に対してあまり意見を言わなかった方が、最近は明細をしっかり見て意見を言われる方が増えたと感じます。
もはや賃貸オーナーは、不労所得者として羨むような職種ではなくなっています。
まずは過去の経費を振り返り、将来予測される修繕等に要する費用をどのように確保するかシミュレーションしましょう。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
