
不動産実務において発生するクレームや争いに関して、消費者契約法が関係することがあります。
相手方は、契約自由の原則を主張されるケースが多いように感じます。
契約自由の原則とは、人が社会生活を営むに際して結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるという民法上の基本原則です。
民法に直接の規定はありませんが、「公序良俗違反の法律行為の無効」(第90条)や「任意規定と異なる意思表示」(第91条)を根拠とされています。
しかし、「公の秩序や強行法規に反しない限り」という条件があります。
消費者契約法という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。
理解を深めて、争いが起こらないように備えましょう。
今回は、不動産取引と消費者契約法について、お話し致します。
消費者契約法の目的と意義

消費者契約法は、この情報格差を踏まえ、消費者を保護するためのルールを定めたものです。
消費者契約法は、2000年(平成12)年5月に制定・公布され、2001年(平成13年)7月1日に施行されています。
消費者契約法の目的
事業者に対して、消費者契約の締結や勧誘などにあたり、3つの方法による規制を課すことによって、消費者を保護する仕組みが構築されています。
第1の方法は、事業者に対して、契約締結や勧誘などにおける努力義務を課すことです。
事業者は、消費者契約の条項を定めるには、解釈に疑義が生じない明確なもので、且つ消費者にとって平易なものになるよう配慮しなければならないとされています。
また、消費者契約の勧誘に際しては、消費者契約の内容について必要な情報提供を行わなければならないなど、努力義務が課されています。
第2の方法は、消費者に対して不当勧誘がなされた場合、契約の取消しを認めることです。
事業者が、消費者契約を勧誘する場面において、消費者を誤認または困惑させた場合などには、消費者が消費者契約を取り消すことが認められています。
第3の方法は、不当な契約条項を無効とすることです。
契約内容が消費者の利益を一方的に害し、信義則に反するなどの場合には、契約条項が無効とされます。
消費者契約の異議
「消費者」
個人
(事業として、または事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)
「事業者」
法人その他の団体、および事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合における個人
「消費者契約」
消費者と事業者との間で締結される契約
すなわち、個人のうち事業を行うために契約をする者以外が「消費者」です。
その他の個人と団体が「事業者」です。
契約当事者の一方が「消費者」、他方が「事業者」の場合に、「消費者契約」となります。
契約の両当事者のいずれもが「消費者」、もしくは、いずれもが「事業者」の場合は、「消費者契約」にはなりません。
個人が当事者となる売買契約や賃貸借について、消費者契約かどうか考えてみましょう。
個人が不動産業者から自宅を購入したり賃借したりする場合は、「消費者」と「事業者」の契約ですから、売買や賃貸借の契約は「消費者契約」です。
個人が売主として自宅を売却し、買主も個人が自宅として使用する場合は、「消費者」と「消費者」の契約ですから、売買契約は「消費者契約」ではありません。
個人が個人営業のために不動産業者から店舗を賃借する場合にも、「事業者」と「事業者」の契約ですから、店舗の賃貸借契約は「消費者契約」ではありません。
個人が買主として不動産業者から投資用不動産を購入する場合に、「事業者」になるかどうかが問題になることがあります。
しかし、一般的には、不動産に投資をして賃貸収入を得ることは事業となります。
したがって、個人であっても投資用不動産を購入する場合には、原則として「事業者」となります。
このことに言及している裁判例として、東京地裁平成31年1月11日判決があります。
そこでは、「会社員である被告は、投資用のマンションを既に3件所有していた中で、さらに投資用として本件物件を購入しようとしたものであるから、被告は、事業としてまたは事業のために本件売買契約の当事者となったというべきであり、「消費者」に当たらない」とされています。
もっとも、不動産取引の回数や不動産の規模を勘案して、事業としてまたは事業のために行ったものではないとされるケースもあります。東京地裁令和4年1月31日判決では、初めての不動産取引であって、売買対象が賃料月額83,500円の居室2室である売買契約について、買主の個人が「消費者」とされています。
事業者の努力義務

「消費者契約の条項作成」
消費者契約の条項を定めるにあたって、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が、その解釈について芸が生じない明確なものであり、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること。
「消費者契約の勧誘」
消費者契約の締結について勧誘をするに際して、消費者の理解を深めるために、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識および経験を総合的に考慮したうえで、消費者の権利、義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。
「定型取引合意に該当する消費者契約の勧誘」
提携取引合意に該当する消費者契約の締結について勧誘をするに際して、消費者が定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除き、消費者が提携契約間の内容を知る権利を行使するために必要な情報を提供すること。
「消費者による消費者契約の解除」
消費者が消費者契約を解除しようとする場合に、消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた消費者が有する解除権の行使に関して、必要な情報を提供すること。
「損害賠償の額の予定または違約金の算定」
損害賠償の額の予定または違約金の算定根拠について、消費者から説明を求められたときは、算定の根拠の概要を説明すること。
不当な勧誘による契約の取消し

不当勧誘等による消費者契約の取消しには、「誤認の類型」、「困惑の類型」、「契約内容が科料な場合の類型」という3つの類型があります。
誤認の類型
「不実告知」
事業者が、重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、そのことにより消費者がその告げられた内容が事実であるとの誤認をして、誤認によって契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者は、消費者契約を取り消すことができます。
= 不実告知の例 =
・物件が築55年であるにも関わらず、「この建物は築50年である」などと告げること。
・抵当権が設定または差押えがなされている宅地であるにも関わらず、「一切負担のない宅地である」などと告げること。
なお、不実であることについて、事業者の故意・過失は問われません。
「断定的判断の提供」
事業者が物品、権利、役務その他のその契約の目的となるものに関し、将来における価額、将来その消費者が受け取るべき金額、その他将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供したことによって。消費者がその断定的判断の内容が確実であるとの誤認をし、それによって契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときには、消費者は消費者契約を取り消すことができます。
= 断定的判断の提供の例 =
・「今この物件を買えば必ず儲かる」などと告げること。
・「2~3年後には必ず2倍の価値となる」などと告げること。
なお、断定的判断の提供であることについては、事業者の故意・過失は問われません。
「利益事実の告知+不利益事実の不告知」
事業者が、ある重要事項またはその重要事項に関連する事項について、消費者の利益となる旨を告げ、且つ不利益となる事実を告げなかったことにより、消費者がその事実が存在しないとの誤認をし、それによって契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときには、消費者は消費者契約を取り消すことができます。
= 利益事実の告知+不利益事実の不告知の例 =
・取引物件の南側隣地に高層マンションが建つ予定があることを知りながら、「日当たり通風は良好」と告げ、そのマンションの建設計画を告げないこと。
・緑化率が条例上の最低限度を下回り、条例違反となっていることを知りながら、この事実を告げず、物件のセールスポイントだけを告げて戸建住宅を販売したこと。
利益事実の告知+不利益事実の不告知については、事業者に故意または重過失があることを要します。
また、利益事実の告知+不利益事実の不告知は、取消事由には当たりません。
困惑の類型
「不退去」
事業者に対して、消費者がその住居または業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
「退去妨害」
消費者が勧誘の場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、事業者がその場所から消費者を退去させないこと。
「勧誘することを告げずに退去困難な場所に同行し勧誘すること」
事業者が、勧誘をすることを告げずに、任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、消費者をその場所に同行し、その場所において契約の締結について勧誘をすること。
= 例 =
・投資用マンションの締結を勧誘することを告げずに、いったん投資セミナーに参加すれば任意に退去することが困難であることを知りながら、消費者を投資セミナーに同行し、その場所でマンションの契約の締結について勧誘をする行為。
「相談の連絡の妨害」
消費者が契約の締結について勧誘を受けている場所において、消費者が契約を締結するか否かについて相談を行うために電話その他の方法によって事業者以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、事業者が威迫する言動を交えて、消費者がその方法によって連絡することを妨げること。
= 例 =
消費者が新築マンション販売の締結について勧誘を受けている場所で、消費者が配偶者と電話で相談したいという意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、消費者が配偶者に電話連絡することを妨げる行為。
「進学・就職・結婚等の不安の不当な利用」
消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、進学・就職・結婚・生計その他の社会生活上の重要な事項、または容姿・体型その他の身体の特徴または状況に関する重要な事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、物品、権利、役務その他の契約の目的となるものが願望を実現するために必要である旨を告げること。
「恋愛感情その他の好意の感情の利用」
消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の行為の感情を抱き、かつ、勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、消費者契約を締結しなければ勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
= 例 =
・デート商法
「加齢等による判断力の低下の不当な利用」
消費者が、加齢または心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
「霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見の利用」
消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者またはその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、もしくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、またはそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げること。
= 例 =
・霊感商法
「契約締結前の債務の内容実施等」
消費者が当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をする前に、契約をしたならば負うこととなる義務の内容の全部、もしくは一部を実施し、または当該消費者契約の目的物の現状を変更し、その実施または変更前の原状の回復を著しく困難にすること。
「損失補償請求等の告知」
消費者が、契約の申込みまたはその承諾の意思表示をする前に、事業者が調査、情報の提供、物品の調達その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったことその他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨および当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。
契約内容が過量な場合
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数または期間(分量など)が、消費者にとっての通常の分量など(消費者契約の目的となるものの内容、取引条件、事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況およびこれについての消費者の認識に照らして、当該消費者契約の目的となるものの分量などとして通常想定される分量など)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により、消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができます。
読みにくいので、不動産の売買や賃貸借の契約内容が過量な場合の例をあげます。
例えば、高齢の夫婦に対して、日常生活にはまったく必要のない著しく広い床面積の建物を居住用として売却したり、賃貸したりすることが想定されます。
不要な広さの住宅の売買や賃貸の勧誘が行われた場合には、契約内容が過量な場合にあたるとして、第4条第4項によって売買契約や賃貸借契約が取り消される可能性があります。
事業者から委託を受けた媒介業者が取消事由となる行為を行った場合
消費者契約の締結に係る消費者の代理人、事業者の代理人および受託者等の代理人は、取消事由となる行為、不当条項として無効となる行為との関係においては、それぞれ消費者、事業者および受託者等とみなされます。
したがって、媒介業者が事業者から委託を受けて媒介行為を行うにあたって、誤認類型や困惑類型に含まれる行為を行った場合には、消費者は、事業者の行った行為とみなして契約を取り消すことができます。
取消権の行使の期間
= 追認することができるとき =
・誤認類型・・事業者の行為により誤認したことを消費者が気づいたとき
・困惑類型・・困惑状態から消費者が脱したとき
もっとも、この取消しは善意無過失の第三者には対抗できません。
また、契約締結のときから5年を経過したとき、取消権は消滅します。
なお、霊感等による知見を用いた告知がなされた場合は、追認をすることができるときから3年間、消費者契約の締結から10年間と、取消権の行使期間が伸長されます。
不当な契約条項の無効

無効となる不当条項には、以下があります。
「事業者の損害賠償の責任を免除する条項等」
「消費者の解除権を放棄させる条項等」
「事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項」
「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等」
「消費者の利益を一方的に害する条項」
事業者の損害賠償の責任を免除する条項等
債務不履行や不法行為による損害賠償責任の内容は、本来、民法によれば、契約当事者の間で自由に取り決めをすることができます。
しかしこれに対して、消費者契約法では、消費者保護のために次の4つを無効としています。
① 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、または事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
② 事業者の債務不履行により。消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、または事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
(ただし債務不履行は、事業者、その代表者またはその使用する者の故意または重大な過失によるものに限ります)
③ 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、または事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
④ 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、または事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
(ただし不法行為は、事業者、その代表者またはその使用する者の故意または重大な過失によるものに限ります)
①、③では、責任の全部免除または責任の有無の決定権限を事業者に付与する条項が無効とされ、②、④では、無効とされ、②、④で、は、故意・重過失について、責任の一部免除または責任の有無の決定権限を事業者に付与する条項が無効とされています。
故意とは、自己の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることです。
過失とは、一定の事実を認識できたにもかかわらず、その人の職業、社会的地位などからみて、一般に要求される程度の注意を欠いたため、それを認識しないことです。
重大な過失とは、この注意を著しく欠いている場合で、相当の注意をすれば容易に有害な結果を予見することができるにもかかわらず、漫然看破したというような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいいます。
「有償契約での契約不適合責任の特例」
上記の①、②の条項のうち、消費者契約が有償契約である場合に、引き渡された目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないときに、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、または事業者にその責任の有無もしくは限度を決定する権限を付与するものは、次の①、②の場合には無効とはされず、効力が認められます。
① 消費者契約において、引き渡された目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないときに、事業者が履行の追完をする責任または不適合の程度に応じた代金もしくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合
② 消費者と事業者の委託を受けたほかの事業者との間の契約、または事業者とほかの事業者との間の消費者のためにする契約で、消費者契約の締結に先立って、またはこれと同時に締結されたものにおいて、引き渡された目的物が種類または品質に関して、契約の内容に適合しないときに、その他の事業者がその目的物が種類または品質に関して、契約の内容に適合しないことにより消費者に生じた損害を賠償する責任の全部もしくは一部を負い、または履行の追完をする責任を負うこととされている場合
「責任の一部免除特約が過失による場合に限定されることの明記」
業者の債務不履行(ただし、事業者その代表者またはその使用する者の故意または重大な過失によるものを除く)または消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた事業者の不法行為(ただし、事業者、その代表者またはその使用する者の故意または重大な過失によるものを除く)により、消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、条項において事業者、その代表者またはその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とされます。
これは、いわゆるサルベージ条項です。
このサルベージ条項を無効とするルールは、消費者契約法の2022年(令和4年)5月の改正で追加されたものです。
例えば、「法律上有効な限り、当社は一切の責任を負いません」という条項は、サルベージ条項です。
また、「当社は一切の責任を負いません」、「その他当社の損害賠償責任を免責する規定は、消費者契約法その他法令で認められる範囲でのみ効力を有するものとします」の、2つの文言が同一条項にあるものも、サルベージ条項として効力は否定されます。
消費者の解除権を放棄させる条項等
しかし、事業者が契約で定められた債務を履行せず、または事業者から引き渡された目的物に瑕疵がある場合でも、消費者が解除することができないとすると、消費者は契約に不当に拘束され続け、既に支払った代金の返還を受けられず、または未払い代金の支払義務を免れることができないことになり、消費者は不利益を被ります。
そこで、消費者契約法では、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、または事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とされています。
なお、消費者の解除権を制限する条項は、無効ではありません。
例えば、解除権の行使期間を限定する条項、解除が認められるための要件を加重する条項、解除する際の方法を限定する条項などは、無効ではありません。
後見開始の審判等による解除権を付与する条項
そこで。事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約の条項は無効とされています。
ただし、消費者が、事業者に対し、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除きます。
解約料を定める条項
なお、平均的な損害額の主張・立証に必要な情報は事業者に偏在しており、消費者がこの額を主張・立証することは容易ではありません。
そこで、消費者の立証責任の負担軽減を図るため、事業者は消費者に対し、消費者契約の解除に伴う解約料を定める情報に基づき解約料の支払いを請求する場合において、消費者から説明を求められたときは、解約料の算定の根拠(算定根拠)の概要を説明するよう努めなければならないとされています。
また、消費者が支払うべき金銭に関する遅延損害金が、年14.6%を超える場合、その率を超える部分は無効です。
消費者の利益を一方的に害する条項
第10条は前段と後段に分かれています。
前段の要件(前段要件)と後段の要件(後段要件)の2つの要件を満たした場合に、消費者契約の条項が無効になります。
前段要件は、契約条項が、法令中の公の秩序に関しない規定(任意規定)の適用による場合に比べ、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重していることです。
後段要件は、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して、消費者の利益を一方的に害することです。
民法第1条第2項には、「権利の行使および義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」として、信義誠実の原則が定められているため、契約条項が信義誠実の原則に違反していることが後段要件となります。
信義誠実の原則は抽象的な概念であって、さまざまな事情を勘案しなければ、この原則に違反するかどうかは判定できません。
第10条による無効とされるかどうかの判断には、判例が重要な意味を持つことになります。
建物賃貸借の敷引特約、更新料支払特約、追い出し条項

この3つは、過去注目された争いであり、消費者の利益を一方的に害する条項に関する例として話題に上がります。
敷引特約
敷引特約は、敷金の額が敷引特約の趣旨からみて高額に過ぎるなどの場合でなければ、第10条による無効にはなりません。
最高裁2011年(平成23年)3月24日判例では、「通常損耗などの補修の要否やその費用の額をめぐる紛争を防止するといった観点から、あながち不合理なものとはいえず、敷引特約が信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできない」として、原則として効力を認めています。
もっとも、合わせて「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金など他の一時金の授受の有無およびその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である」と判断しています。
この最高裁の事案では、月額賃料9万6,000円。保証金(実質は敷金)40万円、経過期間に応じて敷引金18万円ないし34万円を保証金から控除すると定められた特約は、無効とはいえないとして、効力を認めています。
また、最高裁2011年(平成23年)7月12日判決でも、賃料が、契約当初は月額17万5,000円、更新後は17万円であって、敷引金の額はその3.5倍程度であった事案について「高額にすぎるとはいい難く、本件敷引金の額が、近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して、大幅に高額であることもうかがわれない」として、無効ではないとして、効力を認めています。
更新料支払特約
その性格については、最高裁2011年(平成23年)7月15日判決において、次のようにされています。
「いかなる性質を有するかは、賃貸借契約成立前後の当事者双方の事情、更新料条項が成立するに至った経緯、その他諸般の事情を総合考量し、具体的事実関係に即して判断されるべきであるが、更新料は、賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であり、その支払により賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからすると、更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸者契約を継続するための対価等の趣旨を含む総合的な性質を有するものと解するのが相当である」
更新料支払特約は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間などに照らし、高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、第10条による無効とはならず、効力が認められます。
かつてはその効力に争いがありましたが、上記最高裁2011年(平成23年)7月15日判決において、「一定の地域において、期間満了の際、賃借人が賃貸に対し更新料の支払をする例が少なからず存することは公知であることや、従前、裁判上の和解手続きなどにおいても、更新料条項は公序良俗に反するなどとして、これを当然に無効とする取り扱いがされてこなかったことは裁判所に顕著であることからすると更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され。賃借人と賃貸人との間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に、賃借人と賃貸人との間に、更新料条項に関する情報の質および量並びに交渉力について、看破し得ないほどの格差が存するとみることもできない。そうすると、賃貸借契約書に一時的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間などに照らし、高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう『民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの』にあたらないとされ、現在では更新料支払特約の効力に関する考え方が統一されています。
この最高裁の判決では、期間1年、月額賃料3万8,000円、更新料の額を賃料の2か月分とする賃貸借における更新料特約の効力が認められています。
ただし、更新料の額が、賃料の額、賃貸借契約が更新される期間などに照らし、高額に過ぎるなどの特段の事情があれば、更新料支払特約には効力が認められません。
追い出し条項
契約解除をせずに賃貸借が終了したものと取り扱うことはできず、強制執行の手続きを取らずに実力で権利を実現することは、違法となります。
この点に関して、賃借人が、家賃債務保証会社に、賃貸借契約を解除する権限を付与し、賃借物件の明け渡しがあったものとみなす権限を付与する特約(追い出し条項)の効力が消費者契約法10条に違反するものとして、無効とされたケースが、最高裁2022年(令和4年)12月12日判決です。
このケースで問題とされたのは、次の2つです。
1つは、「家賃債務保証会社は、賃借人が支払を怠った賃料等および変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約(原契約)を解除することができる」とする、解除権付与条項です。
もう1つは、「家賃債務保証会社は、次の事由が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって建物の明渡しがあったものとみなすことができる。 2号 賃借人が、賃料等の支払を2ヶ月以上怠り、家賃債務保証会社が合理的な手段を尽くしても、賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況などから建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するとき」とする、明渡しみなし条項です。
最高裁は、解除権付与条項について、「原契約は、当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約であるところ、その解除は、賃借人の生活の基盤を失わせるという重大な事態を招来し得るものであるから、契約関係の解消に先立ち、賃借人に賃料債務などの履行について最終的な考慮の機会を与えるため、その催告を行う必要性は大きいということができる。
ところが、13条1項前段は、所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合、原契約の当事者でもない家賃債務保証会社がその一存で何らの限定なく原契約につき無催告で解除権を行使することができるとするものであるから、賃借人が重大な不利益を被る恐れがあるということができる。
したがって、13条1項前段は、消費者である賃借人と事業者である家賃債務保証会社の各利益の間に看破し得ない不均衡をもたらし、当事者間の衡平を害するものであるから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるというべきである」としている。
また、明け渡しみなし条項については、「家賃債務保証会社が、原契約が終了していない場合において、18条2項2号に基づいて建物の明渡しがあったものとみなしたときは、賃借人は、建物に対する使用収益権が制限されることとなる。そのため、18条2項2号は、この点において、任意規定の適用による場合に比し、消費者である賃借人の権利を制限するものというべきである。
そして、このようなときには、賃借人は、建物に対する使用収益権が一方的に制限されることになるうえ、建物の明渡義務を負っていないにもかかわらず、賃貸人が賃借人に対して建物の明渡請求権を有し、これが法律に定める手続によることなく、実現されたのと同様の状態に置かれるのであって、著しく不当というべきである」として、いずれの条項も無効と判断し、効力を否定しました。
消費者契約法とほかの法律の関係

また、消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について、民法および商法以外のほかの法律に別段の定めがあるときは、その他の法律の定めるところによります。
例えば、損害賠償額の予定について、消費者契約法では、同種の契約の解除に伴い、事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、その超える部分を無効としていますが、宅建業法では、宅建業者が売主となる場合について、売買代金の20%を超えてはならないとされています。
宅建業者が売主となる売買では、消費者契約法ではなく、宅建業法が適用されます。
消費者団体訴訟制度

差止請求の制度は、2016年(平成18年)の消費者契約法改正により適格消費者団体による消費者団体訴訟制度が導入され、2009年(平成19年)6月に施行されています。
被害回復の制度は、2013年(平成25年)に消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律が制定されて、2016年(平成28年)10月に施行され、消費者被害回復訴訟の制度が開始されています。
特定適格消費者団体に被害回復の訴えを提起する権限が認められています。
差止請求の制度
適格消費者団体が、事業者の不当な行為について、是正の申入れと差止めを求める申入れ、ないし請求を裁判または裁判外で行い、消費者被害の未然防止、拡大防止を図る仕組みが、差止請求の制度です。
被害回復の制度
そこで、さらに消費者を厚く保護するために、2013年(平成25年)12月に消費者裁判手続特例法が制定、2016年(平成28年)10月1日に施行され、被害回復手続きの運用が開始されました。
被害回復手続は、事業者の不当な行為により、同じ原因で消費者が数十人程度被害を受けた場合に、金銭的な被害回復を図る消費者被害回復訴訟を提起することができる制度です。
適格消費者団体のうち、さらに認定要件を満たす団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人が、特定適格消費者団体です。
次の要件を満たす消費者被害が、被害回復手続の対象になります。
① 2016年(平成28年)10月1日以降に締結された消費者契約、または、2016年(平成28年)10月1日以降の事業者の不法行為によるものであること。
② 同じ原因で、数十人以上被害が発生したものであること。
③ 次に該当する請求(事業者が消費者に対して金銭支払い義務のあるもの)であること。
- 契約上の債務の履行の請求
- 不当利得に係る請求
- 契約上の債務の不履行による損害賠償の請求
- 不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求
④ 契約の相手方である事業者(債務の履行をする事業者、消費者契約の締結を勧誘し、勧誘させ、勧誘を助長する事業者)に対する請求であること。
被害回復手続は、二段階構造となっています。
第一段階は、適格消費者団体のうちで、内閣総理大臣から認定を受けた特定適格消費者団体が手続きの主体になって、消費者に代わって、事業者に対して被害の集団的な回復を求める訴えを行ないます。
第二段階は、この被害者が被害を申し出ます。
被害回復手続は、消費者からみれば、通常の訴訟とは違って次の利点があります。
① 消費者は直接訴訟をする弁護士を探す必要がない。
② 消費者は二段階目の訴訟手続から参加するため、訴訟の時間を低減できる。
③ 1人で裁判を起こすよりも費用が抑えられる。
なお、被害回復手続きにおいては、拡大損害(契約目的以外の財産が滅失・損傷したことによる損害)、逸失利益(目的物の提供があれば得られたはずの利益)、人身損害(人の生命・身体を害した損害)は、回復手続の対象となる損害には含まれません。
ただし、精神上の苦痛を受けたことに対する損害の請求は、従前は回復手続きの対象となる損害には含まれていませんでしたが、2022年(令和4年)6月1日公布の改正消費者裁判手続特例法において、回復手続の対象となる損害に含まれるものとされました。
終わりに
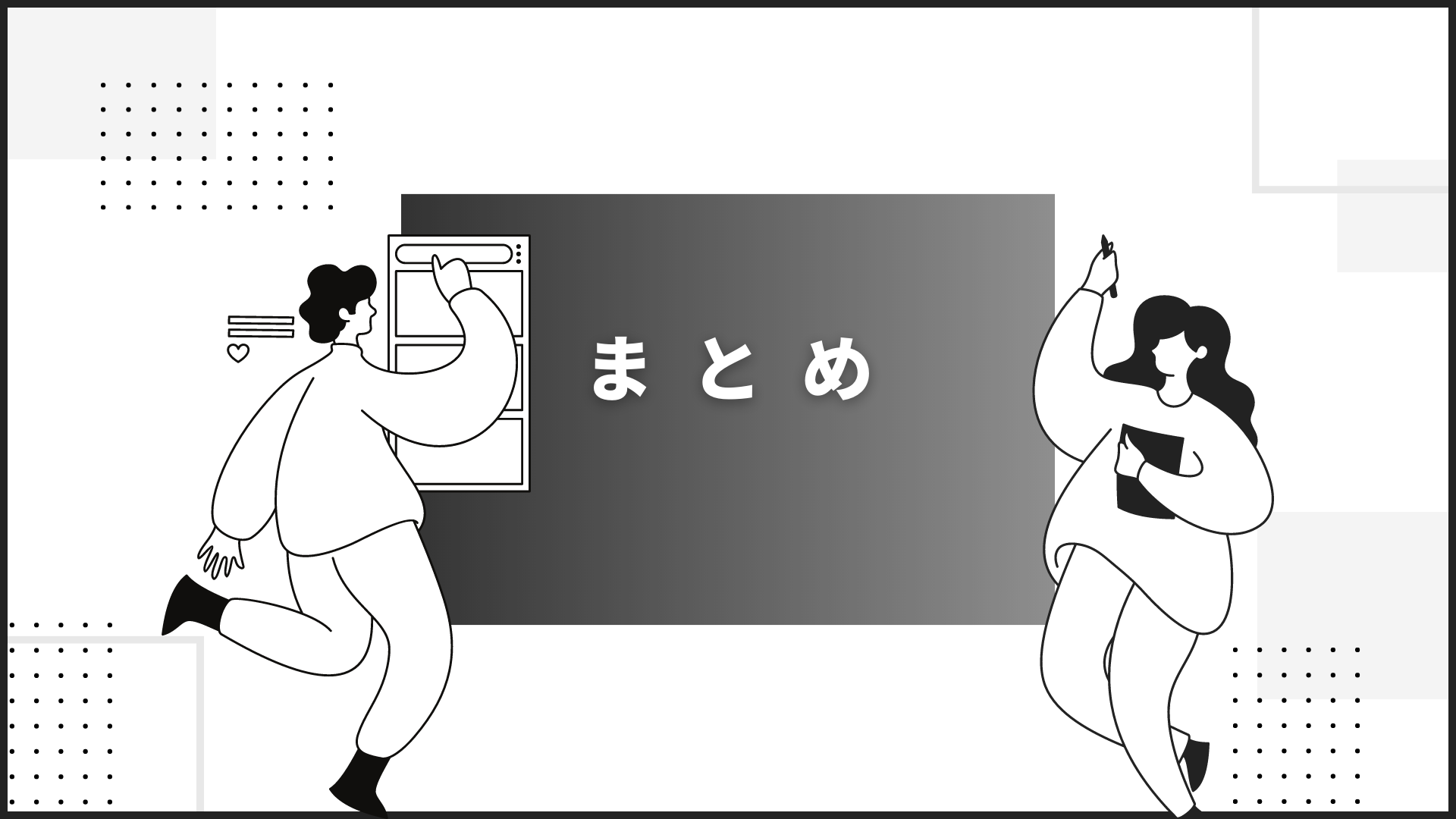
消費者契約法については、まず取引の当事者や不動産仲介業者の関係をみて、その契約が消費者契約法に該当するかどうかを確定しなければなりません。
事業者は、消費者契約に該当するものであるならば、消費者契約法による取消原因となるような、不適切な勧誘行為を行わないように留意することが求められます。
特に、個人が借主となる居住用賃貸借に関しては、最高裁判例判決がある「敷引特約」、「更新料支払特約」、「追い出し条項」の例を正しく把握し、対応するとよいでしょう。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
