
住まいとして考えるにあたり、区分所有マンションは一戸建てとはさまざまな面で違います。
1つには、マンションのような一棟の建物において構造上区分された物件は、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)によって制限があります。
区分所有マンションを検討する場合は、建物の区分所有について理解をしておく必要があります。
今回は、マンションなどの建物の区分所有について、お話し致します。
区分所有権・専有部分・共用部分の意義

区分所有権および専有部分
共用部分
共用部分には、例えば共同の玄関、階段、廊下、エレベーターなどの建物部分および配管、配線、エレベーターの機械などその建物の附属物である「法定共用部分」と、例えば集会室や管理人室のように、本来専有部分になりえる部分および附属の建物を規約で共用部分とした「規約共用部分」の2つがあります。
規約共用部分は、その旨の登記をしないと第三者に対抗できません。
共用部分に関する法律関係
② 共用部分は、規約で一部の区分所有者または管理者の所有とすることができます。
③ 共用部分に対する各共有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専用部分の床面積の割合によって決められます。
④ 共用部分の共有持分は、法律で別段の定めがあるときを除いて、専有部分と分離して処分することができません。
分離処分を許す規約の定めをしても無効です。
また、区分所有権が処分されれば、その区分所有者の共有持分もそれに従います。
⑤ 共用部分の管理に関する事項は、規約で別段の定めをしたときを除いて、集会で区分所有者および議決権の過半数によって決します。
ただし、共有部分の保存のために必要な行為は、各共有者が単独ですることができます。
⑥ 共用部分の変更は、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決定されます。
しかし、共用部分の変更でも、その形状または効用の著しい変更を伴わないものは、区分所有者および議決権の各過半数で決定できます。
⑦ 前記⑤、⑥の場合で、ある区分所有者の専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾を得なければならない。
⑧ 各共有者は、原則としても持分に応じて共用部分の負担に任じ、その部分から生ずる利益を収取します。
⑨ 区分所有建物の設置または保存に瑕疵(本来備えているべき性能や設備を欠いていること)があることにより、他人に損害を生じたときは、その瑕疵は共用部分の設置または保存にあるものと推定されます。
その結果、その瑕疵が特定の専有部分の設置または保存にあることが証明されない限り、区分所有者全員が賠償義務を負うことになります。
敷地に対する権利と法律関係

このような専用部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを「敷地利用権」といいます。
専有部分との分離処分の原則的禁止
ただし、規約で分離処分を許す旨を定めることができます。
原則どおり、分離処分できない場合に、これに反してなされた処分は無効ですが、そのことを知らなかった相手方に対しては、その無効を主張することができません。
ただし、その処分が、分離処分の禁止された専用部分および敷地利用権であることを登記した後になされたものであるときは、無効を主張できます。
管理組合・管理組合法人・管理者

区分所有建物並びにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体を管理組合といい、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます。
「管理組合法人」
管理組合は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となることを定めることができます。
これを管理組合法人といい、理事と監事が置かれます。
「管理者」
区分所有者は、原則として集会の決議で管理者を選任でき、管理者は、共用部分、附属施設、敷地などを保存し、集会の決議を実行し、契約で定めた権利を有し、義務を負います。
管理者および管理組合法人は、損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分などに生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求および受領について代理します。
また、その請求および受領に関し、区分所有者のために原告または被告となることができます。
規約と集会

建物、敷地、附属施設の管理・使用に関する区分所有者相互間の事項が規定されています。
規約を定める場合には、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければなりません。
また、規約によって、区分所有者以外の者の権利を害することはできません。
規約
一部共用部分(一部の区分所有者のみの共有に供されるべきことが明らかな共用部分)に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共有すべき区分所有者の規約で定めることができます。
規約は、悪専用部分、共用部分、建物の敷地、付属施設につき、それらの形状、面積、位置関係、使用目的、利用状況、各区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければなりません。
また、規約は、書面または電磁的記録により作成しなければなりません。
② 規約の設定・変更・廃止は、集会で区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により決定します。
③ マンションの分譲業者のように、最初に建物の全部を所有するものは、単独で規約を設定できるが、「公正証書」によって定めなければなりません。
④ 規約の効力は、区分所有者全員に及ぶが、区分所有者の特定承継人(区分所有者から区分所有権を譲り受けた者など)に対しても効力を生じます
⑤ 規約は、管理者が保管し、保管者は利害関係人から請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、その閲覧を拒んではなりません(電磁的記録の場合も含む)。
集会
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求できます。
② 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者の専用部分の床面積割合によります。
③ 集会の決議は、法律または規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の過半数で決定します。
④ 集会の議事につき、議長は書面または電磁的記録により議事録を作成し、管理者が保管し、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がない限り、その閲覧を拒んではなりません。
⑤ 集会の決議は、規約と同じように、区分所有者のほか区分所有者の特定承継人に対してもその効力を生じます。
⑥ 建物の一部が滅失したときは、集会において、各区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができます。
また、復旧決議があった場合、復旧決議に賛成しなかった区分所有者が有する自己の専有部分などの買取請求権の行使の相手方を、決議賛成者の全員の合意で指定することができます。
これを、買取指定者制度といいます。
ほかに、建替え決議があります。
建替え決議は、次に詳しくお話しします。
建替え決議

建替え決議を行う集会の招集者は、建替え決議を行う集会を招集するときは、少なくても2か月前までに招集の通知を発し、かつ建替えの要否を検討するために必要な事項も通知します。
また、当該集会の会日の少なくとも1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項に関する説明会を開催しなければなりません。
建替え不参加者に対する売渡請求
催告を受けた区分所有者は、催告を受けた日から2か月以内に回答しなければなりません。
もし2か月以内に回答しなければ、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされます。
この期間が経過したときは、建替え決議の賛成者、上記の建替え参加回答者、またはこれらの者全員の合意で指定された買受指定者は、この期間満了の日から2か月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(承継者を含む)に対し、区分所有権と敷地利用権を時価で売り渡すべき事を請求することができます。
そして、建替え決議の賛成者、建替え参加回答者、および区分所有権、敷地利用権を買い受けた各買受指定者(承継人を含む)は、建替え決議の内容により、建替えを行う旨の行為をしたとものとみなされます。
団地内の建物の建替え承認決議
団地内の建物の一括建替え決議制度
ただし、各団地内建物ごと(各棟ごと)に、それぞれその区分所有者および議決権の各3分の2以上を占める者が一括建替え決議に賛成した場合でなければなりません。
マンション敷地売却決議制度
従来であれば、共有物の処分としてマンション敷地利用権の共有者(各専有部分の所有者)の全員一致でなければできなかった、マンションおよびその敷地(借地権含む)の売却ができるようになりました。
すなわち、耐震性が不足しているために、特定行政庁により改正円滑化法第102条に定める要除却認定を受けたマンションにつき、区分所有者、議決権および敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の多数で、要除却認定マンションおよびその敷地(借地権含む)を売却する旨の決議をすることができることになりました。
また、新たに建築されるマンションについては、一定の要件を備え、かつ市街地環境の整備改善に資すると認められた場合、容積率の緩和措置を受けることができます。
それにより、土地および建物の更なる高度利用が期待できます。
その後、2020年6月24日に施行された建替え円滑化法の改正により、除却の必要性に係る認定の対象の拡充などが行われました。
① 除却の必要性に係る認定対象に、従来の耐震性不足のものに加え、以下が追加されました。
- 外壁の剥落などにより危害を生ずるおそれがあるマンション等
- バリアフリー性能が確保されていないマンション等
② 2022年(令和4年)4月1日に、団地における敷地分割制度の創設が施工されました。
- 要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において、敷地共有者の5分の4以上の同意により、マンション敷地の分割が可能
区分所有者・占有者の権利義務

区分所有者の権利と義務
② 区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理または使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはなりません。
③ 区分所有者は、共用部分、敷地、附属施設につき、ほかの区分所有者に対して有する債権、または規約や集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権および建物に備え付けた動産の上に「先取特権」を有します。
④ 前記③の債権は、債務者である区分所有者の特定承継人に対しても請求することができます。
賃借人などの占有者の権利と義務
ただし、意見陳述権があるだけで、議決権はありません。
② 占有者も区分所有者と同様、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはなりません。
③ 占有者は、建物敷地付属施設の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。
義務違反者に対する各種措置

共同の利益を守るために、区分所有法で「義務違反者に対する措置」という条項が設けられています。
共同利益に反する行為の停止等の請求
この請求のための訴えを提起するには、区分所有者および議決権の各過半数による集会の決議によらなければなりません。
専有部分の使用禁止の請求
この決議は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数が必要です。
区分所有権等の競売の請求
この決議も、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数が必要です。
占有者に対する引渡請求
この決議も、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数が必要です。
終わりに
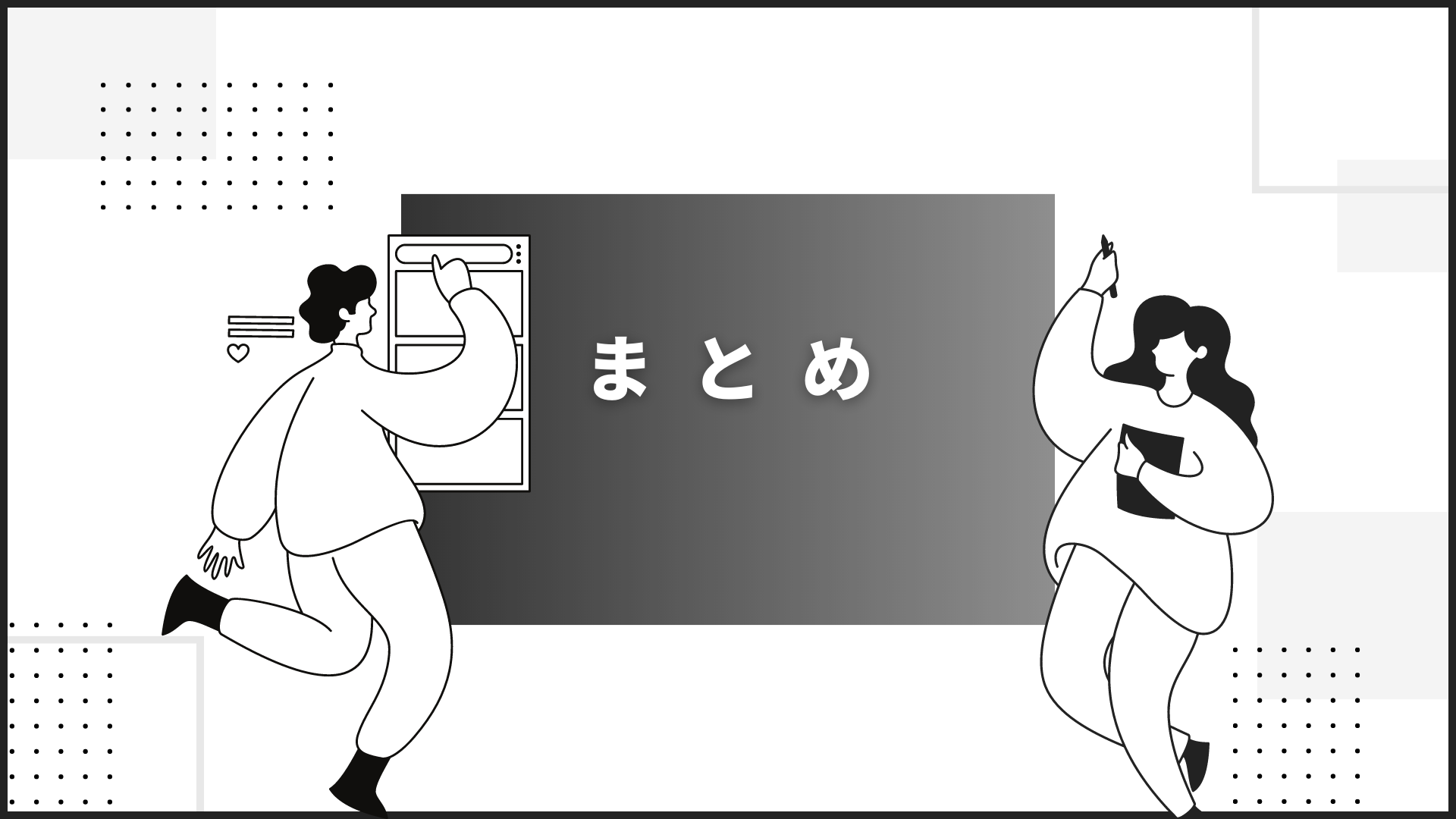
マンションのような共同住宅の建物においては、共同生活を行うためのルールがあり、ルールを守る必要があります。
その根拠となっているものが区分所有法であり、マンションごとに定められている規約です。
区分所有建物を購入することを考えている、または承継する人は、区分所有法を理解し、規約に必ず目を通しましょう。
それは、ワンルームマンションであっても区分所有建物であれば同様です。
ワンルームマンション投資を検討している方は、投資の部分にのみ集中しがちで、区分所有法や規約に対しては希薄なことが多いです。
運用を不動産業者が行うようなサブリース契約を取り交わしている場合は、特に関心がないかもしれません。
管理規約に目を通しておけば、将来の修繕積立金の値上げなどに気付けたかもしれないのです。
また、建替え決議に関しては、区分所有者および議決権の5分の4以上の多数で賛成を得なければなりません。
これが大きなハードルとなっています。
相続では、不動産を共有すると共有者との合意が困難になることから、様々な対策を検討します。
区分所有建物は、既に多数の人との共有状態になっていますので、その合意形成が難しいことが容易に想像できます。
建替えを行うにも多額の予算が必要です。
予算がなく老朽化したマンションは将来どうなってしまうでしょうか。
取り壊しを行うこともできず、建物だけが残されてしまうかもしれません。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
