
あまり気にされない方もいらっしゃるでしょうが、不動産の契約や決済取引の日取りを決めるときに、六曜による日柄を気にされることも多いです。
大切な取引を行うのですから、縁起の良い日を選びたいと思われるでしょうし、縁起の悪い日は避けたいと思われるでしょう。
六曜にはその名のとおり6つの曜がありますが、それぞれどのような意味があるのでしょうか。
「大安」や「仏滅」などは聞いたことがある方も多いでしょうが、他の曜についてはご存じでない場合もあるでしょう。
また、「十二直」という暦注や、「天赦日」や「一粒万倍日」などの選日もあります。
今回は、不動産契約を行う日柄や六曜などの暦について、お話しいたします。
不動産契約に関わる暦・六曜

六曜は中国大陸で生まれたとされており、日本に伝来したのは、一説には14世紀の鎌倉時代といわれています。
江戸時代に入ってから六曜の暦注は流行したようですが、その名称や解釈、順序は少しずつ変化があったようで、六曜が「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」に確定したのは江戸後期・幕末以降のことのようです。
なお、「仏滅」や「友引」という、仏事と関連があるように見える言葉が使われていますが、仏教とは関係がありません。
その後、明治維新による西洋化の一環として、政府はそれまで採用していた天保暦(太陰太陽暦の一つ)を太陽暦に改めました。
太陽暦へ改暦されるにあたり、「吉凶付きの暦注は迷信である」とされ、政府は吉凶に関する暦注を禁止し、尋常小学校の教科書にも迷信であると記載されたようです。
しかしながら、この暦注の廃止は人々の反発を招き、六曜はかえって重視されるようになったともいわれています。
吉凶を表す言葉・六曜
順番は、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の順です。
なお、意味の解釈はさまざまで、どれが正しいという基準はないようです。
この文章では、一般的な解釈を示していきます。
旧暦とは
グレゴリオ暦は太陽の動きをもとにして作られているため、「太陽暦」と呼ばれています。
一方で、太陽暦が明治6年に採用される以前の日本では、月の満ち欠けをもとに、季節を表す太陽の動きを加味して作られた「太陰太陽暦」が使われていました。
「太陰太陽暦」といっても、歴史の中ではたくさんの暦法による計算の規則が使われてきました。
太陽暦への改暦の直前に使われていた「天保暦」と呼ばれる暦法を、一般的には「旧暦」と呼んでいます。
旧暦を含む太陰太陽暦では、月が新月になる日を月の始まりと考え、各月の1日としました。
それから翌日を2日、その次の日を3日と数えました。
そして、次の新月の日がやってくると、その日を次の月の1日としました。
新月から新月までは、平均して約29.5日の間隔です。
12か月では、約29.5日×12か月=約354日となり、太陽暦の1年より約11日短くなります。
そのままでは季節とずれてしまいます。
そこで太陰太陽暦では、暦と季節のずれが大きくなってきて、ひと月分に近くなると「閏(うるう)月」というものを入れて、ずれを修正しました。
例えば、3月の次に閏月が入ると、その月は「閏3月」と呼ばれ、その年は13か月間あるということになります。
閏月は平均すると、19年に7回ほどの割合で入ります。
以上のような理由から、太陰太陽暦では同じ日付であっても、それを現在の暦に換算すると年ごとに違う日付になります。
例えば、現在の暦に切り替わる前の明治3年1月1日は現在の暦では2月1日ですが、翌年の明治4年1月1日は現在の暦では2月19日です。
現在でも、旧暦に合わせて祭りなどの行事が行われることがあるため、旧暦による日付が暦に記載されていることがあります。
先勝
一般的には、急ぐことは吉。
午前は吉、午後は凶とされています。
不動産取引を行う場合は、午前中に行うと縁起が良いでしょう。
友引
一般的には、友を引くと解されます。
祝い事は良いが、葬式などの凶事を忌みます。
朝夕は吉、正午は凶などとされています。
不動産取引を行う場合は、お昼ごろは避ける方が良いでしょう。
先負
一般的には、何事も控えめに平静を保つ日です。
午前は凶、午後は吉とされています。
不動産取引を行う場合は、午後に行う方が良いでしょう。
仏滅
一般的には、万事凶です。
ただし、葬式や法事は構わないとされています。
不動産取引を行う日としては、縁起が良くないといえるでしょう。
一方で、「物滅」として「物が一旦滅び、新たに物事が始まる」と解釈し、物事を始めるには良い日であるという解釈もあります。
大安
一般的には、万事大吉です。
特に婚礼に良いとされています。
不動産取引を行う日としては、六曜の中では最も縁起が良いでしょう。
赤口
一般的には凶日であり、特に祝事は大凶です。
火の元や刃物に要注意。
正午は吉、朝夕は凶とされています。
不動産取引を行う日としては縁起が良くないでしょう。
取引を行う場合は、お昼前後に行うと良いでしょう。
不動産契約に関わる暦・中段、下段など
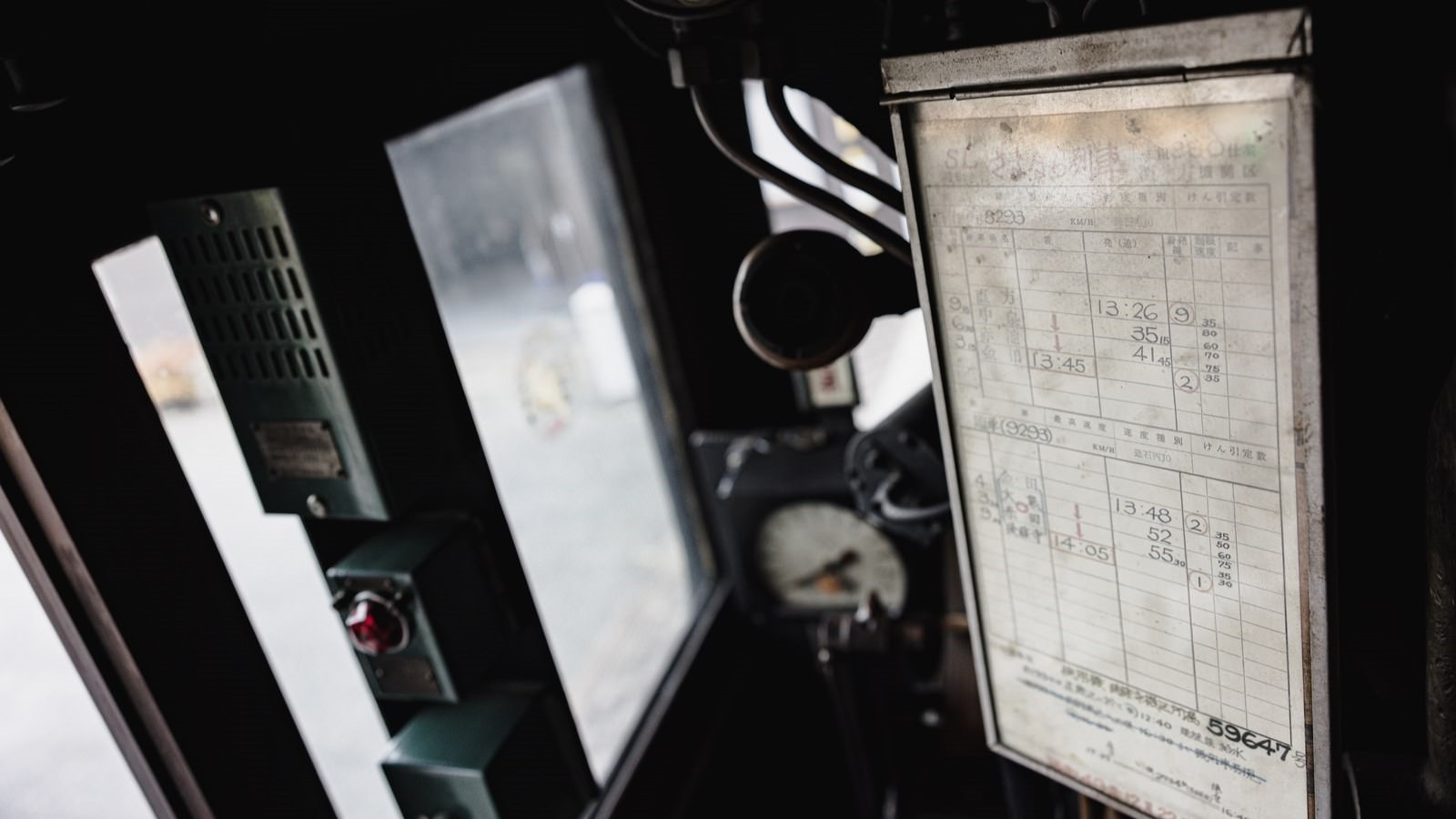
その多くは、干支の組み合わせによって日々の吉凶を判断しています。
例えば、「暦の中段」あるいは「十二直(じゅうにちょく)」と呼ばれるものや、「暦の下段」に記載されていた選日もあります。
「天恩日(てんおんにち)」や「天赦日(てんしゃにち)」などは「暦の下段」に記載されていた選日です。
その他にも「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」「三隣亡(さんりんぼう)」なども選日の一種です。
中段(十二直)
十二直(じゅうにちょく)とも呼ばれます。
十二直の「直」は「当たる」という意味があり、よく当たる暦注と信じられていたと考えられます。
十二直には、「建(たつ)」「除(のぞく)」「満(みつ)」「平(たいら)」「定(さだん)」「執(とる)」「破(やぶる)」「危(あやぶ)」「成(なる)」「収(おさん)」「開(ひらく)」「閉(とづ)」の12種類があります。
古くから中国では、一定の位置にあって動かない北極星を中心に、1日1回転する北斗七星に興味を示していました。
そして、北斗七星のひしゃくの部分(斗柄、剣先星)が夕方どの方角を向いているかを、その方位の十二支に当てはめて各月の名を決め、暦に記しました。
これを月建(げっけん)といいます。
冬至(旧暦11月)には斗柄が真北(十二支の子の方角)を指す(建・おざす)ため、建子の月と名づけました。
同じように、12月は丑、正月は寅…という要領で各月を名づけました。
そして、その節月と同じ十二支を持つ最初の日を「建」とし、以後順に「除」「満」…と配していきます。
例えば1月の月建は寅なので、1月節(立春)後の最初の寅の日が「建」となり、次の卯の日には「除」、辰の日には「満」…と順に配当します。
原則として十二直は12のサイクルですが、毎月の節入りの日のみ、その前日と同じ十二直を配しています。
十二直の意味の解釈は時代によって少しずつ異なっているようです。
現在ではほとんど使われなくなりましたが、建築や引越しの吉凶を見るために使われることがあります。
下段(天赦日などの選日)
「暦の下段」に記載されていた選日には、「天恩日(てんおんにち)」「母倉日(ぼそうにち)」「月徳日(げつとくにち)」「天赦日(てんしゃにち)」「大明日(だいみょうにち)」「重日(じゅうにち、ちゅうにち)」「復日(ふくにち、ふくび)」「帰忌日(きこにち、きいみび)」「血忌日(けこにち、ちこにち、ちいみび)」「往亡日(おうもうにち)」「五墓日(ごむにち)」「凶会日(くえにち)」「黒日(くろび)」「大禍日(たいかにち)」「狼籍日(ろうじゃくにち)」「滅門日(めつもんにち)」があります。
特に「天赦日」は、百神が天に会合し、天が万物を許す日であり、万事にわたって吉とされています。
縁起が良い日として選ばれます。
その他(一粒万倍日など)
「八専(はっせん)」「十方暮(じっぽうくれ)」「三隣亡(さんりんぼう)」「天一天上(てんいちてんじょう)」「一粒万倍日(いちりゅうまんばいにち)」「不成就日(ふじょうじゅび)」「大犯土・小犯土(おおづち・こづち)」「三伏(さんぷく)」「庚申(こうしん、かのえさる)」「甲子(かっし、こうし、かし、きのえね)」があります。
特に「一粒万倍日」は、ひと粒のモミが万倍にも実る稲穂になるというめでたい日のことで、万事を始めるには良い日です。
縁起が良い日として選ばれます。
特に仕事始め、開店、種まき、出金などは吉ですが、増える意味があるため、借金や借り物は凶とされています。
一方で「不成就日」は、その名のとおり万事不成就の日で、事を起こすには良くない日です。
また、「三隣亡」は大凶の日で、特に三件隣まで滅ぼすとされ、建築関係の仕事には縁起の悪い日とされています。
終わりに
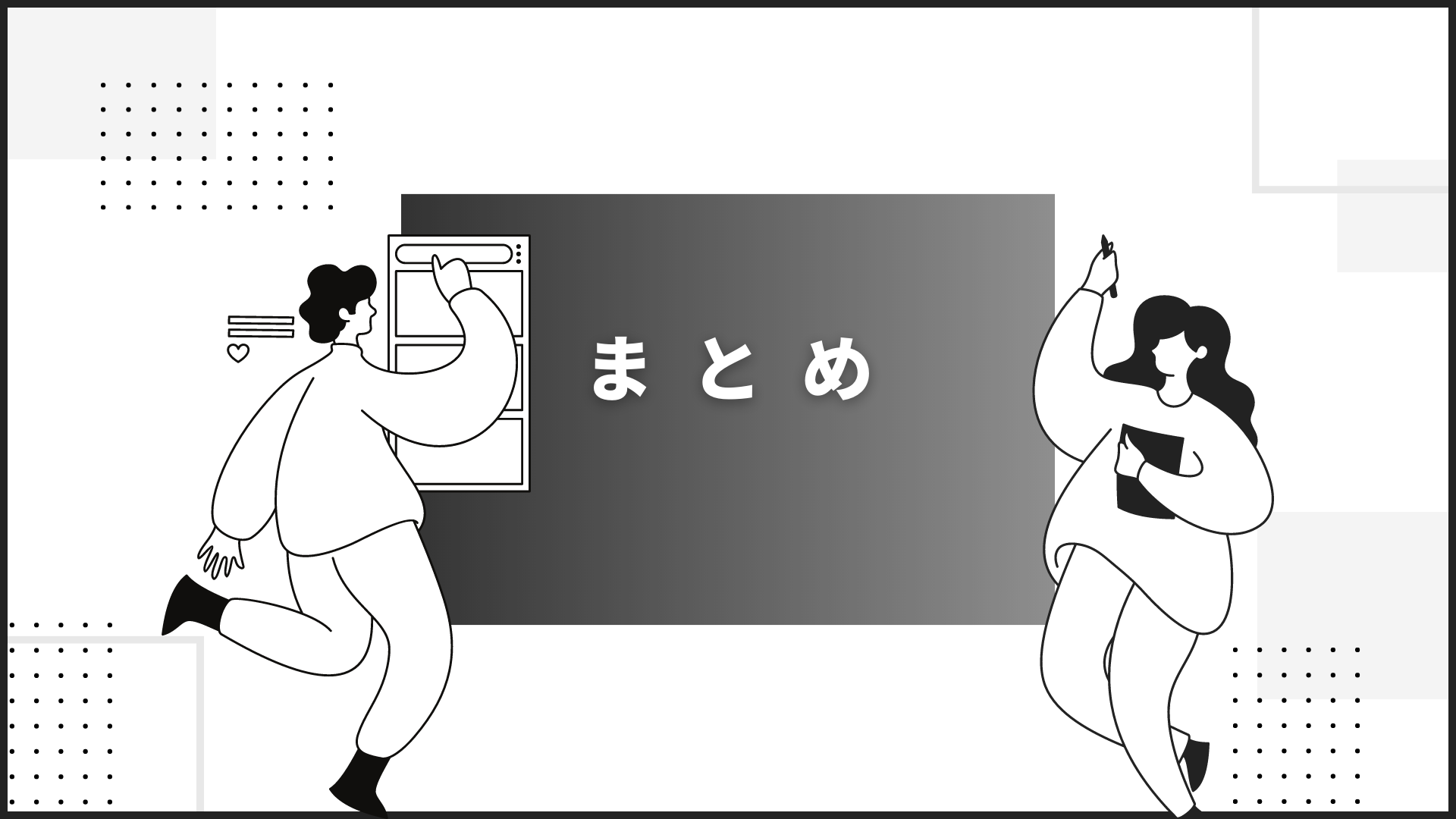
暦の制定は、月の配列が変わることのない現在の太陽暦とは違って非常に重要な意味をもち、朝廷や後の江戸時代には幕府の監督のもとにあったそうです。
太陰太陽暦は、明治時代に太陽暦に改められるまで続きました。
最近は六曜などの暦を気にされる人は少なくなっているように感じますが、古来より人々への影響が大きかったことがうかがえます。
明治維新によって樹立された明治政府は、西洋の制度を導入して近代化を進めました。
暦についても欧米との統一を図り、太陽暦(グレゴリオ暦)への改暦を発表しました。
準備期間がほとんどなく、本来ならば明治5年12月3日が、新しい暦では明治6年1月1日になってしまったため、国内は混乱したそうです。
しかし、福沢諭吉などの学者は合理的な太陽暦を支持し、普及させるための書物を著しました。
縁起の良い日を意識しすぎるとそれにとらわれてしまい、スケジュールに支障をきたすことも考えられます。
しかし、多くの人にとって不動産取引は頻繁にあるものではなく、また影響力が大きいものです。
縁起の良い日があれば、ぜひその日に合わせて調整してみられてはいかがでしょうか。
執筆者
MIRAI不動産株式会社 井﨑 浩和
大阪市淀川区にある不動産会社を経営しています。不動産に関わるようになって20年以上になります。
弊社は、“人”を大切にしています。不動産を単なる土地・建物として見るのではなく、そこに込められた"想い"に寄り添い受け継がれていくよう、人と人、人と不動産の架け橋としての役割を果たします。
